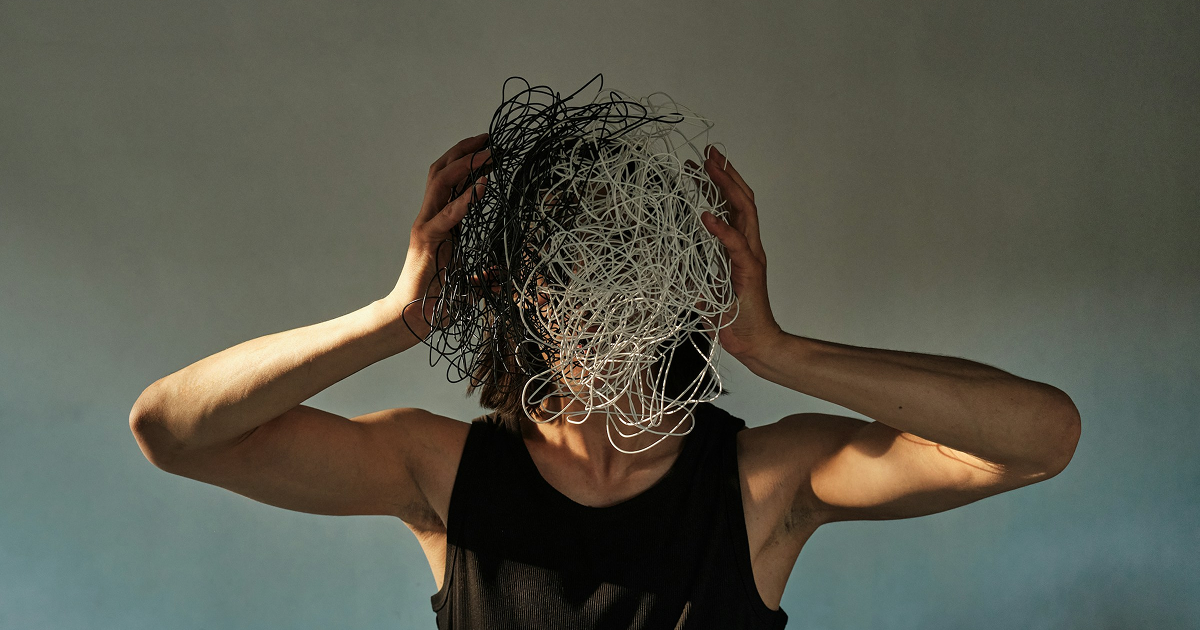夢を忘れてしまうのはどうして?睡眠の質を上げる意外な食べ物とは?
たくさん睡眠をとったはずなのに、授業中にどうしても眠くなってしまう。そんな経験がある方もいるのではないでしょうか。 起きていなければならない状況で、何とかして眠気を覚まそうと工夫を凝らしたことがある人も少なくないはずです。 しかし、もしかすると問題は「睡眠時間」ではなく、「睡眠の質」にあるのかもしれません。今回は睡眠の質に注目し、「良い眠り」について考えていきましょう。 前回のコラムはこちらです。 https://mag.viestyle.co.jp/columm22/ 睡眠妨害だけじゃない!ブルーライトの効果的な一面とは? 良い睡眠のために「睡眠の量」と「質」のどちらがより重要なのでしょうか?もちろん個人差はありますが、睡眠にはある程度の「量」が欠かせないのは確かです。一方で、どれだけ深く眠れているか、つまり「質」も重要なポイントです。どちらか一方が重要だと言い切ることは難しく、両方が揃ってこそ良質な睡眠が得られるといえます。 また、睡眠の質に悪影響を及ぼす要因もわかってきています。たとえば、眠りにくくする要因の一つが、寝る前のブルーライトです。網膜にはRGB(レッド、グリーン、ブルー)の3種類の光を感知する錐体細胞があり、ブルーライトはその中でも短波長の光にあたります。特にデジタル画面にはこの短波長の光が多く含まれているため、就寝前にスマートフォンやタブレットを使うと、網膜神経節細胞がブルーライトを感知し、脳に「朝だ!起きろ!」と信号を送ります。これにより、脳が覚醒し、入眠が遅くなってしまうのです。 人間の体は、24時間の生活リズムである「サーカディアンリズム」を持ち、光がそのリズムを整える重要な要素となっています。そのため、ブルーライトは睡眠の質に大きな影響を与えます。一方、朝にブルーライトを浴びると、目覚めが良くなりやすいこともわかっています※。自然の光を浴びることで、覚醒が促進され、スムーズな朝のスタートが切れるのです。長距離トラックのドライバーや、長時間フライトのパイロットなども、時差ボケを緩和するために「ライトセラピー」と呼ばれるブルーライトを使った療法を利用することがあります。つまり、適切なタイミングであれば、ブルーライトは有効な手段ともいえるのです。 一般的にブルーライトは「悪者」として扱われがちですが、寝る前以外では覚醒をサポートする側面もあります。例えば、スマホのナイトモードはブルーライトをカットし、画面を少し黄色味がかった色にすることで夜のリラックスに役立てています。このように、朝と夜でブルーライトの使い分けを意識することが、質の良い睡眠と日中の覚醒度を保つために役立つかもしれません。 ※出典:https://academic.oup.com/sleep/article/47/Supplement_1/A431/7654950, 2024年11月6日参照 夢を見る人と見ない人の睡眠の違いは? 睡眠の質と関わりが深い「金縛り」の仕組みについてもご紹介しましょう。 まず、睡眠にはいくつかのステージが存在します。入眠後、深いノンレム睡眠に入ると、脳波もゆったりとした1〜3Hzのデルタ波が見られるようになり、この段階で記憶の固定などが行われます。その後、眠りが浅くなり目が動く「レム睡眠」に移行します。このレム睡眠中に、金縛りが起こるのです。金縛りは、脳が覚醒状態に近いものの、体が動かないために発生し、夢を見ている状態に近い感覚が引き起こされると考えられています。 「夢も見ないほどぐっすり眠れた!」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。また、「毎日夢を見るから眠りが浅いのかも」と思ったことがある方もいるのではないでしょうか。しかし実際には、夢は主にレム睡眠中に見られており、睡眠の質を直接示すものではありません。 夢は経験がシナプスに記憶として残るプロセスで生まれると言われます。覚醒中はシナプスが活発に働いていますが、睡眠中にはその活動が抑えられるため、夢はすぐに忘れられてしまう傾向があります。そして、「毎日夢を見る」と感じる人は、たまたまレム睡眠のタイミングで目覚めているため、夢を覚えているのです。 つまり、多くの人は夢を見ていますが、レム睡眠中に起きない限り忘れてしまうだけなのです。そう考えると、良い夢を見て覚えている人は、幸せなスリープサイクルを楽しんでいると言えるかもしれませんね。 音や食べ物で睡眠の質が変わる!? 睡眠の質を高めるうえで、睡眠ステージも重要な要素です。たとえば、ノンレム睡眠(特に徐波睡眠)時には、ゆったりとした音を聞かせることで、その状態を維持しやすくなるとされています。具体的には、脳が1〜3Hzのデルタ波を発しているときに、そのリズムに合わせた音を流すことで、深い眠りを持続させる効果が期待できます。光だけでなく、音も脳のリズムに影響を与え、質の良い深い睡眠のサポートに役立つのです。 また、睡眠の質には、音や光以外にも食べ物や飲み物が大きく影響を与えます。アルコールの回でも紹介しましたが、適度な飲酒はリラックス効果をもたらし、良質な睡眠に繋がることがあります。しかし飲み過ぎると逆に眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる原因にもなってしまいます。睡眠を促進するためには、適切なタイミングと量を守ることが大切なのです。 このように、睡眠の質を高めるためには、音、光、食事のタイミングなど、さまざまな要素が関わっています。どれか一つの要素に注目するだけでなく、総合的に見直していくことが、より良い睡眠を得るための鍵と言えるでしょう。 https://open.spotify.com/episode/25ZFcvkz3vnknJgI9cOJJ9?si=GnbQFtCoRuCqOCeccEfXxg 睡眠の質を高める方法として、メラトニンを増やす食事も注目されています。時差ボケ対策のサプリメントとしても知られるメラトニンですが、自然に増やす手段として「牛乳」が効果的とされています。特に夜間に搾乳された牛乳は、昼間の牛乳に比べてメラトニンの含有量が約10倍も高いとされ、メラトニンが豊富な「ナイトミルク」としても注目されています。このような牛乳は、まるで自然の睡眠補助剤のような役割を果たします※。 また、キウイやさくらんぼなどのフルーツも、睡眠の質を向上させる効果があるというエビデンスが示されています。さらに、ビールの香り付けに使われるホップもリラックス効果があり、入眠をサポートするとされています。これらの食品を寝る前に取り入れることで、ぐっすり眠れる可能性が高まります。 このように、食べ物や飲み物の選択も、快適な睡眠に影響を与える要素です。日中の活動やリラックス習慣と合わせて、睡眠を助ける食材を取り入れることで、より良いスリープサイクルを実現できるかもしれません。 ※出典:https://www.milkgenomics.org/?splash=medicating-the-elderly-with-night-milk, 2024年11月6日参照 まとめ 睡眠の質を左右する要因には、さまざまなものがあります。たとえば光の影響では、ブルーライトは寝る前には悪影響を及ぼすものの、朝や日中の覚醒には効果的です。また、音も深い睡眠中の脳の状態をサポートする手助けとして利用できます。食べ物では、夜に搾った牛乳は昼間のものに比べてメラトニンの含有量が約10倍とされ、リラックス効果が期待されています。 将来的には、快適な睡眠を促す食べ物や飲み物、さらにはその効果を最大限に活用できるデバイスが登場するかもしれません。睡眠環境のさらなる改善に役立つ技術が進むことで、より健康的で質の高い睡眠が身近になることを期待したいですね。 🎙ポッドキャスト番組情報 日常生活の素朴な悩みや疑問を脳科学の視点で解明していく番組です。横丁のようにあらゆるジャンルの疑問を取り上げ、脳科学と組み合わせてゆるっと深掘りしていき、お酒のツマミになるような話を聴くことができます。 番組名:ニューロ横丁〜酒のツマミになる脳の話〜 パーソナリティー:茨木 拓也(VIE 株式会社 最高脳科学責任者)/平野 清花 https://open.spotify.com/episode/73ln9cr7EdI3Zyptf2AY2O?si=STeged6ETkqEUkaz_XULIw 次回 次回にコラムでは、見たい夢を見られる『ドリームエンジニアリング』についてご紹介します。 https://mag.viestyle.co.jp/columm24/