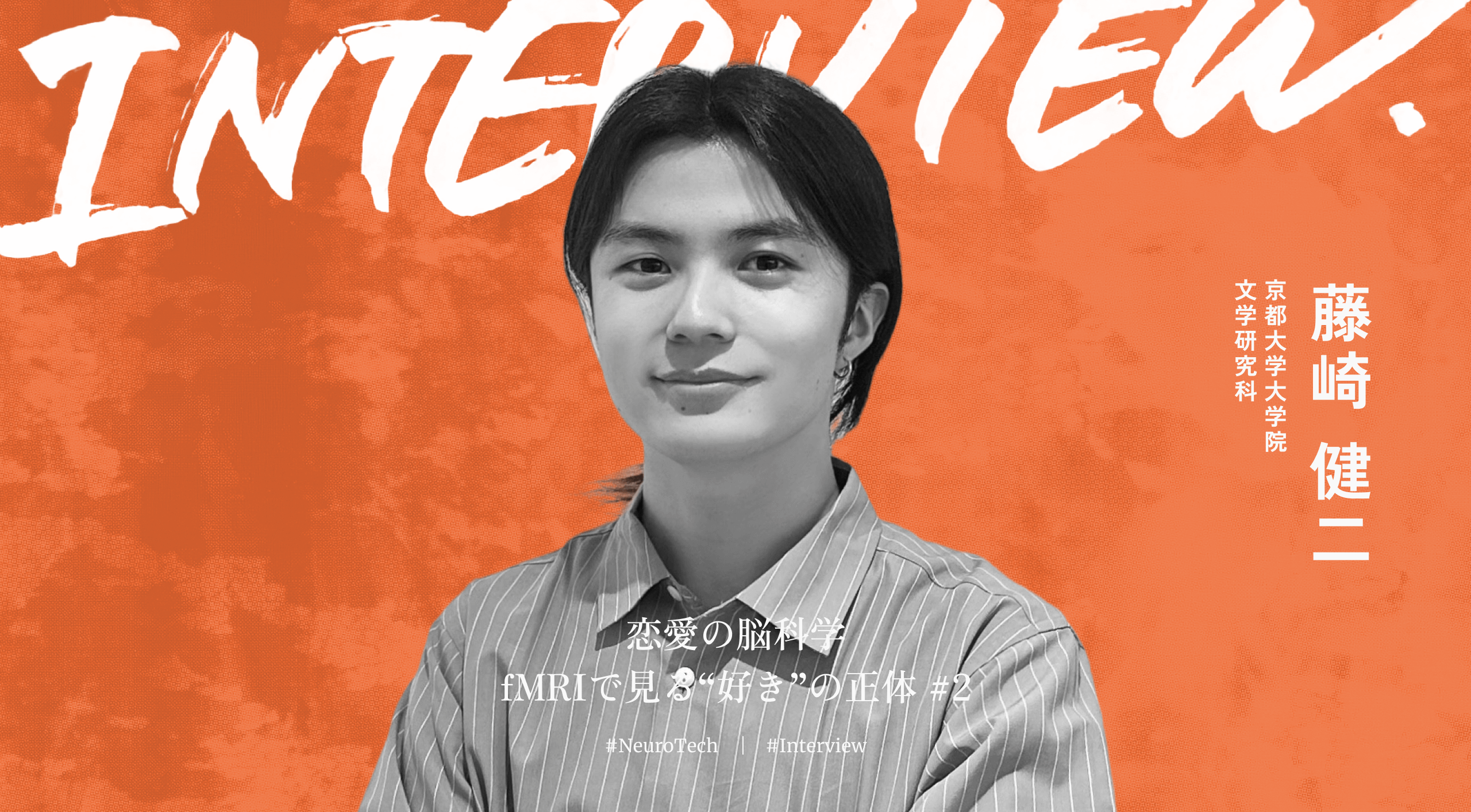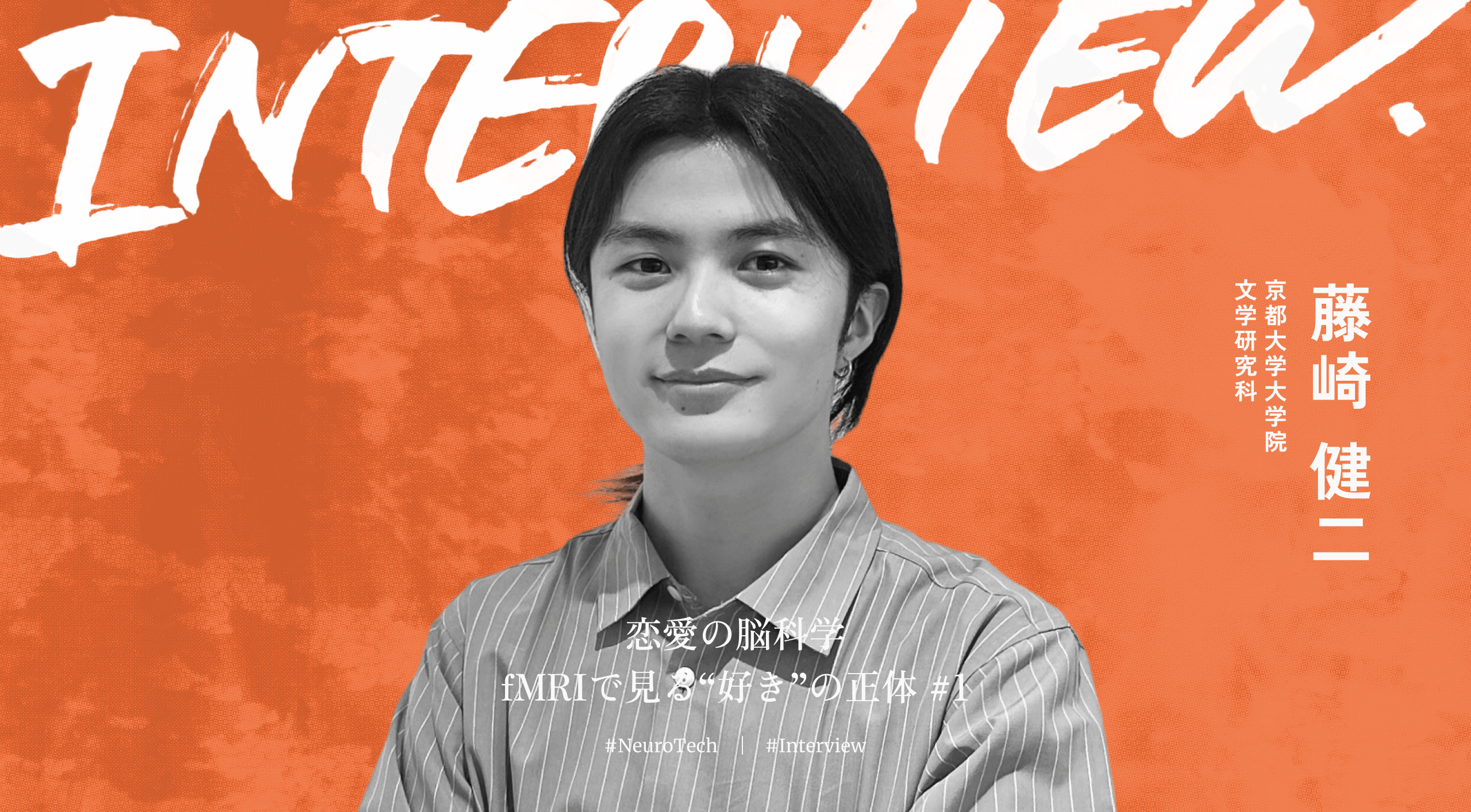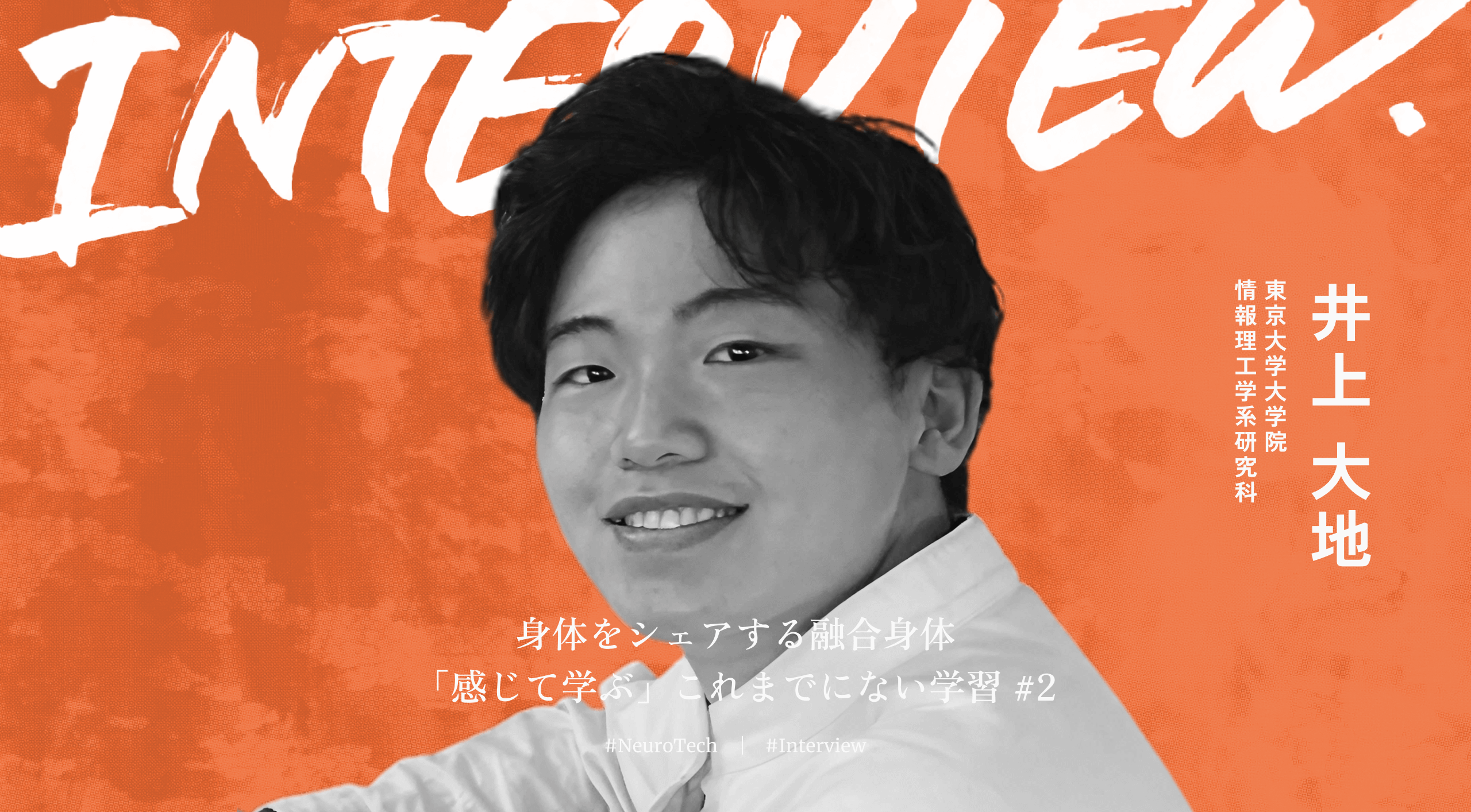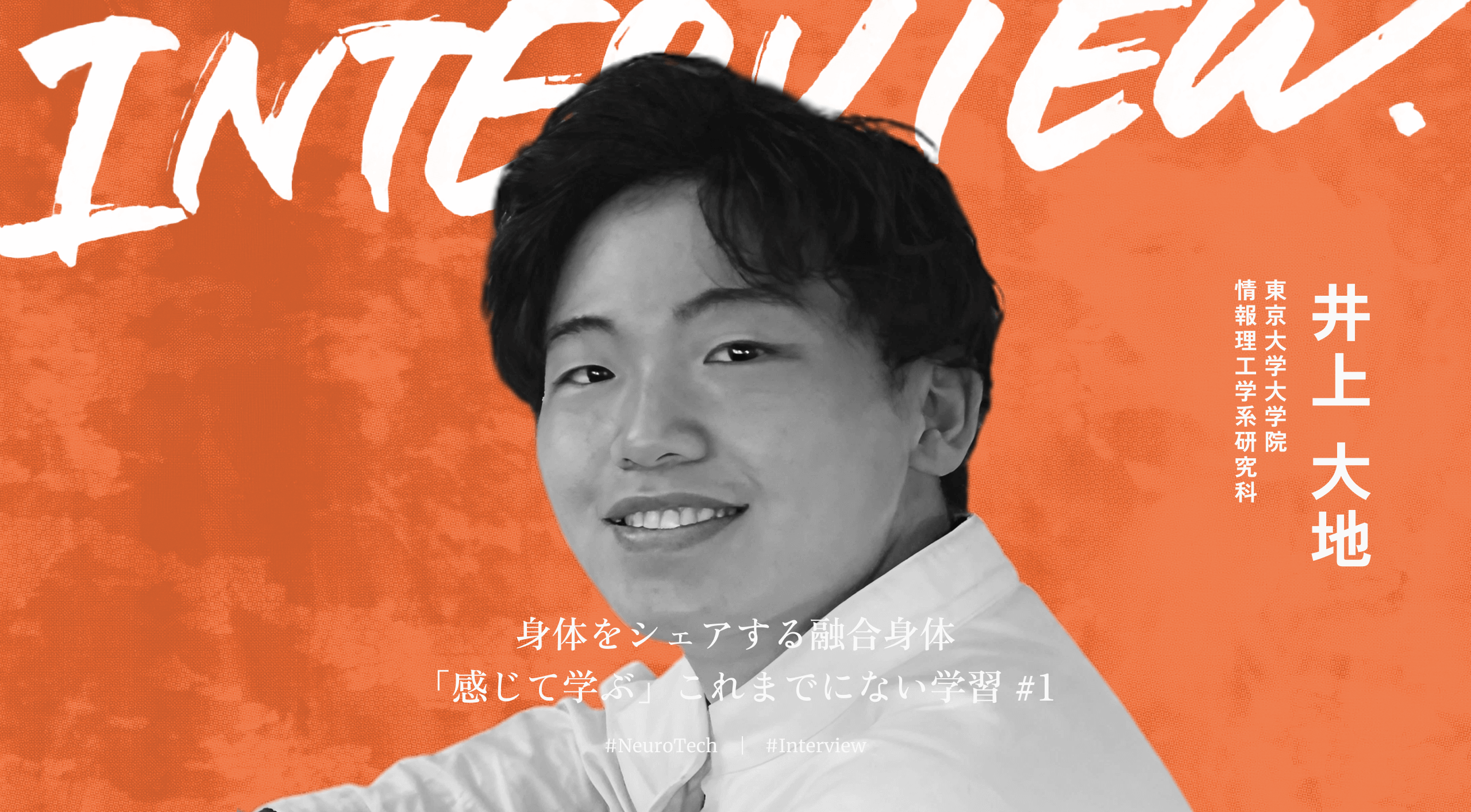自分の“好き”に従い研究の道へ:『恋愛の脳科学』研究者・藤崎健二さんの背景と原点
今回は、京都大学大学院で「恋愛の脳科学」の研究に取り組まれている藤崎さんにお話を伺いました。インタビューの前半では、藤崎さんの研究に至るまでの背景やこれまでの研究成果などについて詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。 https://mag.viestyle.co.jp/interview05/ インタビューの後半では、藤崎さんのパーソナルストーリーに焦点を当て、幼少期の生活や現在の趣味、研究に関するエピソードなどについて伺いました。 研究者プロフィール 氏名:藤崎 健二(ふじさき けんじ)所属:京都大学大学院 文学研究科 博士後期課程研究室:阿部研究室研究分野:恋愛、対人認知、fMRI 就職か進学かーー背中を押したのは自身の経験と一冊の本 ── まずは改めて簡単に自己紹介をお願いします。 現在は京都大学大学院文学研究科に所属し、研究に取り組んでいます。学部時代は慶應義塾大学理工学部で、脳波や心拍などの生理指標の解析に取り組んでいました。その後、恋愛関係の維持や構築を支える脳の仕組みについて深く研究したいと思い、大学院から京都大学に進学しました。 ── 大学院への進学はいつから考え始めましたか? 大学3回生の冬頃から、大学院への進学を考え始めました。元々は大学卒業後に就職するつもりでしたが、就職活動を進める中で、自分の心の声に従って好きなことや楽しいと思えることを仕事にしたいと思うようになりました。そんなとき、学部時代に図書館で偶然手に取ったのが『人はなぜ恋に落ちるのか?: 恋と愛情と性欲の脳科学』という一冊でした。恋愛の脳研究を専門にする第一人者の研究に触れたことで、昔から関心のあった「恋愛のしくみ」について本格的に研究したいという気持ちが強まり、大学院進学を決めました。 ── 始めは研究者になることは考えていなかったのですね。研究テーマの根幹となる、恋愛のメカニズムへの関心はどういった経緯でもつようになったのでしょうか。 自分自身の恋愛経験が大きかったと思います。これまでの人生の中で、特定の相手に強く惹かれる経験を通じて、恋愛がもたらす多幸感や心の揺れ動きは、日常で経験する感情とは質的に異なる、非常に特別なものだと実感しました。そうした体験から、なぜ恋愛はこれほどまでに人の感情や行動に強く影響を与えるのか、その背景にある脳の働きについて関心を持つようになりました。 ── ご自身の経験が研究へのモチベーションだったのですね。元々考えていた進路を変更する上で、苦労されたことはありますか? 周りの友人のほとんどが大手企業の就職を目指す中で、別の道を選ぶのは不安もあり、勇気が要る決断でした。そんな中、幸いにも同じように研究の道を志す先輩方が身近にいて、その存在が自分の背中を押してくれました。 人生のモットーはイチロー選手への憧れから ── 子供のころは脳科学以外にどのようなことに興味を持っていましたか? 小さい頃から、生き物に強い興味がありました。幼稚園の頃は昆虫が好きで、「昆虫博士」と呼ばれていたこともあります。小学生になると犬を家に迎え、高校時代には海外の爬虫類などを飼育していました。今でもいろんな動物が好きですが、犬が1番愛おしいです。 ── 様々な生き物に関心をもち続けた半生だったのですね。子供のころからの興味が現在まで続いているとのことですが、他にも今の自分に影響を与えた出来事や影響を受けた人物はいますか? はい、元メジャーリーガーのイチロー選手から大きな影響を受けました。小学校から中学3年生まで野球を続けていたこともあり、当時からイチロー選手は馴染みのある存在でした。あるとき、読書感想文のために彼に関する本を読んだことをきっかけに、その生き方や考え方に深く共感し、自分も彼のように信念を持って道を切り開いていける人になりたいと思うようになりました。 ── 具体的にはイチロー選手のどのような姿に影響を受けたのでしょうか? 好きなことを徹底して追求する姿勢に、強く影響を受けました。イチロー選手が野球という好きなことに出会い、誰よりも打ち込んできたからこそ、あれだけの成果を残せたのだと思っています。その姿勢は、「好きなことや楽しいと感じられることを大切にしたい」という、私自身の価値観の原点となっており、大学院進学を決める上でも大きな指針になりました。 また、直面する課題に対して原因の仮説を立て、検証し、改善へとつなげていくというイチロー選手の姿勢にも強く惹かれました。単に努力するのではなく、常に思考を巡らせながら自分を高めていくその在り方に、深い知性と探究心を感じました。 とはいえ、「修学旅行でも握力トレーニングを終えるまでは友達と遊ばなかった」という彼のストイックさについては尊敬しつつも、自分にはまだ難しいと思ってしまいます(笑) 研究は楽しい!ーーこれからの研究者に伝えたいこと ── 普段はどのように過ごされているのですか? 研究活動が生活のほとんどを占めています。その他には、研究室のリサーチアシスタント業務や、学部時代にアルバイトとして勤めていた会社からの委託業務などに取り組んでいます。 ── 研究やその関連活動が生活の一部となっているのですね。息抜きとして何か取り組んでいることはありますか? 今は料理にハマっています。昔から美味しい料理が好きで、学部時代は服と食べ物にバイト代を費やしていました。しかし、3年前に東京から京都に引っ越したことで美味しいお店と出会う頻度が減ってしまったので、節約も兼ねて自分で料理をするようになりました。最近はお肉やチーズの燻製料理にハマっています。 ── 最後に、これから同じ領域に挑戦してみたい学生や若い研究者に向けて、メッセージをお願いします。 研究に興味がある方には、「研究は楽しい!」ということをお伝えしたいです。アカデミアには自分の興味関心を探究できる世界が広がっており、大変なことも多いですが、この道を選んで本当に良かったと思っています。 少しでも関心がある方は、ぜひ勇気を出して、実際に研究をしている方の話を聞いてみることをおすすめします。近い分野でご活躍されている研究者の方々とは、研究に関する議論を深めたり、将来的に共同研究を行うなどのかたちでつながりを持てれば幸いです。 NeuroTech Magazineでは、ブレインテック関連の記事を中心にウェルビーイングや若手研究者へのインタビュー記事を投稿しています。また、インタビューに協力していただける研究者を随時募集しています。 応募はこちらから → info@vie.style