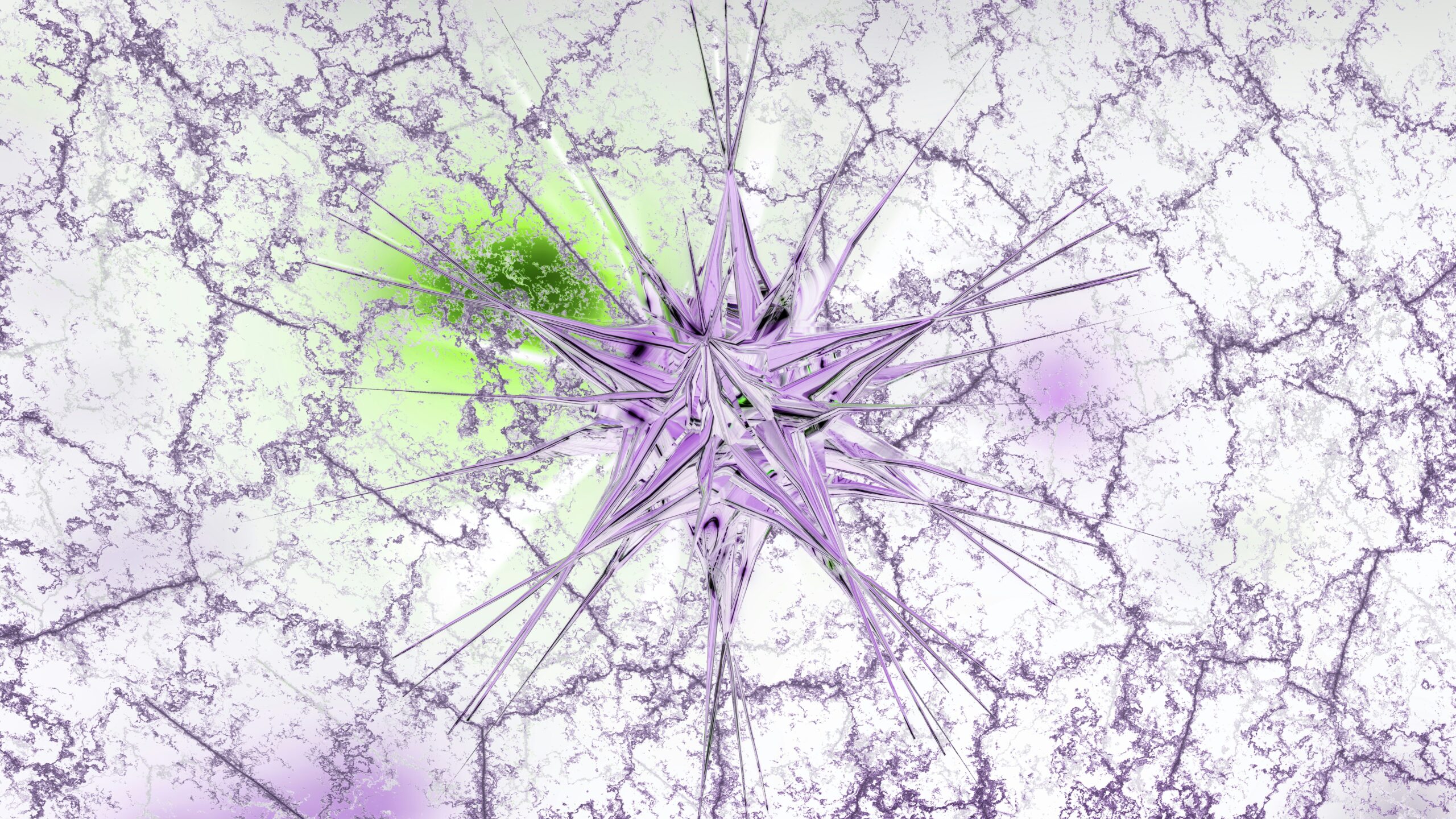職場の嫌がらせも情熱で跳ね返せる?──仕事への情熱が「退職したい」気持ちを左右する意外なメカニズム
職場の人間関係は、仕事のやりがいや満足度に大きく影響します。何気ない言動に傷ついたり、意図しない誤解が生まれたり、評価されていないように感じたり──そんな「心理的ストレス」は、決して珍しいことではありません。 こうしたストレスが溜まると、多くの人が「このままでいいのだろうか」と職場を離れることを考え始めます。しかし一方で、そんな環境でもへこたれずに仕事を続ける人がいるのも事実です。いったい何がその違いを生むのでしょうか。 2025年1月、トルコの複数の大学研究者によって発表された研究論文「From victims to survivors: Does job passion mitigate the impact of social undermining on turnover intention?」は、職場のストレスと「仕事への情熱」がどのように関わり合うのかを明らかにしました。 興味深いのは、「情熱」は強ければ強いほど良い、という単純なものではないという点です。同じように仕事へ強い思いを持っていても、ある人の情熱はストレスにしなやかに耐える力になり、別の人の情熱はストレスに押しつぶされやすくしてしまう——そんな“質の違い”があることが研究で示されています。 この記事では、職場でのネガティブな関わり(ソーシャル・アンダーマイニング)と、仕事への情熱が社員の「辞めたい気持ち」にどのように作用するのか、わかりやすく解説します。 職場の「陰湿な妨害」──ソーシャル・アンダーマイニングとは? まず押さえておきたいのが、研究で扱われているソーシャル・アンダーマイニングという概念です。聞き慣れない言葉ですが、簡単に言えば「職場における陰湿な妨害行為」のことを指します。たとえば、上司が意図的に部下を無視したり、同僚が陰で悪口を広めたり、わざと協力しないことで相手の評価を落とそうとしたりする行為がこれに当たります。 重要なのは、そうしたネガティブな言動が「意図的に行われている」と被害者が感じる点です。つまり、ただ機嫌が悪いから冷たかったというより、「相手を陥れよう」という悪意を持った振る舞いだと受け取られる場合、それがソーシャル・アンダーマイニングにあたります。 職場のネガティブな関わりが生む連鎖 当然ながら、こうした職場での嫌がらせは受ける側に大きなストレスを与えます。過去の研究でも、ソーシャル・アンダーマイニングによって仕事上のストレスが増大し、自己効力感(自分は仕事ができるという感覚)が低下し、組織への愛着心が薄れ、心理的な健康が損なわれ、さらには「職場を去りたい」という意向が高まることが報告されています。 実際、職場で足を引っ張られる経験をした人ほど、退職願望が強まる傾向は以前からよく知られており、被害者になった社員は遅刻や欠勤が増えたり、仕事の能率が落ちたりするといった悪影響も指摘されています。つまり、職場の人間関係の問題は放っておくと組織全体の生産性や人材流出にも直結しかねないのです。 では、もし職場でそんな陰湿な妨害を受けてしまったら、私たちはどう対処すればいいのでしょうか?もちろん職場いじめそのものをなくす取り組みが最優先ですが、最新の研究ではその問いに対してユニークな視点から光を当てています。 それが「仕事への情熱(ジョブ・パッション)」です。仕事に対する熱い思いが、嫌がらせによる心理的ダメージを和らげ、「辞めたい」という気持ちを変化させるかもしれない──そう仮説を立てたのです。 参考:Duffy, M. K., Ganster, D., & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. Academy of Management Journal, 45(2), 331–351. https://psycnet.apa.org/record/2002-13600-002 「仕事への情熱」には2種類ある?──調和型パッションと強迫型パッション 「仕事が大好き!」という情熱は、一見するとポジティブなエネルギー源に思えます。しかし、研究者たちは、この仕事への情熱には2つのタイプが存在すると指摘します。カナダの心理学者ヴァレランらの提唱する「デュアル・モデル」によれば、情熱には調和型(ハーモニアス)と強迫型(オブセッシブ)の2種類があるといいます。 調和型パッションとは、『やりたいからやる』という感覚に根ざし、自分の意思で柔軟にコントロールできている情熱です。 自分の意志で仕事に取り組めているため、努力していても心に余裕があり、生活全体のリズムも崩れにくいという特徴があります。仕事への没頭とプライベートのバランスが自然と取れており、「この仕事が好きだ」という気持ちが内側から湧き上がるような、内発的動機づけに支えられています。 こうした調和型パッションには、実証研究でも興味深い効果が示されています。仕事に対する満足度が高く、日々のパフォーマンスも安定しやすく、心理的な幸福感にもつながりやすいという報告が重ねて示されているのです。 また、過度なストレスで気力が尽きてしまう“燃え尽き(バーンアウト)”に陥りにくいだけでなく、結果として離職しにくい傾向も確認されています。仕事に向かう姿勢そのものが健全であるため、逆境にあっても揺らぎにくいと考えられています。 一方、強迫型パッションは、仕事に強くひきつけられているものの、その源にあるのは「やらなければならない」という義務感や不安です。仕事を通して自分の価値を保とうとする気持ちが強く、気づけば生活の多くを仕事が占め、心の余裕が失われやすくなります。 このタイプの情熱を持つ人は、他者からの評価や小さなトラブルにも反応しやすく、ストレスを抱え込みやすい傾向があります。研究でも、強迫型パッションが高いほど葛藤や不安が増し、バーンアウトのリスクや離職意向が高まることが示されています。熱心に働いているように見えても、内側ではプレッシャーに押されて消耗が進みやすい情熱のあり方と言えます。 このように、同じ「情熱」でもその質によって働き方や心の状態は大きく変わります。周りを見渡してみても、仕事を楽しみながら取り組む人もいれば、仕事に熱心なのにどこか余裕がなく、いつも緊張しているように見える人がいますよね。 今回の研究が明らかにしたのは、こうした「調和型」と「強迫型」という情熱の違いが、職場でのネガティブな言動に直面したとき──つまり、評価を下げられたり足を引っ張られたりする場面で、「辞めたい」と感じる度合いにどう影響するのかという点でした。 参考:Vallerand, R. J., Blanchard, C., Mageau, G. A., Koestner, R., Ratelle, C., Léonard, M., Gagné, M., & Marsolais, J. (2003). Les passions de l'âme: On obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85(4), 756–767. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14561128/ 逆境に強い人の秘密は「情熱の質」だった トルコの研究チームは、防衛産業に従事する401名の社会人を対象に調査を行い、職場で上司や同僚から妨害・嫌がらせ(ソーシャル・アンダーマイニング)を受けた経験と、各人の仕事への情熱タイプ、そして「この職場を辞めたいと思う気持ち」(退職意向)との関係を分析しました。 統計解析の結果、嫌がらせと退職意向を巡る以下のような明確なパターンが浮かび上がりました。 まず大前提として、上司からであれ同僚からであれ、職場で妨害行為を受けると退職したい気持ちは有意に高まることが確認されました。これは従来の研究結果とも一致する部分ですが、特に上司からの嫌がらせは退職意向との結びつきが強く、部下に対する上司の態度が社員の会社への留まり方針を大きく左右することが示されました。 一方、同僚からの嫌がらせも社員同士の関係悪化を通じて着実に「職場に居たくない」という思いを高める結果が出ています。 情熱タイプが変えるストレス反応 注目すべきは、この「妨害を受けたときに辞めたくなる気持ち」が、仕事への情熱のタイプによって大きく変わった点です。調和型パッションを持つ人は、上司や同僚からネガティブな行動を受けても、その影響が驚くほど弱まり、「辞めたい」と感じにくくなることがわかりました。 統計的にも、調和型パッションの高いグループでは、妨害と退職意向のつながりがほとんど見られないほどに縮小しており、情熱がストレスに対する防波堤のように働いているのが確認されています。 理不尽な場面に直面しても、「それでもこの仕事が好きだ」「自分にとって意味のある仕事だから続けたい」という内側からの動機づけが、気持ちを大きく揺らがせずに踏みとどまらせているのかもしれません。 一方で、強迫型パッションが強い人の場合はまったく逆の傾向が見られました。ネガティブな行動を受けると、その影響が増幅し、「もう続けられない」と感じやすくなるのです。統計的にも、強迫型パッションの高いグループでは、妨害と退職意向の結びつきがさらに強まり、情熱が低い人よりも急激に「辞めたい気持ち」が高まることが確認されています。 仕事に強く依存し、「結果を出さなければ」という思いに支えられているからこそ、妨害を受けたときに怒りや失望が大きくなり、強い逃避反応につながってしまうのかもしれません。情熱そのものは強いのに、むしろ心の負担が増えてしまうという、どこか皮肉な結果が浮かび上がっています。 脳と心理から見る「情熱」の不思議な効能 では、なぜ情熱のタイプによってストレスへの強さが変わるのでしょうか。その理由は、心理学の理論である自己決定理論によって説明できるかもしれません。この理論では、人が健やかに意欲を持って働くためには、自分の意思で選んでいるという感覚や、仕事をうまくやれているという手応え、周囲とのつながりを感じられることなど、いくつかの基本的欲求が満たされていることが重要だとされています。 調和型パッションは、こうした欲求が自然に満たされている状態で生まれる情熱です。だからこそ、仕事で壁にぶつかっても心の土台がしっかりしており、ストレスによって大きく揺さぶられにくい特徴があります。 一方で、義務感やプレッシャーに突き動かされる強迫型パッションでは、これらの欲求が十分に満たされていないことが多く、ちょっとした不安やネガティブな出来事に敏感に反応してしまいやすいのです。 脳科学が示す調和型 vs 強迫型の違い 脳科学的な観点でみると、調和型パッションは、心理的な満足感(報酬)を高め、結果としてストレスの知覚やストレスホルモンの分泌を間接的に低減させている可能性があります。 一方、強迫型パッションは義務感や不安に駆動されているため、持続的なプレッシャーとなり、その結果、慢性的なストレス反応を引き起こしやすくなると考えられます。そこに職場での嫌がらせという追い打ちが加われば、心身の限界を超えて「逃げ出したい」という強烈な反応が起きても不思議ではありません。 今回の研究結果は、まさに「情熱の質の違い」がストレスに対する脳と心の反応を変化させることを示唆していると言えるでしょう。 まとめ:情熱は退職の歯止めになるのか? 今回紹介した研究によって、職場での人間関係ストレスと「仕事への情熱」という要素が、実は密接に絡み合っていることがわかりました。上司や同僚からの嫌がらせは、それ自体が社員に「辞めたい」と思わせる強い動機になります。しかし、そのマイナスの効果は社員一人ひとりが持つ情熱のタイプによって増減するのです。 調和型の情熱はまるで防護服のようにストレスの影響を軽減し、被害を受けてもなお仕事に踏みとどまる力を与えてくれます。一方で強迫型の情熱は、残念ながらストレスを増幅させ、退職への傾きを一段と急にしてしまいます。 「情熱」という言葉はポジティブに聞こえますが、今回の研究はその“質”こそが重要であると教えてくれます。情熱には光と影があり、本当に社員を救うのはバランスの取れた健全な情熱なのです。組織としても、ただ「情熱を持て!」と鼓舞するのではなく、社員が自発的にやりがいを感じられる環境を整え、調和型パッションを育めるようなマネジメントが望まれます。 たとえば、自由度の高い職務設計や、公正な評価、サポートし合う職場文化の醸成などは、社員の基本的欲求を満たし情熱を良い方向へ導くはずです。同時に、陰湿な職場いじめを防止する取り組みは言うまでもなく重要でしょう。 最後に、もし今この記事を読んでいるあなた自身が職場で辛い思いをしているなら、自分の心の中の「情熱の種類」を見つめ直してみてください。もしその仕事が本当に好きなら、その内なる想いがきっとストレスに負けないエネルギーを与えてくれるはずです。 一方で、「やらねば」という義務感に縛られているなら、少し肩の力を抜いて自分の心身をいたわることも大切かもしれません。情熱は人を強くも弱くもする——だからこそ自分にとって健全な情熱とは何かを考えてみる価値がありそうです。 仕事への向き合い方ひとつで、職場という荒波の中でもあなた自身が被害者ではなくサバイバーになる道が開けるかもしれません。 今回紹介した論文📖 Tosun, B., Güner Kibaroğlu, G., Basım, H. N., & Çetin, F. (2025). From victims to survivors: Does job passion mitigate the impact of social undermining on turnover intention? Journal of Economics and Management, 47(1), 90-116 https://www.researchgate.net/publication/389200342_From_victims_to_survivors_Does_job_passion_mitigate_the_impact_of_social_undermining_on_turnover_intention