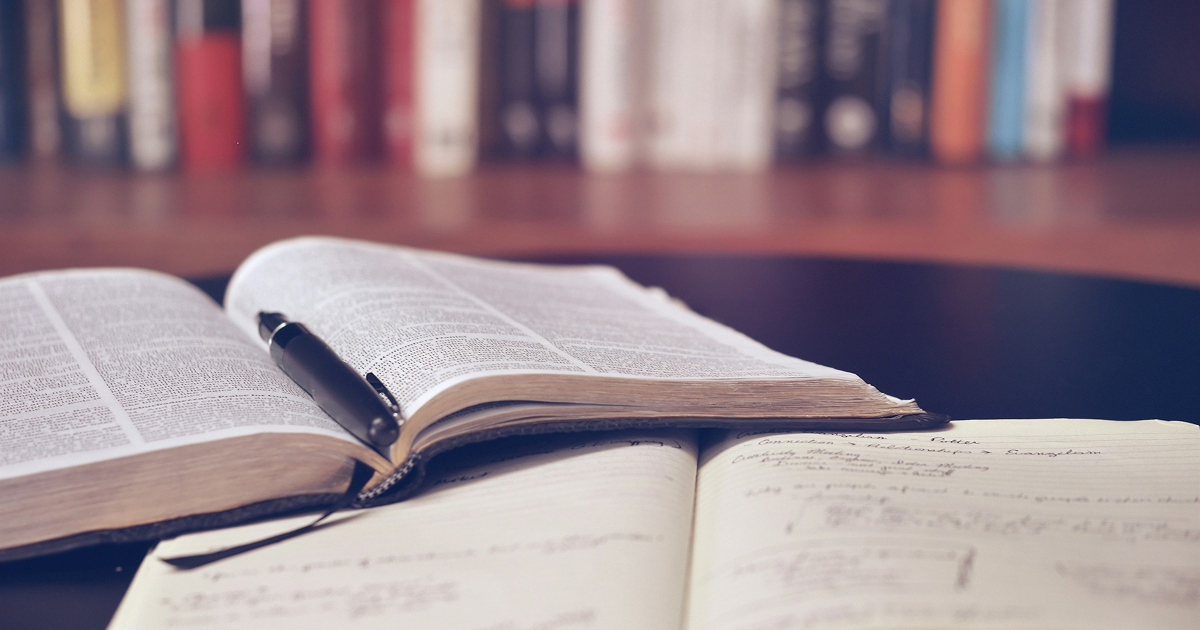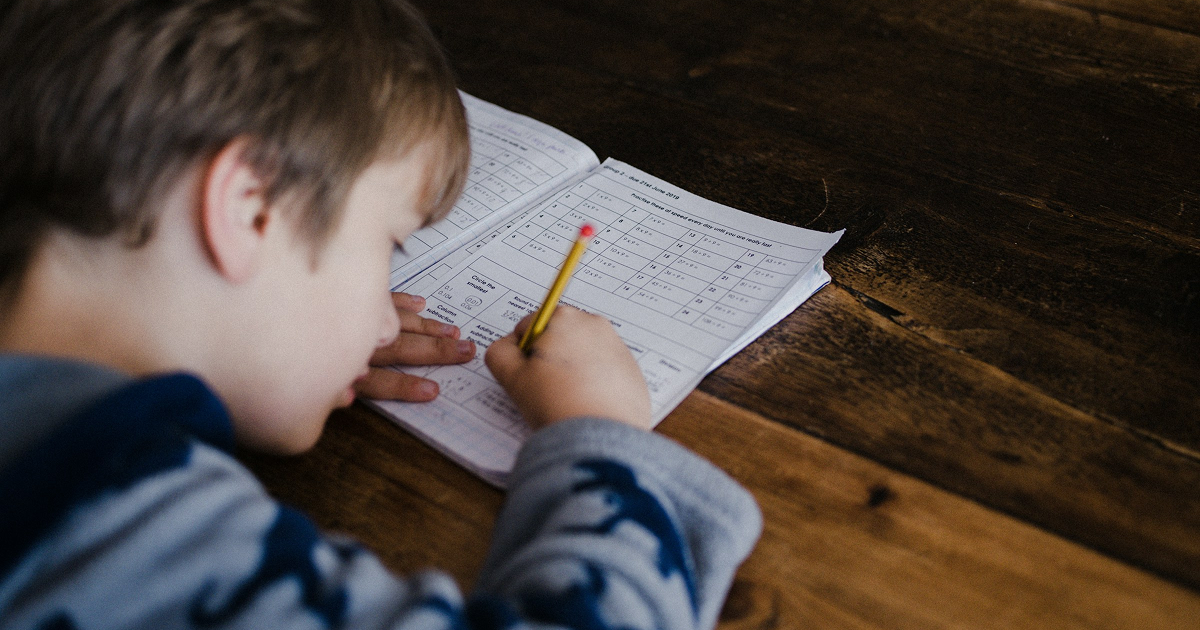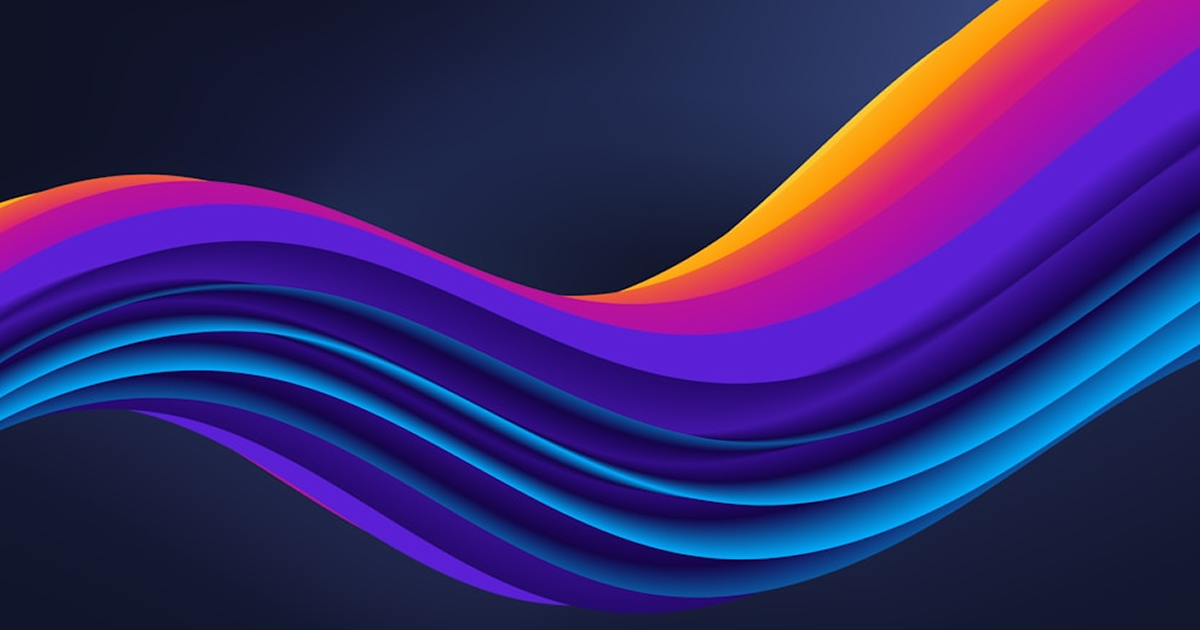朝型と夜型はどっちがいいの?平日の日本人は時差ボケ状態にある!?
「学習」というテーマで、パフォーマンスを向上させるためには睡眠が重要であると学びました。しかし、緊張する試験を控えていたり、楽しみなイベントがあると、なかなか眠れないという方もいるのではないでしょうか。 実は、睡眠に効果的な食べ物や飲み物があったり、ニューロフィードバックの介入を通して、睡眠の質を高めるなど、現在さまざまな技術が生み出されています。そこで、今回は「睡眠」について深掘りしていこうと思います。 前回のコラムはこちらです。 https://mag.viestyle.co.jp/columm21/ 電車で居眠りをする日本人を見た海外の人の驚きの反応は? 日本ではバスや電車の中で、居眠りをしている人をたくさん見かけますよね。しかし、ヨーロッパでは、そのような公共の場で眠っていると「体調が悪い」と見られてしまうそうです。実際、海外の友人に「移動の電車で多くの人が眠っているけれど、日本人はみんなナルコレプシーなのか?」と聞かれたことがあります。 ナルコレプシーとは、十分な睡眠をとっていても、日中に眠気が襲ってきて、自分でも制御できずに眠ってしまう症状のことです。きっと日本では、電車で眠っていても、物を盗られたり、襲われたりする危険が少ないから、安心して眠れてしまう、という文化の違いだと思います。 しかし、日本には睡眠不足の人が多いのではないかという考え方もあります。睡眠が不足していると、日中帯のパフォーマンスが低下してしまいます。アルコールを飲んでいる時と同じくらい、脳の機能が下がるとまでも言われているのです。 ある研究者が、睡眠不足がどれほどのコストになっているのかを計算したところ、日本ではGDPの2.9%ほどが、睡眠不足によって失われているのではないかという結果になりました。これは他の国と比べても、かなり大きな数値で、日本人は睡眠不足の人が多いということがわかります。これを改善することで、日本は経済的にも、便益を享受することができると言われています。 朝型と夜型の人の違いとは? 睡眠不足を表す指標の一つに、睡眠負債と言うものがあります。いつ眠くなっていつ起きるのかというのは個人差がありますよね。それをクロノタイプと言うのですが、そのため一概に夜遅くまで起きていることや朝遅くまで寝ていることが良くない、とは言い切ることができません。 朝、学校が始まる時間が早すぎると思ったことがある人もいるのではないでしょうか。日本の学校の始業時間は、クロノタイプが朝型の人に合わせて、作られているのだと思います。イギリスでは、人によってクロノタイプが違うのだから、10時始業のように時間を遅らせたら良いのでは?と考えられ、実際に成績も上がったという成果があります。 大昔の狩猟時代に、朝に活動して夜に眠る人たちを、動物に襲われないように守ってくれていた人がいると思います。そのような人たちが今の夜型になっているのかもしれませんね!代わりに朝型の人たちは朝に活動して、今の夜型の人たちを守っていたのかもしれません。 飛行機に乗らなくても時差ボケしてしまう人とは? このように睡眠には個人差があるため、みんながみんな同じような睡眠リズムを持っているわけではありません。平日は6時に起きるけれど、休日は10時まで寝てしまう、というように、平日と休日で、起きる時間が変わる人もいるのではないでしょうか? このような本来寝ていたい時間との差を、ソーシャルジェットラグと言います。ジェットラグというのは、飛行機に乗って時差ぼけをしてしまうことを指します。そして、ソーシャルのせいで、平日はずっと起きていて、休日だけたくさん寝てしまうことにより、睡眠のリズムが平日と休日で変わってしまい、ラグが生まれるのが、ソーシャルジェットラグです。 日本の睡眠研究で、平日働いた後に、好きなだけ休日に寝てくださいと言うと、平日よりも睡眠時間が数時間ほど長くなる人も多くいるそうです。普通に寝ると、人は8.4時間ほど眠るそうですが、平日は7時間ほどしか寝ない人が多いため、そこの差で睡眠不足が生じてしまいます。 まとめ 私たち日本人は、他の国の人と比べても、睡眠不足の人が多いです。このような睡眠負債を抱えていると、日中のパフォーマンスが下がってしまったり、経済的な負担にも繋がってしまいます。睡眠不足は平日と休日の睡眠時間の差にも現れていて、睡眠不足の解消は、社会的な課題であると言うことができます。 🎙ポッドキャスト番組情報 日常生活の素朴な悩みや疑問を脳科学の視点で解明していく番組です。横丁のようにあらゆるジャンルの疑問を取り上げ、脳科学と組み合わせてゆるっと深掘りしていき、お酒のツマミになるような話を聴くことができます。 番組名:ニューロ横丁〜酒のツマミになる脳の話〜 パーソナリティー:茨木 拓也(VIE 株式会社 最高脳科学責任者)/平野 清花 https://open.spotify.com/episode/4FsfTfp2A0oNGH4jEdlaUl?si=vj_70I7YQGmfyTO74vHXFQ 次回 次回もコラムでは、『睡眠の質を高める意外なヒント』をいくつかご紹介します。 https://mag.viestyle.co.jp/columm23/