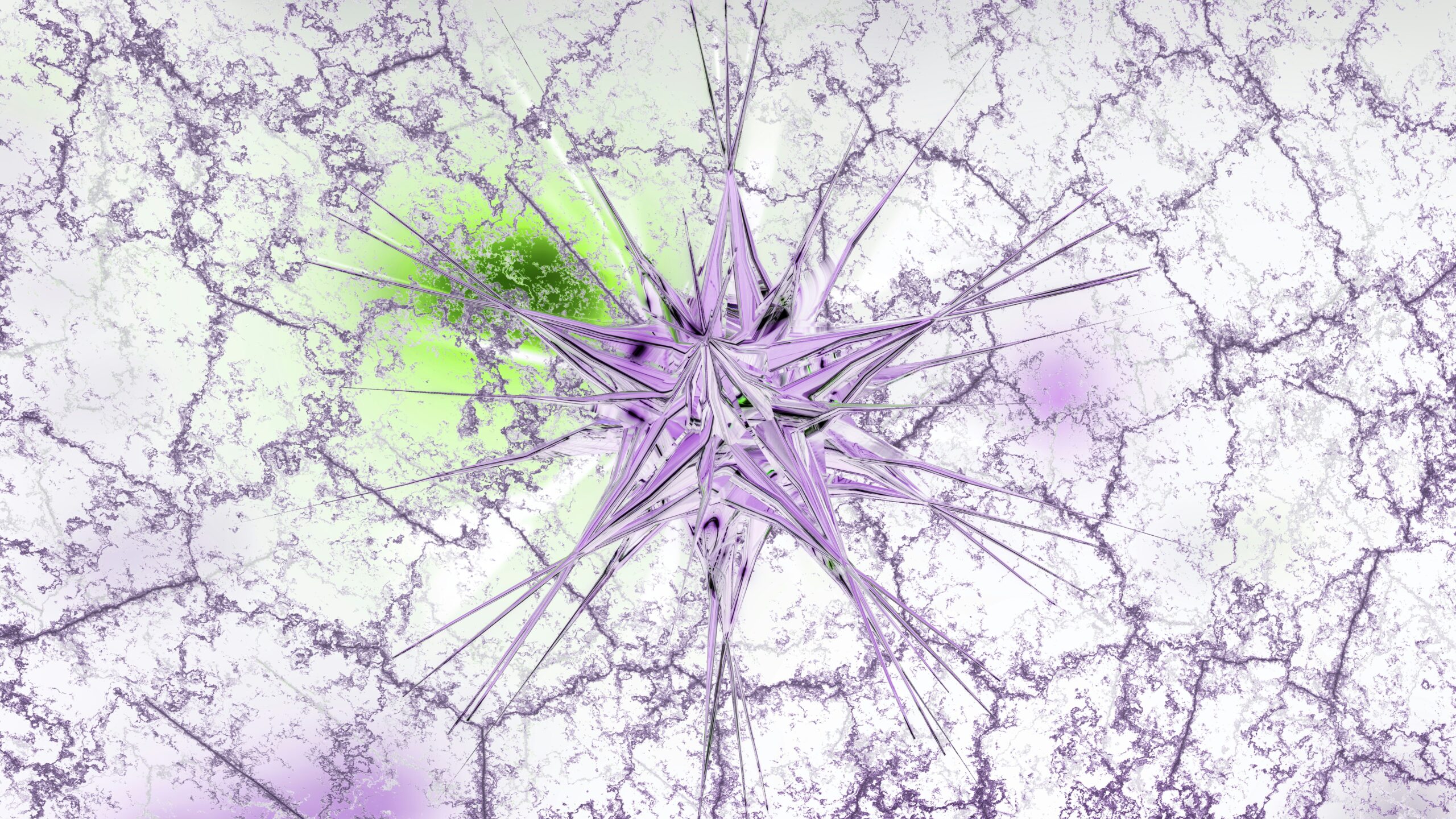「自分ってどんな人?」その答えは脳が知っている:脳波でわかるナルシシズム
「脳波で性格がわかる時代が来た」──そんな見出しを目にしたら、にわかには信じがたいかもしれません。しかし、最新の研究は、まさにその可能性を示唆しています。自己愛が強い、いわゆる「ナルシシスト」かどうかが、脳波(EEG)のパターンから読み取れるかもしれないのです。 本稿では、2025年に報告された「ナルシシズムの脳波デコード(Decoding the Narcissistic Brain)」という研究をひも解きながら、脳活動から性格がわかる未来について考えてみます。 性格研究の盲点?脳から見たナルシシズム ナルシシズム(自己愛傾向)は古くから心理学で注目されてきたトピックです。ビジネスや政治の世界でも「ナルシシスト」の成功や失敗が語られることがあります。ところが意外なことに、ナルシシズムという性格特性の研究は数多くあるにもかかわらず、その神経的な基盤を掘り下げた研究はごくわずかしか存在しません。 なぜこのギャップが生まれたのでしょうか。一つには、ナルシシズムが主に自己報告アンケートなどで測られる性格特性で、客観的な脳指標と結びつけるのが難しかったことが挙げられます。また、性格の神経基盤を探る「パーソナリティ神経科学」という分野自体、まだ新しい学際領域です。 こうした背景の中、「脳波でナルシシズムを読み解けるか?」という挑戦的な問いに踏み込んだのが今回紹介する研究です。 あなたの“ナルシシズム”、どのタイプ? 一口にナルシシズムと言っても、その表れ方にはいくつかのタイプがあります。本研究では特に以下の5種類のナルシシズムに着目しています: エージェンティック・ナルシシズム(Agentic narcissism)自己顕示的で権力志向なタイプ。自分の才能や成果を誇示し、他者より優れていると信じる「典型的なナルシシスト」です。 コミュナル・ナルシシズム(Communal narcissism)共益的(コミュニティ志向)なタイプ。表面的には謙虚で「人のため」を謳うものの、内心では「自分は誰よりも博愛的で徳が高い」と信じています。 賞賛追求型ナルシシズム(Admirative narcissism)周囲からの称賛や承認を何より求めるタイプ。魅力的に振る舞い、人から好かれ尊敬されることで自己価値を保ちます。 競争的ナルシシズム(Rivalrous narcissism)他者との比較や競争にとらわれるタイプ。他人を蹴落としてでも優位に立とうとし、批判的・攻撃的な態度で自己を守ろうとします。 脆弱型ナルシシズム(Vulnerable narcissism)繊細で傷つきやすいタイプ。表立って傲慢には振る舞いませんが、内心では特別な存在でありたい願望と、他者から評価されない不安との葛藤に苦しみます(いわゆる「隠れナルシシスト」)。 上述のうち前者4つは顕在的ナルシシズム(grandiose narcissism)とも総称され、自己評価が過剰に高い点では共通しています。しかし、その中でも「エージェンティック vs コミュナル」「称賛追求 vs 競争志向」といったサブタイプに分かれ、それぞれ性格的な特徴が異なります。 一方、脆弱型ナルシシズムは表面的な自信のなさや不安感を特徴とし、顕在型とは様相が異なります。このようにナルシシズムには多面的な顔があるため、研究チームは「その多面性が脳活動に現れるのではないか」と考えました。 脳波から見える、あなたのパーソナリティ では実際にどのように「脳波で性格を読む」のか、その方法を見てみましょう。研究では健康な若年成人162名を対象に、まず上述の5タイプそれぞれについて自己報告式の質問尺度を実施しました。次に被験者には安静状態で脳波(EEG)の計測を行います。 安静時の脳波は、何も課題をしていないリラックスした状態(目を開けた状態と閉じた状態の両方)で数分間記録されました。ポイントは、この脳波計測中、被験者は特に「自分をよく見せよう」とか「考え事をしよう」と努めているわけではないということです。いわば“何気ない脳のクセ”が記録されたと言えるでしょう。 集められた脳波データは周波数ごとの脳波パワースペクトルに変換されました。脳波にはΔ波(1~4Hz)、θ波(4~8Hz)、α波(8~12Hz)、β波(12~30Hz)、γ波(30~40Hz)といった周波数帯があります。各被験者について、各周波数帯で脳波の強さ(パワー)が計算され、それとナルシシズム傾向との関係が分析されたのです。脳波の種類についての詳細は以下の記事でも紹介しています。 https://mag.viestyle.co.jp/eeg-business/ 鍵となる分析には機械学習(マシンラーニング)の手法が使われました。研究者らは脳波のパターン(32か所の電極で計測された周波数ごとのパワー分布)から、先述のナルシシズム各尺度の得点を予測(デコード)できるかを試みたのです。 具体的にはサポートベクター回帰というアルゴリズムを用い、脳波データから各人格特性スコアを当ててもらいます。もちろん単に「勘で当てる」のではなく、まず多くの被験者データでモデルを訓練し、それがどの程度正確に他の被験者のスコアを当てられるか検証しました。 予測精度が高ければ「脳波にその人格特性の手がかりが含まれていた」と解釈できます。精度評価は偶然の当たりを上回るかどうか統計的にチェックされ、予測が偶然によるものではなく、実際に脳波と性格傾向の間に関連があると判断できる場合のみ、有意とされました。 タイプ別ナルシシズム、脳波が示す“違い” 結果はどうだったのでしょうか。研究チームの報告によると、脳波パターンから5つのナルシシズム傾向をそれぞれ有意に予測できました。 さらに興味深いのは、タイプごとにその脳波特徴が異なっていた点です。たとえば、エージェンティック型とコミュナル型では、それぞれ関連する脳波の周波数やパワーの分布パターンが全く重ならなかったといいます。自己中心的なナルシシストの脳波パターンと、「自分は博愛的だ」と信じるナルシシストの脳波パターンは明確に異なり、混同されなかったということです。これはナルシシズム研究におけるエージェンシー対コミュニオン(自己志向か他者志向か)の理論モデルとも合致します。 同様に、賞賛追求型と競争型でも脳波パターンはほぼ重ならず別物でした。他人から賞賛を集める戦略のナルシシストと、他者を出し抜く戦略のナルシシストでは、脳の休息時活動に違いが現れるというのです。これも理論上提唱されていた「賞賛と敵対」という二分モデルを支持する結果と言えます。 一方、脆弱型ナルシシズムは他のタイプと様相が異なりました。脆弱型が高い人ほど、脳波の低周波帯(デルタ・シータなどの遅い波)から高周波帯(ベータ・ガンマなどの速い波)まで幅広い帯域で脳波パワーが低い傾向が見られたのです。平たく言えば、脆弱なナルシシストの脳波は全体的に大人しめだということです。この特徴は、自己愛が強いのに表立って自己主張できず内省的で不安が強いという脆弱型の性質とも符合するかもしれません。 図:各ナルシシズムタイプと脳波パターンの関係(Zhou et al., 2025) 以上のように、ナルシシズムの多様な側面ごとに固有の脳波パターンが確認されたのです。研究チームは「これらの結果を総合すると、自己愛傾向の多様な形が安静時脳活動から信頼性高く予測できることが示唆された」と述べています。この成果は人格特性を脳から読み解くパーソナリティ神経科学という分野の新たな一歩と言えるでしょう。 VIEの脳波計で“自分の脳”を理解する VIEのEEG Headphoneのような革新的なデバイスにより、誰でも脳波を“日常的に”測ることが可能になってきています。特に研究用に特化したこのデバイスは、高度な脳波センサーを内蔵したオーディオデバイスとして、リアルタイムで集中・リラックス・認知負荷といった状態を非侵襲かつ高精度に可視化することが可能です。 特許取得済みのセンシング技術と、研究・開発向けのSDK/データ出力機能を備えており、神経科学・心理学・教育など多様な分野での応用が期待できます。 詳細はこちら:VIE EEG Headphone公式HP 脳が語る「あなた」の個性 私たちの脳は、言葉にしなくても多くのことを物語っています。今回の研究は、「人間の脳波は、口を開く前にその人の性格を映し出しているのかもしれない」という驚きとともに、新たな問いを投げかけました。もちろん、脳波で性格のすべてが分かるわけではありません。しかし「脳波で性格がわかる時代」が現実味を帯びてきたことは確かです。 将来、ビジネスや教育の場で脳波から個人の特性に合わせたアプローチを取る、といった応用も夢ではないかもしれません。また逆に、脳波でここまで性格が予測できてしまうことに対する倫理的な議論も必要になるでしょう。 私たちの脳活動と心の個性は表裏一体である──そのことを今回の研究は改めて示しています。何気なく過ごす今この瞬間も、あなたの脳波はあなたという人間の一端を物語っているのかもしれません。そんな事実に思いを馳せると、日常の風景が少し違って見えてきませんか。 🧾 参考文献 Zhou, Z., Huang, C., Robins, E. M., Angus, D. J., Sedikides, C., & Kelley, N. J. (2025). Decoding the Narcissistic Brain: Predicting diverse forms of narcissism from resting-state EEG using multivariate pattern analysis. NeuroImage, Volume 288, 120279. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925002873