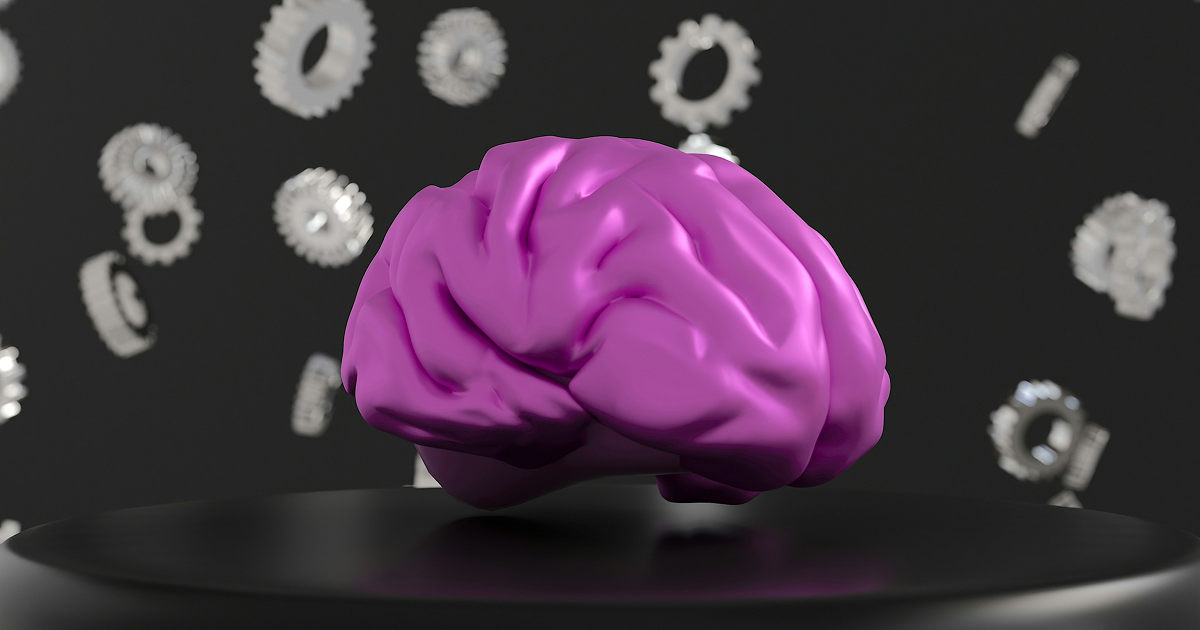ニューロリサーチとは?顧客の無意識を解明しマーケティング効果を最大化する新手法
「アンケートやインタビューでは、どうも顧客の“本音”が見えてこない…」多くのマーケティング担当者が一度は抱えるこの悩み。従来の調査手法で得られるデータだけでは、消費者の真のニーズや購買行動の背景にある深層心理まで捉えることは困難でした。
しかし今、その壁を打ち破る可能性を秘めた「ニューロリサーチ」が、マーケティングの新常識として注目を集めています。脳波や視線、心拍数といった生体データを科学的に分析し、消費者の潜在意識や無意識の感情を解き明かすこの手法は、広告効果の最大化、商品開発の精度向上、UXデザインの最適化など、幅広い分野で目覚ましい成果を上げています。
本記事では、ニューロリサーチの基本から、従来の調査手法との決定的な違い、具体的な活用事例、そしてマーケティングの未来をどう変えるのかまでを解説します。
ニューロリサーチとは?消費者の「本音」に迫る科学的アプローチ
まず、「ニューロリサーチ」という言葉が具体的に何を指すのか、どのような仕組みで消費者の深層心理にアクセスするのか、その基本的な定義と主要な測定手法について解説します。
ニューロリサーチの定義:脳科学で探る無意識の反応
ニューロリサーチとは、脳科学や神経科学、生理心理学の知見と計測技術を応用し、消費者が製品や広告、ブランドなどに触れた際の無意識的な感情や生理的反応を測定・分析するマーケティングリサーチ手法です。
従来のアンケート調査やインタビューのように、消費者が「意識して言語化する」情報に頼るのではなく、言葉にはならない、あるいは本人すら自覚していない「本音」の反応を捉えることを目的としています。これにより、より客観的で深層的な消費者インサイトの獲得が期待できます。
主な測定手法:脳波(EEG)・アイトラッキング・心拍数など
ニューロリサーチでは、様々な生体計測技術が用いられます。代表的なものとしては、以下のような手法があります。
- 脳波(EEG:Electroencephalography): 頭皮に電極を装着し、脳の電気活動を測定します。これにより、興味、関心、快・不快、ストレス、集中度といった感情や認知状態の変化をリアルタイムで捉えることができます。
- アイトラッキング(視線計測): 特殊なカメラで眼球の動きを追跡し、消費者が何に注目し、どのくらいの時間見ていたか、どのような順序で見たかなどを記録します。広告やパッケージデザイン、ウェブサイトのどの部分が注目を集めやすいかなどを客観的に評価できます。
- 心拍数(HR:Heart Rate)/心拍変動(HRV:Heart Rate Variability): 心拍数やその変動を測定することで、興奮、リラックス、ストレスといった情動反応や覚醒レベルを評価します。
- 皮膚電気活動(EDA:Electrodermal Activity)/ 発汗反応(GSR:Galvanic Skin Response): 精神的な興奮や感情の起伏に伴う発汗量の微細な変化を測定し、感情の強さや覚醒度を捉えます。
- 表情分析(Facial Coding): 顔の筋肉の微細な動きをカメラで捉え、AIで解析することで、喜び、怒り、悲しみ、驚きといった基本的な感情を客観的に判定します。 これらの手法を単独または組み合わせて用いることで、消費者の多角的な反応を明らかにします。
なぜ今ニューロリサーチ?従来のマーケティングリサーチが抱える限界

長年にわたりマーケティングの意思決定を支えてきた従来の調査手法ですが、その有効性には限界も見え始めています。ここでは、アンケート調査や定性調査といった従来手法が直面する課題を明らかにし、ニューロリサーチが求められる背景を探ります。
アンケート・インタビューでは見えない「建前」と「本音」の壁
アンケート調査やグループインタビューなどの定性調査は、消費者の意見や考えを直接収集できるという大きなメリットがあります。しかし、これらの手法で得られる回答は、あくまで消費者が「意識的に表現したもの」です。
人は無意識のうちに社会的に望ましいとされる回答を選んだり(社会的望ましさバイアス)、質問の意図を深読みしたり、あるいは自身の感情や動機を正確に言語化できなかったりすることがあります。その結果、表面的な「建前」の意見は集まっても、行動を真にドライブする「本音」のインサイトが見えにくいという課題があります。
「言っていること」と「やっていること」のギャップ:実際の購買行動との乖離
「この商品を購入したいですか?」というアンケートの質問に「はい」と答えた人が、実際にその商品を購入するとは限りません。逆に、「特に興味はない」と答えた商品がヒットすることもあります。
このように、意識調査で得られた回答と、実際の購買行動との間にはしばしばギャップが生じます。これは、人間の意思決定の多くが、合理的な判断だけでなく、無意識の感情や直感、その場の雰囲気といった要因に大きく影響されるためです。
従来の手法では、こうした瞬間的な感情や無意識の動機を捉えることが難しいため、購買行動の予測精度に限界がありました。
調査結果の主観性と再現性の課題
従来の調査手法、特に定性調査の結果は、調査員のスキルや解釈、あるいは調査対象者のその時々の気分や体調によって左右される可能性があり、結果の客観性や再現性を担保することが難しい場合があります。
また、アンケートの設問設計によっても回答が誘導されることがあり、データの信頼性に影響を与えることも少なくありません。
ニューロリサーチ3つの強み:潜在意識を捉え、成果に繋げる

従来のマーケティングリサーチが抱える課題に対し、ニューロリサーチは消費者の深層心理に迫ることで、より精度の高いインサイトを提供します。ここでは、ニューロリサーチならではの3つの大きな強みを解説します。
強み1:言語化できない「無意識の感情・反応」をデータ化
ニューロリサーチ最大の強みは、消費者が言葉にできない、あるいは自覚すらしていない無意識レベルでの感情や生理的反応を、客観的な生体データとして捉えられる点です。脳波や視線、心拍数などの変化を数値化・可視化することで、「なんとなく好き」「理由は分からないけど気になる」といった曖昧な感覚の正体を科学的に解明し、マーケティング施策の精度向上に繋げることができます。
強み2:購買意欲やブランドへの共感をより正確に測定
例えば、「ブランドに対する好意度」を測定する場合、アンケートでは「好きですか?」という直接的な質問になりますが、ニューロリサーチではブランドロゴや関連情報に触れた際の脳活動や生理反応から、そのブランドに対する無意識的な魅力度や感情的な結びつきの強さを評価できます。
これにより、広告が実際に消費者の心に響いているのか、商品デザインが本当に購買意欲を刺激しているのかを、より本質的なレベルで把握することが可能です。
強み3:客観的データに基づく高い結果の再現性と信頼性
ニューロリサーチは、人間の生体反応という客観的な指標に基づいて分析を行うため、回答者の主観やその場の状況、調査員のスキルといった外的要因に左右されにくいという特徴があります。これにより、調査結果の再現性が高まり、データの信頼性が向上します。科学的根拠に基づいたデータは、マーケティング戦略の意思決定において、より確かな判断材料を提供します。
【徹底比較】ニューロリサーチ vs 従来のマーケティングリサーチ

ニューロリサーチと従来のマーケティングリサーチは、それぞれ異なるアプローチで消費者理解を試みます。両者の特徴を比較することで、ニューロリサーチの独自性と優位性、そして適切な使い分けについて理解を深めましょう。
データ取得のスピードと精度:リアルタイムな生体反応 vs 回答者の記憶
ニューロリサーチは、消費者が広告や製品に接触した瞬間の生体反応をリアルタイムで計測・記録するため、鮮度の高い一次情報を捉えることができます。
一方、アンケートやインタビューは、消費者の記憶に基づいて後から回答を得るため、時間の経過による記憶の薄れや変容、思い出しバイアスの影響を受ける可能性があります。
また、ニューロリサーチが生理反応を直接測定するのに対し、従来手法は言語化された意識的な反応が中心となるため、無意識レベルの情報の精度には差が出ます。
コストとリソース:専門性と初期投資 vs 手軽さと広範囲カバー
一般的にニューロリサーチは、脳波計やアイトラッカーといった専用の測定機器、実験環境の整備、そしてデータ解析を行う専門知識を持つ人材が必要となるため、1回の調査にかかるコストや時間は従来の調査手法よりも高くなる傾向があります。
一方、オンラインアンケートなどは比較的低コストで、広範囲の対象者から短期間に大量のデータを収集できるというメリットがあります。ただし、ニューロリサーチから得られるインサイトの深さと質を考慮すれば、投資対効果(ROI)は高くなる可能性があります。
分析対象の深さ:深層心理の解明 vs 顕在的な意見・行動
ニューロリサーチの最大の価値は、消費者が自覚していない潜在意識や無意識の感情、直感的な反応といった深層心理にアクセスできる点です。例えば、広告の特定のシーンでなぜポジティブな感情が喚起されたのか、あるいはなぜ特定の商品棚の前で無意識に足が止まったのか、といった「Why(なぜ)」の部分を生理学的データから明らかにします。
これに対し、従来の手法は、主に消費者が認識している顕在的な意見や行動、態度の把握に留まることが多く、深層心理へのアプローチは限定的です。
データの客観性:生体データ vs 自己申告データ
ニューロリサーチで扱う脳波や視線、心拍数などの生体データは、個人の意思や主観が介在しにくいため、非常に客観性が高いと言えます。これにより、社会的望ましさバイアスや建前といったノイズに影響されず、消費者の純粋な反応を捉えることができます。
一方、アンケートやインタビューで得られる自己申告データは、回答者の記憶の正確性や感情表現の仕方、質問の受け止め方など、多くの主観的要素に左右される可能性があります。
ニューロリサーチの導入事例
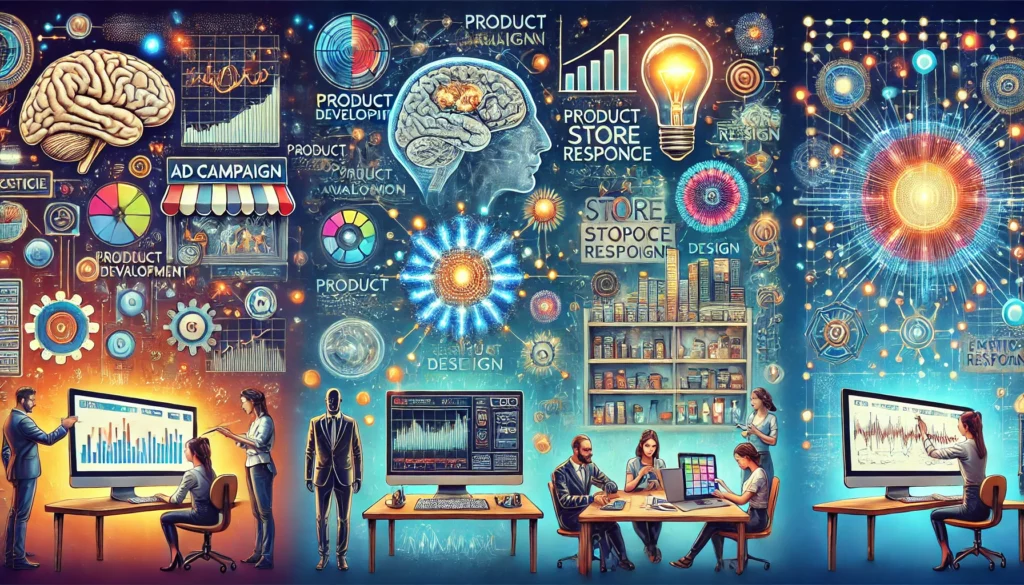
ニューロリサーチは、広告制作や商品開発、店舗設計、UXデザインなど、さまざまな分野で導入されています。その活用により、消費者の無意識的な反応や潜在的なニーズを把握し、マーケティング施策の成功率を飛躍的に高めた事例が数多く報告されています。
ダイドードリンコ:テレビCM最適化事例
ダイドードリンコ株式会社は、テレビCMの効果を高めるため、ニューロマーケティングを活用した評価を実施しました。この評価では、被験者がCMを視聴する際の脳波データや瞳孔の動きを測定し、視聴者の感情的な反応や集中度を分析しました。その結果、CMの冒頭部分で視聴者の興味を引く要素が不足していることが判明し、冒頭の5秒間をより印象的なシーンに変更しました。また、消費者の感情が高まるシーンを強調し、エンディングに配置することで、広告の視聴完了率が25%向上し、商品認知度も大幅に上昇しました。
参照:https://marketing.itmedia.co.jp/mm/articles/1706/26/news015.html
アサヒビール:『アサヒもぎたて』の成功事例
アサヒビール株式会社は、缶チューハイ『アサヒもぎたて』のパッケージデザインリニューアルに際し、ニューロリサーチとアイトラッキングを組み合わせた新手法を採用しました。この調査では、被験者に複数のパッケージ案を提示し、視線の動きと脳波を測定することで、消費者が最も魅力的と感じるデザイン要素を分析しました。
結果として、「収穫後24時間以内搾汁」のメッセージを上部に配置し、視線を引きつけるデザインが最も高い評価を得ました。このデザインを採用した新パッケージは、店頭での視認性が向上し、トライアル層の購買意欲を高めることに成功しました。
参照:https://www.macromill.com/service/case/001/
Neurensics社:ニューロリサーチを活用した広告効果の評価
オランダのニューロマーケティング企業であるNeurensics社は、食品会社Bolletje社の2種類のテレビCMを対象に、ニューロリサーチを活用した広告効果の評価を実施しました。この調査では、被験者にCMを視聴させ、fMRIを用いて脳活動を測定し、13種類の感情を分析しました。
その結果、売上が高かったCMは、ポジティブな感情を引き起こす要素が多く含まれていることが判明しました。一方、売上が低かったCMは、視聴者の注意が分散し、ネガティブな感情を引き起こす要素が含まれていました。この分析により、広告の感情プロファイルと売上効果の関連性が明らかになり、効果的な広告制作の指針が得られました。
参照:https://www.taiken-institute.jp/topics/column/6
ニューロリサーチはマーケティングの未来をどう変えるか

ニューロリサーチは、これまでブラックボックスとされてきた消費者の「無意識」の領域に科学の光を当て、その心の動きをデータとして捉えることを可能にする革新的なマーケティングリサーチ手法です。本記事で見てきたように、データの精度、リアルタイム性、そして分析の深さにおいて、従来の手法にはない大きな可能性を秘めています。
広告クリエイティブの最適化、ヒット商品を生み出すパッケージデザイン、顧客満足度を高める店舗・ウェブサイト体験の設計など、ニューロリサーチの応用範囲はますます広がっています。そして、その効果は数々の導入事例によって実証されつつあり、マーケティング施策の精度と成功率を飛躍的に高める力を持っています。 確かに、現状では導入コストや専門知識の必要性といったハードルも存在しますが、技術の進歩とともにこれらの課題も徐々に解消され、より多くの企業にとって身近なツールとなっていくでしょう。
消費者の「本音」をより深く、より正確に理解したい――。この普遍的なマーケターの願いに応えるニューロリサーチは、単なる一時的なトレンドではなく、今後のマーケティング活動において不可欠な羅針盤となるはずです。その可能性を最大限に引き出すことで、企業はかつてないレベルで顧客と繋がり、真に価値あるコミュニケーションを展開し、持続的な競争優位性を築くことができるでしょう。ニューロリサーチは、まさにマーケティングの未来を切り拓く鍵なのです。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る