心理的安全性が低いと危険?5つのデメリットと改善策
職場における心理的安全性は、従業員が安心して意見を述べ、挑戦できる環境を作るうえで欠かせない要素です。しかし、心理的安全性が低いと、発言しづらい雰囲気やミスの隠蔽、さらには離職率の上昇など、組織全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、心理的安全性が低いことによる5つのデメリットを詳しく解説するとともに、それを改善するための具体的な方法を紹介します。心理的安全性のバランスを適切に保ち、成長を促す職場環境を作るためのヒントをお届けします。
心理的安全性とは?
心理的安全性とは、チームや組織の中で、個人が自由に意見を表明し、質問や提案をしても批判や報復を恐れずにいられる状態を指します。この概念は、ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授によって提唱され、Googleの「プロジェクト・アリストテレス」によっても、成功するチームの重要な要素の一つとして確認されました。
心理的安全性の基本概念と重要性
心理的安全性は、単に「居心地が良い職場」を意味するものではなく、チームのパフォーマンス向上に不可欠な要素です。従業員が自信を持って意見を述べられる環境では、問題の早期発見や創造的なアイデアの共有が促進されます。これにより、組織のイノベーションが生まれやすくなり、チームワークの向上にもつながります。
一方で、心理的安全性がない環境では、従業員が意見を控えるようになり、結果として情報共有の不足や業務の停滞が発生する可能性があります。職場の信頼関係を築くためには、心理的安全性を確保することが重要です。
心理的安全性が低い職場の特徴
心理的安全性が低い職場では、以下のような特徴が見られます。
- 発言しづらい雰囲気がある
会議や日常業務の中で、自由に意見を述べることが難しい雰囲気がある職場では、従業員が消極的になり、意見を言うことに躊躇するようになります。その結果、重要な課題が見過ごされることもあります。 - 失敗を過度に恐れる文化がある
失敗が許されない文化では、新しい挑戦が敬遠され、イノベーションが生まれにくくなります。従業員がリスクを取ることを避けるようになり、結果的に組織の成長が停滞する可能性があります。 - 批判や責任追及が多い
ミスや問題が発生した際に、建設的なフィードバックではなく、個人への批判や責任追及が優先される職場では、従業員が防衛的になり、主体的に行動することが難しくなります。これにより、チームの信頼関係が損なわれ、パフォーマンスが低下します。
心理的安全性の低い環境では、従業員のエンゲージメントや生産性が低下するだけでなく、組織全体の活力も失われる可能性があります。次に、心理的安全性が持つデメリットについて詳しく見ていきます。
心理的安全性が低いことによる5つのデメリット

心理的安全性が低い環境では、従業員の働きやすさだけでなく、組織全体のパフォーマンスや成長にも深刻な影響を及ぼします。ここでは、心理的安全性が低いことによる5つのデメリットについて詳しく解説します。
発言がしにくくなり、チームの成長が阻害される
心理的安全性が低い職場では、従業員が自由に発言できないため、新しいアイデアや提案が生まれにくくなります。特に、イノベーションが求められる場面では、発言しづらい環境が大きな障害となります。
- アイデアを自由に出せないため、チームのイノベーションが停滞
チームメンバーが「批判されるかもしれない」と感じると、新しいアイデアを提案することをためらうようになります。これにより、創造的な発想が生まれにくくなり、競争力の低下を招きます。 - 部下が上司に意見を言いにくく、意思決定が一方的になる
部下が上司に対して率直な意見を伝えられない職場では、上層部の意思決定が一方的になりがちです。その結果、現場の課題が適切に共有されず、組織の方向性が誤ったものになる可能性があります。
ミスや問題が隠され、重大なトラブルにつながる
心理的安全性が低いと、従業員はミスを報告しにくくなり、結果として問題が隠蔽されるリスクが高まります。これは組織の信頼性や持続性に深刻な影響を及ぼします。
- ミスを報告しにくく、問題が隠蔽されやすくなる
失敗を責める文化があると、従業員はミスを隠す傾向にあります。問題が早期に発見・対処されず、結果として重大なトラブルに発展することもあります。 - 企業の不祥事や組織の崩壊を招くケースも
多くの企業不祥事の背景には、従業員が問題を報告しにくい文化があることが指摘されています。内部告発が遅れ、取り返しのつかない事態になるケースも少なくありません。
離職率が上がり、優秀な人材が流出する
心理的安全性が低い職場では、働きづらさを感じる従業員が増え、結果として離職率の上昇につながります。
- 上司や同僚との関係が悪化し、働きづらい環境になる
職場での信頼関係が築けないと、従業員は仕事に対して消極的になり、モチベーションが低下します。結果として、職場の雰囲気が悪化し、長く働き続けることが困難になります。
- 人材が定着せず、組織のパフォーマンスが低下
離職が増えることで、新しい人材の採用・育成の負担が増加し、組織全体の生産性が低下します。特に、経験豊富な人材が流出することで、業務の継続性に支障をきたす場合もあります。
ストレスが増加し、メンタルヘルスの悪化を招く
心理的安全性が低い環境では、従業員が常にプレッシャーを感じ、心身の健康に悪影響を及ぼします。
- 高圧的な環境がストレスの原因となり、心身の健康を損なう
常に上司や同僚の目を気にしながら働く環境では、従業員のストレスが増加します。これにより、集中力の低下や体調不良を引き起こすこともあります。 - 社員のモチベーション低下やバーンアウトのリスク
精神的な負担が蓄積すると、社員は仕事に対する意欲を失い、最悪の場合は燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ることもあります。これが組織全体の生産性に悪影響を与えることは言うまでもありません。
チームワークが機能せず、業務効率が低下する
心理的安全性が低いと、チーム内の連携が取れなくなり、業務効率の低下を招きます。
- 互いに信頼できないため、情報共有が不足し、連携が取りづらくなる
信頼関係が築けていないチームでは、メンバー間の情報共有がスムーズに行われません。その結果、業務が属人的になり、チーム全体の効率が悪化します。 - 部署間の協力が難しくなり、組織全体の生産性が落ちる
チーム内の心理的安全性が低いと、他の部署との協力関係も希薄になります。結果として、組織全体の連携が取れず、生産性が大きく低下することになります。
このように、心理的安全性が低いは、職場環境だけでなく、組織の持続的な成長にも悪影響を与えます。
心理的安全性が高いことによるリスクとは?
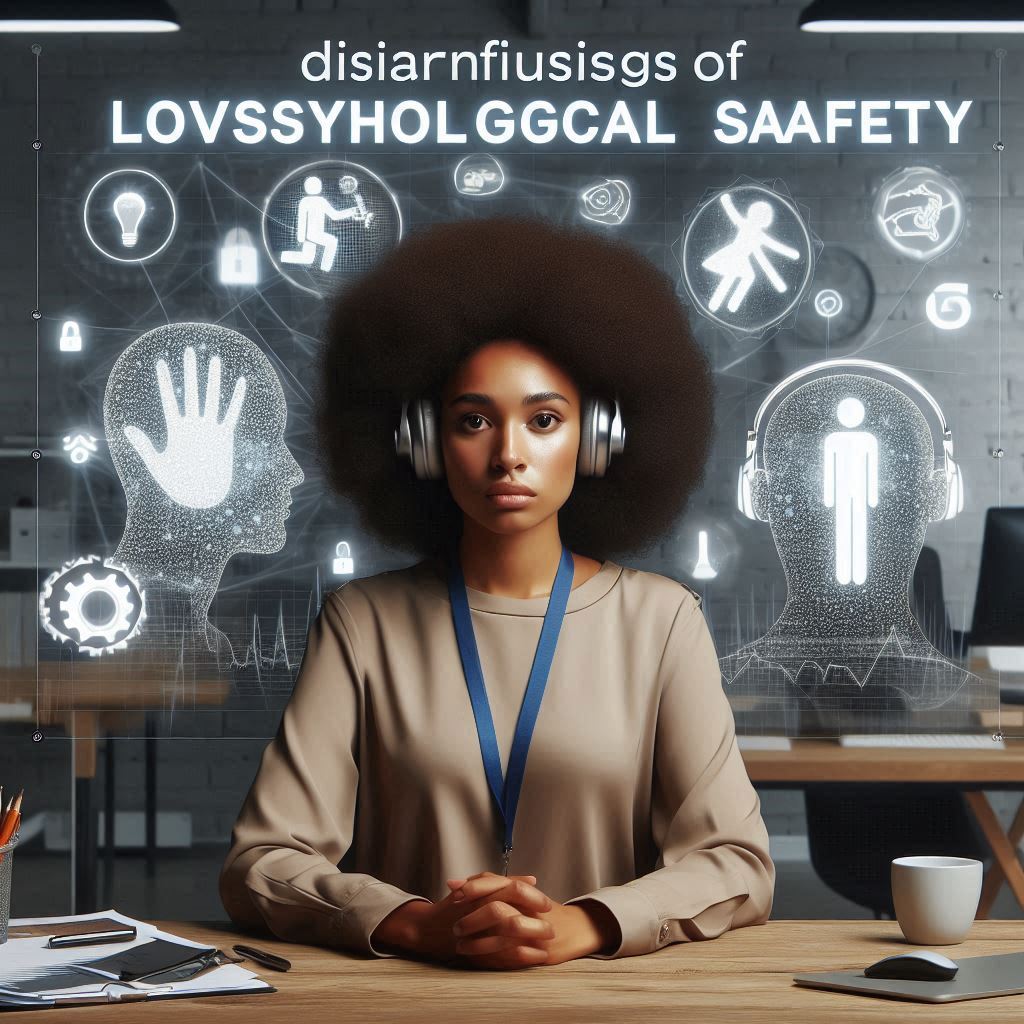
心理的安全性が確保された職場では、従業員が自由に発言でき、安心して働ける環境が整います。しかし、心理的安全性が過剰になると、逆に組織の成長を阻害するリスクもあります。「意見が言いやすい環境」と「ぬるま湯の組織」は別物であり、適度な緊張感を持たせることが重要です。
心理的安全性が高すぎると成長を阻害する可能性
心理的安全性が高いこと自体は良いことですが、バランスを欠くと「挑戦しなくても許される環境」になってしまうリスクがあります。
- 挑戦しなくても許される環境になる
心理的安全性が過剰になると、従業員が新しいことに挑戦する必要性を感じなくなる可能性があります。リスクを取らなくても仕事が進む状況では、チーム全体の停滞につながることもあります。 - フィードバックが甘くなり、成長の機会を失う
心理的安全性が強調されすぎると、フィードバックが過度に優しくなり、建設的な意見が交わされなくなる場合があります。たとえば、「批判を避けるために遠慮したフィードバックしかできない」という状態では、個々の成長が妨げられ、結果として組織全体のパフォーマンスも低下します。
「心理的安全な職場」と「ぬるま湯組織」の違い
心理的安全性が高い職場と、単なるぬるま湯組織には明確な違いがあります。心理的安全性を確保しつつ、適度な緊張感を維持することが求められます。
- 心理的安全な職場:意見を言いやすく、適度な緊張感がある
健全な心理的安全性が確保されている職場では、意見を自由に述べることができる一方で、適切なフィードバックが行われ、成長の機会が与えられます。ミスが許される環境でありながら、それを改善するための議論が活発に行われるため、組織としての成長が促進されます。
- ぬるま湯組織:批判が全くなく、責任を取らない風潮が生まれる
一方で、過度な心理的安全性がある組織では、フィードバックや建設的な議論が避けられ、従業員が責任を取らない風潮が生まれやすくなります。例えば、「誰もが意見を尊重し合うが、決定的な判断がなされない」「問題が指摘されず、業務の質が低下する」といった事態が発生する可能性があります。
適度な心理的安全性を保ちつつ、成長のためのチャレンジ精神を促すことが、健全な組織運営には欠かせません。
心理的安全性を高めるための改善策
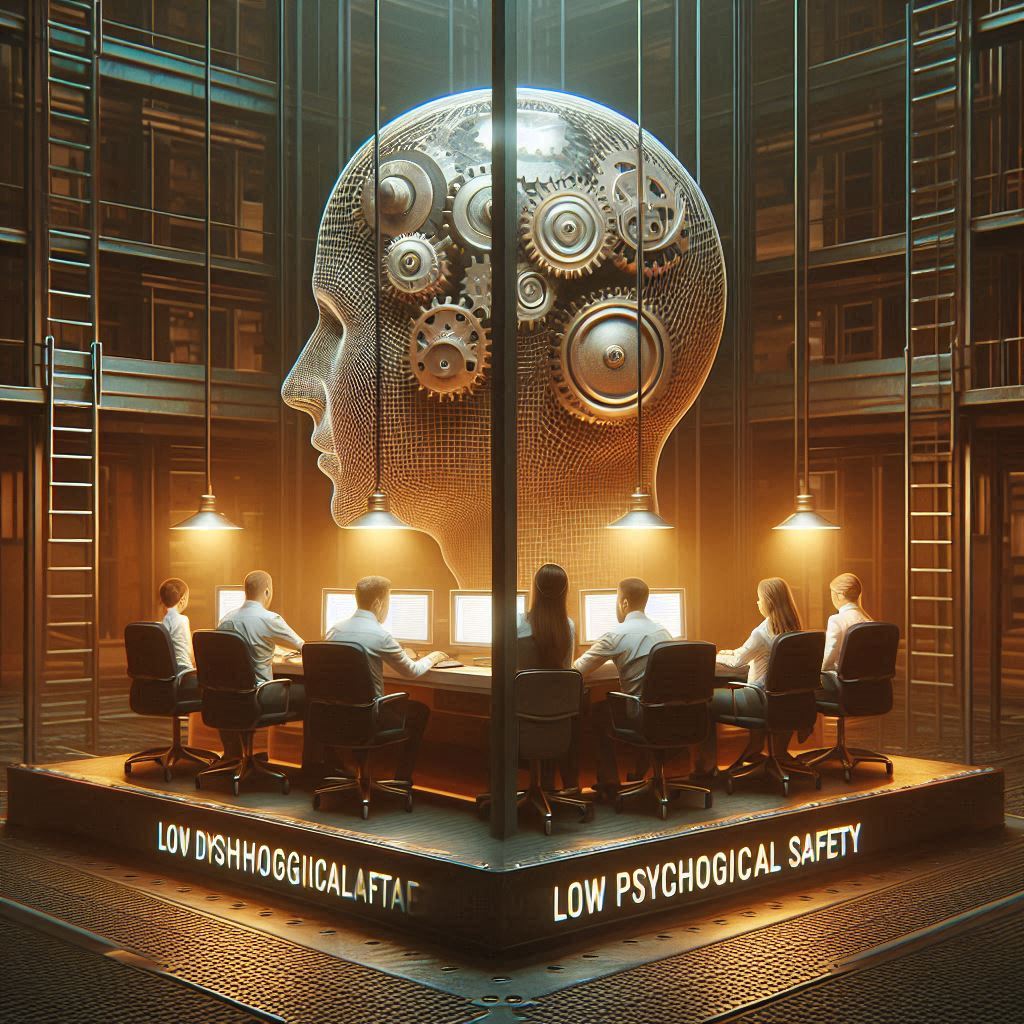
心理的安全性が適切に保たれている職場では、従業員が安心して意見を交わし、主体的に行動できる土壌が育ちます。ただし、前章でも述べたように、心理的安全性が過剰になると、組織に必要な緊張感や成長の機会を損なうリスクもあります。重要なのは、「意見が言いやすい」だけでなく、「目的に向けて健全な刺激がある」状態を維持することです。
この章では、そうしたバランスの取れた心理的安全性を実現するために、組織が取り組むべき具体的な改善策や評価のポイント、業務の厳しさとの両立方法について解説していきます。
心理的安全な職場を作るための具体的なステップ
心理的安全性を高めるためには、リーダーやマネージャーの積極的な関与が不可欠です。以下のようなステップを取り入れることで、より良い職場環境を構築できます。
- 上司が率先して安心して発言できる環境を作る
心理的安全な職場を作るには、まずリーダー自身が率先してオープンなコミュニケーションを取ることが重要です。部下の意見に耳を傾け、批判ではなく建設的なフィードバックを行うことで、発言しやすい雰囲気を醸成できます。 - 建設的なフィードバック文化を根付かせる
フィードバックが否定的なものばかりでは、心理的安全性を損なう要因になります。ポジティブな側面を強調しながら、改善点を具体的に伝える文化を定着させることが大切です。例えば、「○○の部分は非常に良かったので、△△を工夫するとさらに効果的になる」といった伝え方を意識すると、相手も受け入れやすくなります。
心理的安全性を測るためのチェックポイント
心理的安全性の向上を目指すには、現状を正確に把握することが欠かせません。以下のチェックリストを活用し、組織やチームの心理的安全性を評価してみましょう。
心理的安全性を測るチェックリスト
- ☐ チームメンバーは自由に意見を述べられる雰囲気があるか
- ☐ フィードバックが建設的に行われ、批判的な言動が少ないか
- ☐ ミスを報告しやすい環境が整っているか
- ☐ 上司やリーダーが部下の意見を積極的に聞いているか
- ☐ 会議やディスカッションで一部の人だけが発言していないか
- ☐ 従業員同士の信頼関係が築かれているか
評価方法
- 定期的な従業員アンケートの実施
心理的安全性に関する質問を含む匿名アンケートを実施し、チームの現状を可視化します。 - 1on1ミーティングの活用
個別に従業員の意見を聞くことで、表面化しにくい課題を発見できます。 - フィードバックセッションの導入
定期的に振り返りの時間を設け、心理的安全性の向上に向けた取り組みを話し合います。
チェックリストを活用し、定期的に心理的安全性を測定することで、より健全な職場環境を築くことができます。
心理的安全性と業務の厳しさのバランスを取る方法
心理的安全性は重要ですが、それだけに偏ると、甘えや緩みを生むリスクがあります。大切なのは、安心して意見を言える環境と、責任ある行動や成果への意識を両立させることです。
発言の自由を保障するだけでなく、「根拠のある発言を促す」「目標への主体的な取り組みを評価する」といった姿勢を組織に根付かせることで、適度な緊張感を保ちながら、チーム全体の成長を後押しできます。心理的安全性と業務の厳しさは相反するものではなく、相乗効果を生む関係として捉えることが重要です。
心理的安全性の低さが職場に与える影響を正しく理解しよう

心理的安全性の低い職場環境では、発言しづらい雰囲気や過度な責任追及が従業員のストレスを増大させ、結果として生産性やチームワークの低下につながります。一方で、心理的安全性が過剰になりすぎると、ぬるま湯の組織になり、挑戦や成長の機会を奪ってしまうこともあります。
大切なのは、心理的安全性と適度な緊張感をバランスよく保つことです。オープンなコミュニケーションを促進し、フィードバック文化を根付かせることで、従業員が安心して発言しながらも、成長できる環境を作ることができます。
組織の持続的な成長を実現するために、心理的安全性の重要性を理解し、適切な施策を講じることが求められます。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る


