ガンマ波の可能性:医療・教育・エンタメを進化させる脳科学の挑戦
私たちは日々、集中力や記憶力の低下、ストレス管理など、脳の働きに関する悩みを抱えています。そんな中、近年注目されているのがガンマ波です。特に40Hz音を活用したガンマ波サウンドは、認知機能の向上や認知症予防、リラックス効果など、脳の健康に役立つ可能性が示されています。
本記事では、ガンマ波がもたらす効果や、その技術を活用したVIE株式会社の取り組みを紹介します。日常生活や未来の社会に、ガンマ波技術がどのように関わっていくのか、一緒に見ていきましょう。
ガンマ波とは?注目されるその理由
ガンマ波とは、脳内で観測される脳波の一種で、高周波数(30Hzから100Hz)の活動を指します。ガンマ波は、記憶、注意力、学習など、脳が何かに集中して働いているときによく現れ、簡単に言うと、「脳がフルスピードで頑張っているとき」に見られる信号のようなものです。
脳波にはガンマ波以外にもさまざまな種類があり、それぞれに異なる特徴や役割があります。他の脳波について詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
ガンマ波と認知機能の関係
ガンマ波は、脳のさまざまな部分が協力して働くときに重要な役割を果たしています。たとえば、物を見て「これは、りんごだ」と気づくとき、目で見た情報と過去の記憶が結びついて「りんご」と認識します。このとき、ガンマ波がその情報をつなげる役割をしているのです。
このように以前の記憶を思い出すときや、新しいことを覚える時、ガンマ波の活動が活発になります。特に、集中して勉強したり、新しいスキルを習得したりしているときに、ガンマ波が脳全体で強く発生します。このため、「ガンマ波を増やすことで学習効率が向上する」とも言われています。
一方で、ガンマ波の減少は注意力の低下や記憶力の低下を引き起こすことがあり、近年ではアルツハイマー病などの認知症とも関連があることが明らかになっています。
そのため、ガンマ波を増やすための方法として、瞑想や音楽、さらには脳を刺激する技術などが注目されています。
認知症とブレインテックの関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
VIE社のガンマ波研究の最前線を紹介
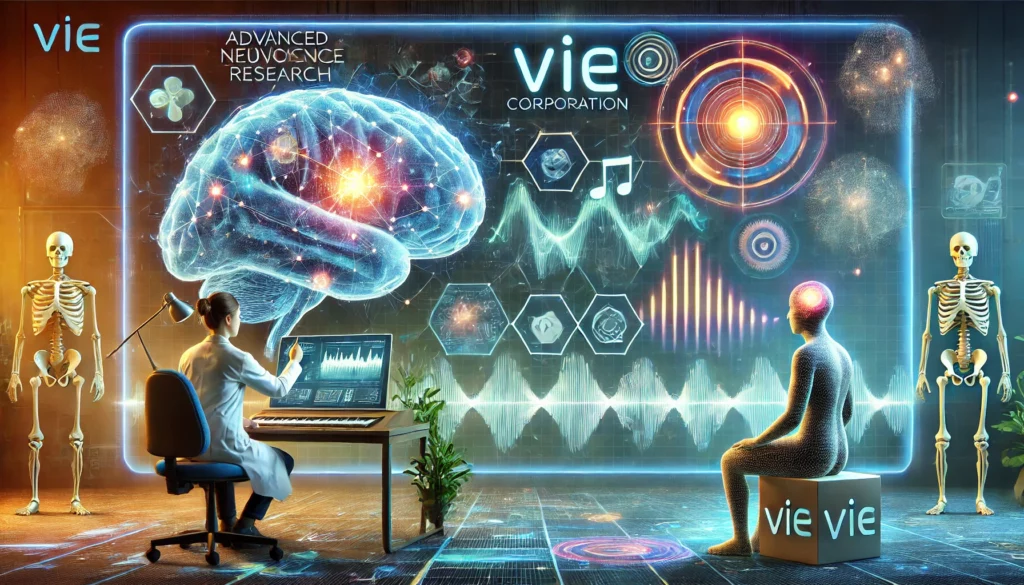
VIE社は、脳科学とエンターテインメントを融合させた先進的な研究や事業開発を行っている企業です。ガンマ波の研究にも注力しており、これまでの研究成果や実際に事業化しているものをいくつかご紹介します。
ガンマミュージックの研究成果
VIE社は、ガンマ波を活性化させる音響刺激「ガンマミュージック」を開発しました。ガンマ波の40Hzの単調な音刺激は不快に感じられることが多く、長時間聴くのが難しいという課題がありました。これを解決するため。ドラム、ベース、キーボードなどの楽器音に40Hzの振動を組み込み、心地よく聴ける音楽としてガンマミュージックを作成することに成功しました。
実験では、ガンマミュージックを聴いた参加者は、高いリラクゼーションや快適さを感じるとともに、脳が刺激を正確に処理している状態であることを示す聴覚定常状態反応(ASSR)が強く誘発されることが確認されました。
ガンマミュージックの効果は、認知機能の向上や調整における新しいアプローチとして注目されており、この研究成果により、さらなる応用研究が進むことが期待されます。
論文についてはこちらの記事を参照ください。
ガンマ波を活用した事業の取り組み
ガンマ波を取り入れたカラオケ
VIE社は、JOYSOUNDを展開する株式会社エクシングと共同で、「ガンマ波カラオケ」を開発し、2024年7月5日から全国で配信を開始しました。
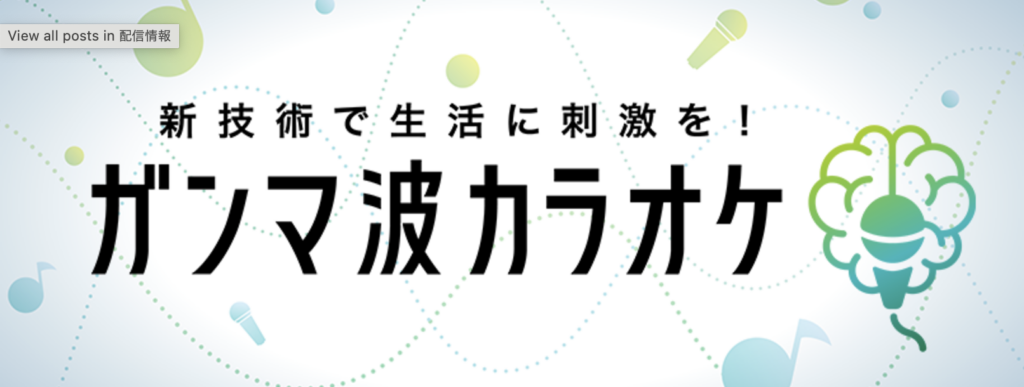
この「ガンマ波カラオケ」は、ガンマ波の力を活用し、カラオケの楽しさを取り入れながら、高齢化社会が直面する課題にアプローチする新しい取り組みです。
ガンマ波は、記憶や思考を行う際に現れる脳波であり、ガンマ波の音を聴かせることで、マウスの認知機能が改善されたり、ヒトを対象とした臨床試験で認知機能の低下や脳萎縮の抑制が期待できる可能性が示されています。
「ガンマ波カラオケ」では、楽しみながら生活に刺激をプラスし、高齢化社会が抱える課題を音楽を通じて解決することを目指しています。配信楽曲には、BEGINの「島人ぬ宝」や川中美幸の「二輪草」など、幅広い世代に愛される全30曲が含まれています。
この取り組みにより、高齢化社会における健康的で楽しい生活の実現が期待されています。
ガンマ波カラオケについては以下のサイトをご参照ください。
音楽配信サービスVIE Tunes
VIE Tunesは、脳をととのえるニューロミュージックを提供する音楽アプリです。このサービスは、科学的根拠に基づいた音楽を通じて、ユーザーの集中力向上やリラクゼーションを効果的にサポートします。
VIE Tunesの最大の特徴は、ユーザーの状態や目的に応じた音楽を提供できる点です。例えば、シーンボタンで「仕事」や「睡眠」を選択したり、「リラックス」から「フォーカス」にスライドして調整することで、必要に応じた脳の状態を引き出すことが可能です。
VIE Tunesについては以下のサイトをご参照ください。
ガンマ波の応用可能性

ガンマ波は、認知機能の改善や感情の安定に深く関わる脳波として注目されており、その応用範囲はヘルスケア、教育、エンターテインメントなど多岐にわたります。以下では、具体的な応用分野について詳しく解説します。
ガンマ波×ヘルスケア
ガンマ波の活性化は、アルツハイマー病や認知症の予防・改善に有効とされています。研究では、40Hzの音波刺激をマウスに与えた結果、脳内の老廃物(アミロイドβ)の蓄積が減少し、認知機能が改善されたという成果が得られています(1)。この知見を基に、脳波を活用した音響療法やデバイスの開発が進んでいます。
またヘルスケア分野では、ガンマ波を利用したリラクゼーション技術が注目されています。ガンマ波は、深い集中状態やマインドフルネスの実践中に観測されることが多く。ガンマ波を刺激する音楽は、ストレス軽減や感情の安定を促進するツールとして、働く世代から高齢者まで幅広い層にメリットが期待されています。
(1)Iaccarino, H. F., et al. (2024). Multisensory gamma stimulation promotes glymphatic clearance of amyloid. *Nature*, 615, 232–236. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07132-6
ガンマ波×教育
ガンマ波は、記憶力や集中力の向上に寄与することが示されていますが、現時点では、ガンマ波を活用した学習アプリやデバイスはまだ実用化されていません。しかし、ガンマ波を活用した学習デバイスとして、例えばヘッドセット型のデバイスを装着することで、学習中のガンマ波をモニタリングし、最適なタイミングで刺激を与えるシステムが開発されるかもしれません。
さらに未来の学校では、ガンマ波を利用した学習環境が整備され、教室内で流れる音楽や視覚コンテンツがガンマ波を活性化し、子どもたちが集中力を高めながら学ぶ環境を提供する日が来るかもしれません。
ガンマ波×エンターテインメント
ガンマ波は、感情の高まりや深い集中状態と関連しており、エンターテインメント分野においても大きな可能性を秘めています。例えば、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術と組み合わせることで、ユーザーの脳波状態をリアルタイムでモニタリングし、映画やゲームのシーンがユーザーの感情や集中度に応じて動的に変化するシステムが開発されるかもしれません。
ユーザーが没入感を高めたい場面ではガンマ波を活性化する音響や映像効果が自動的に提供されることで、これまでにない没入型エンターテインメント体験が実現するでしょう。
さらに、ライブコンサートや舞台公演では、観客の脳波状態をフィードバックし、パフォーマンス内容や照明、音響がリアルタイムに最適化されるといった新たな演出手法も考えられます。
こうした技術が進展すれば、エンターテインメントは単なる受動的体験ではなく、ユーザー自身の脳の状態がコンテンツを形作る「双方向型体験」へと進化し、これまでにない感動や興奮を生み出すことが期待されます。
ガンマ波活用の課題と展望

ガンマ波を活用した技術は、教育、医療、エンターテインメント分野で大きな可能性を秘めています。しかし、実用化には克服すべき課題も残されています。以下では、その課題と克服後に期待される展望についてご紹介します。
課題1:脳波の測定と分析の精度向上
脳波は非常に微弱な生体信号であり、外部環境のノイズや体の動きによる影響を受けやすいという課題があります。その中でもガンマ波は高周波の成分を持つため、他の脳波と比べてノイズとの分離が難しく、正確な測定と分析には高度な技術が必要です。
さらに、医療機関や実験室と異なり、日常的な環境下では周囲の電磁波や動作ノイズが増加し、計測のハードルが一層高まります。そのため、今後は脳波センサー技術の小型化・高感度化や、AIを活用したデータ解析技術の高度化が求められます。特にリアルタイムでのノイズ除去や、動きながらでも安定した脳波計測を可能にする技術革新が、実用化のカギとなるでしょう。
課題2:脳波データのプライバシー保護
脳波データは、個人の心理状態や健康状態、さらには認知能力やストレスレベルなど、非常にデリケートな個人情報を含んでいます。このため、不正アクセスやデータ漏洩が発生した場合、プライバシー侵害のリスクは極めて深刻です。特に、医療や教育分野で脳波データを活用する場合、より高いレベルのデータ保護対策が求められます。
技術的には、データ暗号化や匿名化技術の高度化、アクセス権限の厳格な管理が不可欠です。また、脳波データの収集や活用に関して、利用者本人や保護者への明確な説明と同意(インフォームド・コンセント)が徹底されることが重要です。こうした技術的・法的・倫理的側面の連携が、安心して脳波データを活用できる社会の実現には欠かせません。
展望1:ウェアラブルデバイスとの統合
将来的には、ガンマ波を計測・分析できるウェアラブルデバイスが日常生活に自然に溶け込むことが期待されます。例えば、軽量でスタイリッシュなヘッドセットやVIE Zoneのようなイヤホン型デバイスが普及すれば、特別な環境や高度な設備がなくても、いつでも手軽に脳の状態をモニタリングし、集中力の向上やリラックス、ストレス管理が可能になるでしょう。
VIE Tunes Proについてはこちら
さらに、スマートフォンやタブレットとの連携により、脳波データをリアルタイムで可視化し、ユーザーに適切なフィードバックを提供するアプリケーションの開発も進むと考えられます。これにより、個人のライフスタイルやニーズに合わせた脳の健康管理がより身近なものとなり、日常生活や仕事、学習の質が向上することが期待されます。
展望2:パーソナライズド技術の発展
脳波データを活用したパーソナライズド技術の進化により、個々のユーザーに合わせた音楽、学習プログラム、リラクゼーション体験が提供される未来が期待されます。脳の状態をリアルタイムで解析し、その瞬間に最適な音響、映像、刺激を自動調整するシステムが開発されれば、ユーザーは常に自身に合った環境や体験を得ることができるでしょう。
例えば、集中力が低下している際には注意力を高める音楽が流れ、ストレスが高まっている場合にはリラックス効果のあるコンテンツが自動的に提供されるようになります。さらに、教育現場では、生徒一人ひとりの脳波データに基づき、学習内容や進行速度が調整されることで、より効果的な教育が実現できる可能性があります。
ガンマ波の可能性を追い求めて

ガンマ波技術は、脳科学とテクノロジーの融合によって、新たな価値を生み出す可能性を秘めています。医療、教育、エンターテインメント、さらには日常生活のさまざまな場面で活用が期待されており、その影響範囲は今後ますます広がることでしょう。
技術的な課題や倫理的配慮は依然として重要ですが、脳波デバイスの進化やAIを活用したデータ解析技術の進展により、より自然に、より効果的に脳波技術を活用する未来が見えてきました。VIE株式会社をはじめとする研究・開発の最前線では、ガンマ波を活かした具体的な取り組みが進められています。
ガンマ波の可能性を追求する取り組みは、ただ技術を発展させるだけではなく、より健康的で充実した人生、そして豊かな社会の実現へとつながっていくでしょう。
WRITER
Sayaka Hirano
NeuroTech Magazineの編集長を担当しています。
ブレインテックとウェルビーイングの最新情報を、専門的な視点だけでなく、日常にも役立つ形でわかりやすく紹介していきます。脳科学に初めて触れる方から、上級者まで、幅広く楽しんでもらえる記事を目指しています。
一覧ページへ戻る


