メンタルヘルスとは?職場での対策と個人でできるケア
日々の忙しさの中で、気分がすぐれなかったり、仕事に集中できなかったりすることはありませんか? 疲れが取れにくくなったり、やる気が出なかったりするのは、心の健康が影響しているサインかもしれません。そのまま放置すると、仕事のパフォーマンスや人間関係にも影響を及ぼすことがあります。
メンタルヘルスは、誰にとっても大切なもの。ただ「うつを防ぐ」だけでなく、心のバランスを整え、前向きに過ごすための基盤となります。本記事では、メンタルヘルスの基本から、企業の取り組み、職場でのストレス対策、そして個人でできるセルフケアまで、具体的な方法を紹介します。
なんとなく不調を感じるときこそ、心のケアを見直すタイミング。今日から実践できる対策を一緒に考えていきましょう。
メンタルヘルスとは?
メンタルヘルスとは、世界保健機関(WHO)の定義によれば、「単に精神疾患がない状態ではなく、個人が自身の能力を発揮し、通常の生活のストレスに対処し、生産的に働き、社会に貢献できる状態」を指します(1)。精神的に安定していると、仕事のパフォーマンスが向上し、人間関係も円滑になり、生活の質が向上します。
一方で、ストレスや不安が長期間続くと、心身のバランスが崩れ、うつ病や適応障害などの精神疾患を引き起こすリスクが高まります。現代社会では、多くの人が仕事や生活の中で何らかのストレスを抱えています。特に職場環境の変化が激しい昨今、メンタルヘルスを守ることは個人だけでなく、企業や社会全体にとっても重要な課題となっています。
(1)参照:https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400227881.pdf
なぜ今、メンタルヘルスが重要なのか?
近年、メンタルヘルスの重要性が急速に高まっています。その背景には、働き方や社会環境の変化が大きく影響しています。
かつては「少しくらいのストレスは我慢するもの」「仕事は多少つらくても仕方がない」といった考え方が一般的でした。しかし、ストレスや長時間労働が健康に深刻な影響を与えることが明らかになり、企業や国も積極的にメンタルヘルス対策に取り組むようになっています。
テクノロジーの発展や経済のグローバル化により、ビジネス環境は急速に変化しています。それに伴い、多くの労働者がプレッシャーを感じるようになり、メンタルヘルスの問題を抱えるケースが増えています。
例えば、常に高い成果を求められる仕事環境では、精神的な負担が大きくなり、ストレスが蓄積しやすくなります。また、リモートワークの普及により、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、長時間労働や孤独感を感じる人が増えているのも一因です。
さらに、メンタルヘルスの不調は個人だけでなく、企業や社会全体にも影響を及ぼします。メンタルヘルスが損なわれることで、仕事の生産性が低下し、離職率が上昇するだけでなく、社会全体の医療費や社会保障費の増加にもつながるのです。このような状況を踏まえ、メンタルヘルスの維持・向上は、個人の幸福だけでなく、企業や社会の持続的な発展にとっても不可欠な要素となっています。
企業におけるメンタルヘルスの課題

企業においても、従業員のメンタルヘルス対策は重要な経営課題として認識されるようになり、多くの職場でストレスチェック制度の導入や相談窓口の設置などが進んでいます。
しかし、対策が形式的にとどまっていたり、従業員が気軽に相談しづらい雰囲気があったりするなど、まだ改善の余地がある職場も少なくありません。特に、リモートワークの普及や働き方の多様化が進む中で、より柔軟かつ実効性のあるメンタルヘルス施策が求められています。
長時間労働と過重労働の常態化
日本では、働き方改革の影響もあり、長時間労働の是正が進んでいます。しかし、業種や職種によっては依然として業務負担が大きく、ストレスが慢性化しやすい環境にある人も少なくありません。
特に、管理職やリーダー層では、責任感の強さから「自分が休むわけにはいかない」と無理を重ね、結果としてメンタル不調に陥るケースが課題となっています。こうした状況を改善するためには、個人の意識改革だけでなく、組織全体でのサポート体制の充実が求められています。
職場の人間関係によるストレス
職場の人間関係は、メンタルヘルスに大きく影響を与える要因のひとつです。上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかない場合、職場環境がストレスの要因となることがあります。
また、厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」では、パワハラやモラハラなどのハラスメントを経験したと回答した人の割合が一定数存在することが分かっており、これがメンタルヘルスの悪化につながるケースも指摘されています。企業においては、対策の強化が求められています。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html
リモートワークによる新たな課題
コロナ禍をきっかけに、多くの企業がリモートワークを導入しました。これにより通勤時間が減るなどのメリットがある一方で、社員同士のコミュニケーション不足や、仕事のオンオフの切り替えが難しくなるといった新たな問題が浮上しています。オフィスに出社していた時には何気なくできていた相談や雑談が減り、一人で業務を抱え込んでしまうことで、精神的な負担が増してしまうケースも少なくありません。
メンタルヘルス不調のサインを知る
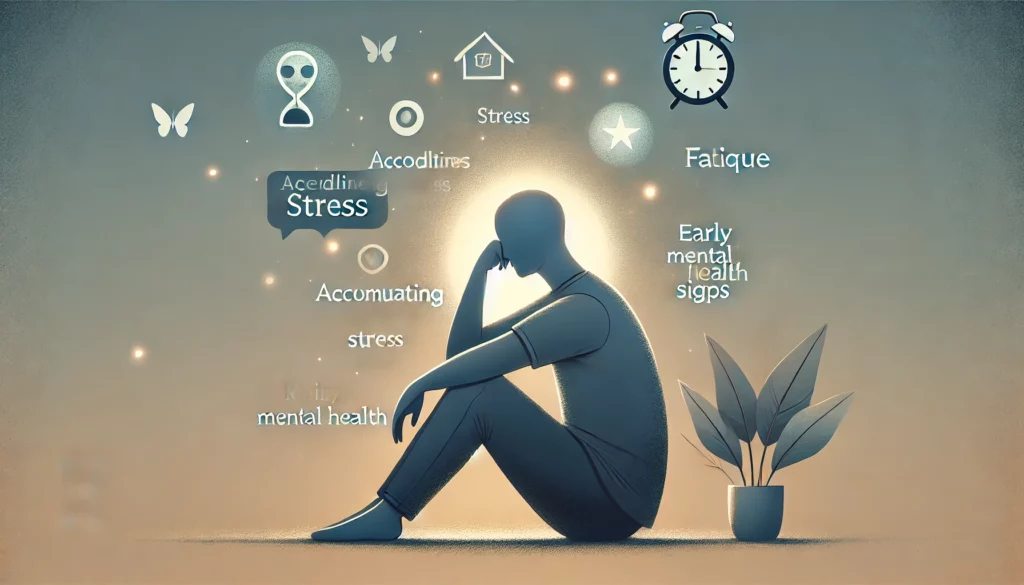
メンタルヘルスの不調は、突然起こるものではなく、日々の生活の中で少しずつ蓄積されていくものです。しかし、多くの人はそのサインに気づかず、「疲れているだけ」「少し頑張れば大丈夫」と無理をしてしまいがちです。気づかないまま放置してしまうと、次第に気持ちが落ち込み、仕事や日常生活に支障をきたすこともあります。
また、自分のメンタルヘルスだけでなく、周囲の人の変化にも気を配ることが大切です。職場では、日々一緒に働く同僚や部下の様子を見て、いつもと違う変化がないか気づくことができるかもしれません。早めに異変を察知し、適切な対応を取ることで、不調を悪化させずに済む可能性が高まります。
自分自身のメンタル不調をチェックしよう
ストレスや疲れが原因で気持ちが落ち込むことは誰にでもありますが、それが長引いている場合や、普段とは違う症状が出ている場合は注意が必要です。以下のような変化が続く場合、メンタルヘルスに問題が生じている可能性があります。
1. 気分の変化
以前は楽しめていたことに対して、興味や関心が薄れていると感じることはありませんか?好きだった趣味が面倒に感じたり、何をしても楽しくないと感じる場合は、精神的なエネルギーが低下しているサインかもしれません。また、理由もなくイライラしたり、不安感が強くなることもメンタルの不調を示す兆候のひとつです。
2. 体調の変化
メンタルヘルスの不調は、身体にも影響を及ぼします。例えば、慢性的な頭痛、胃の不快感、肩こり、動悸などの症状が続く場合、それはストレスが身体に影響を与えている可能性があります。また、食欲が極端に減る、または過食してしまうといった変化も、精神的なストレスが原因で起こることがあります。
3. 睡眠の異常
寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝スッキリ起きられないなど、睡眠に問題を感じることはありませんか?メンタルの不調が進行すると、睡眠の質が低下し、さらに心身の回復が遅れるという悪循環に陥ることがあります。逆に、異常なほど長時間眠り続けてしまうことも、ストレスや心の疲れのサインです。
4. 仕事や日常のパフォーマンスの低下
集中力が続かない、ミスが増える、仕事への意欲が湧かないといった状態は、メンタルヘルスの不調が影響しているかもしれません。これまで当たり前にできていた作業に手間取るようになったり、やる気が起きず仕事を先延ばしにしてしまう場合は、精神的な疲労が蓄積している可能性があります。
5. 社会的な交流の減少
人と話すのが億劫になったり、LINEや電話の返信が面倒になったりすることはありませんか?メンタルの調子が悪いと、人との関わりを避けたくなることがあります。職場や友人とのコミュニケーションが減ってきたと感じたら、自分の心の状態を振り返ることが大切です。
もしこれらのサインに思い当たることがあれば、「まだ大丈夫」と無理をせず、少し立ち止まって心のケアをすることが重要です。特に、症状が長期間続いている場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
職場でのメンタル不調のサイン
メンタルヘルスの不調は、職場の中でも表れることがあります。特に、周囲の同僚や部下がいつもと違う行動を取っている場合、それがメンタルの問題によるものかもしれません。職場でのメンタルヘルス不調のサインに気づき、適切なサポートを行うことは、チーム全体の働きやすさを向上させることにもつながります。
1. 表情や態度の変化
普段は明るく振る舞っていた人が急に口数が減ったり、無表情になったりしている場合は、心に何かしらの負担を抱えている可能性があります。逆に、突然イライラしやすくなったり、怒りっぽくなることも、ストレスが原因となっていることがあります。
2. 仕事のミスやパフォーマンスの低下
仕事の進捗が遅れがちになったり、ミスが目立つようになった場合、メンタルの不調が影響している可能性があります。特に、普段は几帳面でミスが少ない人が急に注意散漫になったり、物事を忘れやすくなっている場合は、一時的な疲れではなく、心の負担が蓄積しているサインかもしれません。
3. 遅刻や欠勤の増加
普段は時間を守る人が頻繁に遅刻したり、理由をつけて休みがちになる場合、心身の疲れが溜まっているかもしれません。特に、「体調が悪い」と言いながら休む回数が増えたり、「仕事がしんどい」と口にすることが多くなった場合は、早めに話を聞いてみることが大切です。
4. 職場での人間関係の変化
チームでの会話にあまり参加しなくなったり、周囲との距離を取るようになった場合は、メンタルの不調が影響している可能性があります。逆に、必要以上に攻撃的な態度を取るようになった場合も、ストレスが溜まっているサインかもしれません。
職場でこうしたサインを見つけたら、「何か困っていることはない?」とさりげなく声をかけることで、相手が悩みを打ち明けやすくなるかもしれません。無理に詮索する必要はありませんが、ちょっとした気遣いが、大きな支えになることもあります。
企業が実施するメンタルヘルス対策とは?事例付きで解説

メンタルヘルスの問題は、個人だけの課題ではなく、企業全体で取り組むべき重要なテーマとなっています。メンタルヘルス対策を進める企業は増えており、その取り組みも多様化しています。ここでは、実際に導入されている具体的な施策を紹介し、企業がどのように従業員の心の健康を守っているのかを見ていきましょう。
こちらの記事もチェック
1. ストレスチェック制度の活用
企業のメンタルヘルス対策として最も一般的なのが「ストレスチェック制度」です。2015年に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業所には毎年1回のストレスチェックが義務付けられました。これにより、従業員が自分のストレス状態を客観的に把握し、必要に応じて産業医やカウンセラーに相談できる環境が整備されています。
ストレスチェックは、単に従業員のストレスを測定するだけでなく、企業が職場環境を改善するための重要な指標としても活用されています。例えば、ストレスが高い部署が特定された場合、その部署の働き方や業務負担を見直すことで、職場全体のメンタルヘルスを向上させることができます。
【事例】川崎市消防局のストレスチェック活用法
川崎市消防局では、ストレスチェックの結果を活用し、全ての高ストレス者に対して保健師による補助面談を実施し、個別のフォローアップを行っています。また、半年に1回、保健師が各消防署を巡回し、健康診断後のフォローや高ストレス者への面談を行うことで、職員のストレス軽減に努めています。
2. 従業員支援プログラム(EAP)の導入
「EAP(Employee Assistance Program)」とは、企業が従業員のメンタルヘルスを支援するために提供するプログラムのことです。これは、専門のカウンセラーや心理士による相談サービスを企業が提供する仕組みで、メンタルヘルスだけでなく、仕事や家庭の問題、法律や財務に関する相談など、幅広いサポートが受けられるのが特徴です。
企業がEAPを導入することで、従業員が職場のストレスや個人的な悩みを気軽に相談できる環境が整います。特に、職場の上司や同僚には話しづらい悩みを抱えている場合、外部の専門家に相談できることは大きな安心感につながります。
【事例】大成建設株式会社のEAP導入事例
大成建設株式会社では、2001年より外部のカウンセリング機関と提携し、従業員とその家族が匿名で無料相談できるEAP(従業員支援プログラム)を導入しています。このプログラムでは、メールや電話を通じて外部の専門カウンセラー(衛生保健福祉士、臨床心理士等)に相談できる体制を整えています。
導入当初はEAPの認知度が低く、社員の相談利用に対するハードルがあったものの、プロモーションビデオの作成や利用案内の配布などの普及活動を進めた結果、相談件数が徐々に増加しました。このように、EAPの活用促進には、従業員に向けた継続的な情報発信が重要であることが分かります。
参照:https://www.jes.ne.jp/casestudy/taiseikensetsu
3. ハラスメント防止対策の強化
メンタルヘルスの悪化には、職場の人間関係が大きく関与していることも少なくありません。特に、パワハラやセクハラなどのハラスメントは、被害者の精神的な健康を著しく損なうだけでなく、職場全体の雰囲気を悪化させる原因にもなります。そのため、多くの企業がハラスメント防止策を強化し、健全な職場環境を維持する取り組みを進めています。
【事例】ソニー銀行株式会社のハラスメント対策
ソニー銀行株式会社では、企業理念である「自由豁達で愉快な業務環境を整備する」を基盤に、ハラスメント防止に積極的に取り組んでいます。特段ハラスメントが多発していたわけではありませんが、多様な人材が集まる企業であるからこそ、さまざまなハラスメントが発生する可能性があると考え、予防的な対策が必要と判断しました。
こうした背景を踏まえ、ソニー銀行では全従業員を対象にセクシュアルハラスメント防止研修を定期的に実施し、管理職には適切なコミュニケーション方法の指導を強化。また、社内外に3つの相談窓口を設置し、従業員が匿名で相談しやすい体制を整えました。これにより、ハラスメントの兆候が見られた際の早期対応が可能となり、従業員が安心して働ける環境づくりが進められています。
参照:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/another-company/archives/2
個人でできるメンタルケア

メンタルヘルスを守るためには、企業のサポートや周囲の理解も重要ですが、それと同じくらい「自分自身でできる対策」も大切です。毎日のストレスをうまくコントロールし、心の健康を維持することが、長期的なメンタルヘルスの向上につながります。
すぐに実践できるストレスマネジメント
日々の生活や仕事の中で、知らず知らずのうちにストレスが溜まっていることがあります。ストレスを完全になくすことはできませんが、適切に発散することで心の負担を軽減できます。
1. 深呼吸やマインドフルネスを取り入れる
ストレスが高まったとき、無意識に呼吸が浅くなっていることがあります。そんなときは、一度ゆっくりと深呼吸をしてみましょう。鼻からゆっくり息を吸い込み、口から細く長く吐き出すことで、自律神経が整い、気持ちが落ち着いていきます。
また、「マインドフルネス瞑想」も効果的です。数分間、目を閉じて深く呼吸しながら、自分の内面に意識を向けるだけでも、気持ちがリセットされることがあります。
こちらの記事もチェック:瞑想の記事
2. 書くことで気持ちを整理する(ジャーナリング)
ストレスや悩みを頭の中だけで抱えていると、余計に気持ちがモヤモヤしてしまいます。そんなときは、「書くこと」を習慣にしてみましょう。紙やノートに思っていることを書き出すことで、自分の気持ちを客観的に整理でき、ストレスの軽減につながります。
特に、1日の終わりに「今日よかったこと」を3つ書き出すだけでも、前向きな気持ちになりやすくなります。
3. 「今できること」に集中する
ストレスがたまると、「あれもやらなきゃ」「この先どうなるんだろう」と不安が膨らみがちです。そんなときは、「今この瞬間にできること」に意識を向けることで、気持ちを整理しやすくなります。
例えば、「とりあえずコーヒーを飲んでひと息つく」「5分だけ散歩をする」など、小さな行動から始めることで、気持ちが落ち着きやすくなります。
健康的な生活習慣で心を整える
メンタルヘルスは、心の問題だけでなく、体の健康とも深く関わっています。食事や睡眠、運動などの生活習慣を見直すことで、ストレス耐性を高めることができます。
1. 睡眠の質を向上させる
睡眠不足は、メンタルヘルスに大きな影響を与えます。寝不足が続くと、集中力が低下し、ストレス耐性も下がってしまいます。睡眠の質を向上させるためには、以下のような工夫を取り入れると良いでしょう。
・寝る前にスマホやPCの画面を見る時間を減らす(ブルーライトは睡眠の質を下げる)
・寝る1時間前にはリラックスする時間を作る(読書やストレッチなど)
・朝起きたら太陽の光を浴びることで、体内リズムを整える
2. バランスの良い食事を意識する
食事の栄養バランスも、メンタルヘルスに影響を与えます。特に、「腸内環境」が心の健康に密接に関わっていることが研究で明らかになっています。発酵食品や食物繊維を意識的に摂取することで、腸内環境を整え、メンタルの安定にもつながります。
また、カフェインやアルコールの過剰摂取はストレスを増幅させることがあるため、適度に抑えることが大切です。
3. 軽い運動を習慣にする
運動は、ストレス解消に非常に効果的です。激しい運動でなくても、1日10分のストレッチやウォーキングをするだけで、気分がスッキリしやすくなります。運動によって脳内に「セロトニン(幸福ホルモン)」が分泌され、精神的な安定を促します。
特に、自然の中でのウォーキング(森林浴)は、リラックス効果が高いと言われています。週末に公園や自然の多い場所で散歩をするのもおすすめです。
職場でも、自分でも。心の健康を大切にしよう

メンタルヘルスは、個人の問題ではなく、職場全体、そして社会全体で取り組むべき重要な課題です。仕事や日常生活の中で、ストレスやプレッシャーを完全になくすことはできません。しかし、企業と個人がそれぞれの立場で意識し、適切な対策を講じることで、ストレスを軽減し、心の健康を守ることは可能です。
メンタルヘルスは、仕事のパフォーマンスや人生の質を大きく左右するものです。心の健康を維持することは、自分自身を大切にすることであり、職場や社会にとってもプラスになる行動です。企業と個人がともに支え合い、メンタルヘルスを守るための環境をつくることが、より良い未来へとつながります。今日から、自分自身の心の声に耳を傾け、職場でもプライベートでも、心の健康を大切にしていきましょう。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る


