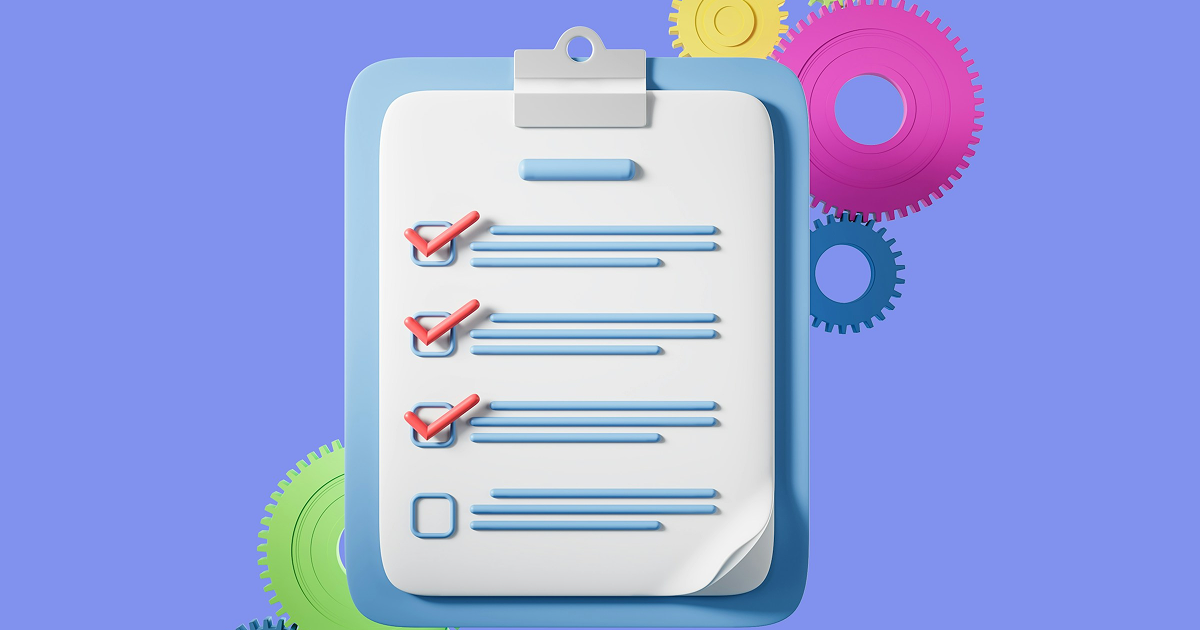ストレスチェック制度の意味と目的|企業が実施すべき方法と注意点
現代の職場では、業務負担や人間関係の問題、長時間労働など、さまざまなストレス要因が存在し、それが生産性の低下や人材流出につながるリスクを高めています。
そこで重要なのがストレスチェック制度の適切な運用です。ただ義務として実施するだけではなく、結果を活かして職場環境を改善することで、従業員の健康を守り、組織の成長にもつなげることができます。
本記事では、ストレスチェックの実施方法や企業の義務、罰則、さらには効果的な活用方法について詳しく解説します。従業員が安心して働ける環境を整え、企業の持続的な発展を目指しましょう。
ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、職場で働く人の心理的な負担(ストレス)を把握し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐための制度です。仕事上のストレスが過度に蓄積されると、心身の健康に影響を及ぼすことがあるため、定期的にストレスの状態を確認し、必要な対策を講じることが求められています。
この制度の目的は、個人のストレス状態を可視化するだけでなく、組織全体の職場環境の改善にも役立てることです。従業員が健康的に働ける環境を整えることで、生産性の向上や職場の定着率向上にもつながります。特に近年では、働き方改革の一環として、企業が積極的にメンタルヘルス対策を行うことが重要視されています。
なぜストレスチェックが必要なのか(労働安全衛生法との関係)
ストレスチェック制度は、2015年に労働安全衛生法の改正によって義務化されました。これは、長時間労働や職場のプレッシャーによる精神的な健康問題が増加し、社会的にも大きな課題となっていたことが背景にあります。
この制度ができるまで、日本では「長く働くこと」や「厳しい環境で成果を出すこと」が重視されがちでした。しかし、その結果として、メンタルヘルスの不調を抱える人が増え、企業にとっても労働生産性の低下や離職率の上昇といったリスクを招く要因となっていました。
こうした課題を解決するために、企業には従業員の心の健康を管理する責任が求められるようになりました。ストレスチェックを通じて職場のストレス状況を把握し、必要に応じて職場環境の改善や専門的な支援を提供することが、企業の重要な役割となっています。
ストレスチェックが義務となる企業とは?
後ほど、詳しく説明をしますが、ストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者を雇用している事業場に課せられています(参照:ストレスチェック制度の意味と目的)。この「50人以上」という基準には、正社員だけでなく、一定の雇用形態で継続的に働く契約社員や派遣社員なども含まれることがあります。そのため、中規模以上の企業は必ずストレスチェックを実施する必要があります。
一方、50人未満の企業については、法律上の義務はないものの、実施が推奨されています(努力義務)。メンタルヘルス対策の重要性が高まる中、規模に関わらずストレスチェックを導入する企業も増えてきています。特に、従業員の健康管理を重視する企業では、法的義務の有無にかかわらず積極的に取り組んでいます。
ストレスチェックを行うメリット

ストレスチェックは、単なる義務ではなく、企業と従業員双方にとって大きな意義を持つ制度です。職場でのストレスを放置すると、メンタルヘルスの不調を引き起こし、個人のパフォーマンス低下や企業全体の生産性の悪化につながる可能性があります。
従業員の健康維持とパフォーマンス向上
ストレスチェックを行うことで、従業員は自分のストレス状態を客観的に把握することができます。
日々の業務の中で「なんとなく疲れている」「仕事のモチベーションが上がらない」と感じていても、その原因を明確にすることは簡単ではありません。しかし、ストレスチェックの結果を見れば、現在の心理的な負担のレベルを数値化して理解することができ、必要に応じて適切な対策を講じることが可能になります。
また、ストレスが軽減されることで、集中力が向上し、業務効率も改善されます。仕事のパフォーマンスが向上することで、個人の達成感やモチベーションにも好影響を与え、より良い働き方ができるようになります。
離職率の低下と職場定着の促進
メンタルヘルスの問題が原因で、休職や退職に至るケースは少なくありません。特に、長時間労働や人間関係のストレスが原因で心の不調を抱えると、従業員が会社を離れる可能性が高まります。
ストレスチェックを通じて、こうした問題を早期に発見し、適切なケアを行うことで、従業員の離職を防ぐことができます。また、企業がメンタルヘルス対策に積極的に取り組むことで、「この会社は社員の健康を大切にしている」と感じる従業員が増え、職場への定着率が向上します。
職場環境の改善と生産性向上
ストレスチェックの結果を分析することで、企業は職場の課題を明確にし、環境の改善に役立てることができます。例えば、特定の部署でストレスが高い傾向が見られる場合、その原因を探り、業務負担の見直しや職場のコミュニケーションの改善を行うことで、働きやすい環境を整えることが可能になります。
また、職場のストレスが軽減されることで、従業員は安心して働けるようになり、結果的に業務の効率化やパフォーマンスの向上につながります。特に、心理的な安全性が確保されると、チームワークの向上や積極的な意見交換が促され、組織全体の活性化にもつながるでしょう。
ストレスチェックの実施方法と進め方

ストレスチェックは、従業員の心理的負担を測定し、メンタルヘルスの状態を把握するために行われます。企業が適切に実施するには、事前の準備、従業員への周知、結果のフィードバック、必要に応じた対応策の検討など、段階的なプロセスが必要です。
本章では、ストレスチェックの具体的な実施方法について、自社内で運用する方法と外部機関を活用する方法の2つの選択肢を解説します。
ストレスチェックの実施方法
ストレスチェックの実施方法は、企業の規模や体制によって異なります。主に、「社内での実施」と「外部機関の活用」の2つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選ぶことが重要です。
1. 社内で実施する方法
社内の産業医や人事担当者が主導してストレスチェックを実施する方法です。特に大企業では、健康管理システムを導入し、従業員がオンラインで回答できる環境を整えているケースも増えています。
メリット
- コストを抑えながら、社内の状況に応じた柔軟な運用が可能
- 企業文化や職場環境を踏まえた対応ができる
注意点
- ストレスチェックに関する専門知識が必要
- 産業医やカウンセラーとの連携が不可欠
自社での実施は、社内に産業保健の専門家がいる場合や、すでにメンタルヘルス対策に取り組んでいる企業に向いています。
2. 外部機関を活用する方法
ストレスチェックを専門とする企業や医療機関に委託する方法です。特に中小企業では、ストレスチェックの運用ノウハウが不足していることが多いため、外部機関のサポートを活用することでスムーズに実施できます。
メリット
- 専門的な分析が可能で、データの精度が高い
- 個人情報の管理が徹底され、従業員が安心して回答できる
注意点
- コストがかかる場合がある
- 企業の文化や状況を踏まえた対応がしにくい場合も
外部機関を利用することで、社内のリソースを最小限に抑えながら、専門的な知見を活かしたストレスチェックを実施できます。
ストレスチェックを実施する際のポイント

ストレスチェックを効果的に実施するためには、単にアンケートを行うだけではなく、適切な準備やフォローが重要です。
実施の目的を明確にし、従業員が安心して参加できる環境を整え、結果を職場改善につなげることが求められます。また、形だけのチェックになってしまうと、本来の目的であるメンタルヘルスの維持・向上や職場環境の改善が実現できません。
そこで、ストレスチェックを実施する際に押さえておくべき3つのポイントを紹介します。これらを意識することで、チェックの精度を高め、企業と従業員双方にとって有益なものにすることができます。
従業員の安心感を確保することが最優先
ストレスチェックを実施する際、最も大切なのは、従業員が安心して受けられる環境を整えることです。心理的な状態を正直に回答してもらうためには、結果の扱いが明確であること、プライバシーが確実に守られることを従業員に理解してもらう必要があります。
特に、従業員が「この結果が人事評価に影響するのでは?」と不安に感じると、本音で回答しづらくなります。そのため、ストレスチェックの結果は、本人の同意なしに会社が閲覧することはできないことや、職場環境の改善のために活用することを事前に周知することが重要です。
また、回答方法についても、できるだけ負担が少ない仕組みを整えることで、従業員が抵抗なく参加できるようになります。例えば、オンラインで手軽に回答できる環境を用意したり、勤務時間内に実施できるように配慮したりすることが効果的です。
チェック結果を職場環境の改善につなげる
ストレスチェックの本来の目的は、職場環境をより良くすることです。しかし、実施しただけで何のアクションも起こさないと、「形だけの取り組み」となり、従業員の信頼を失う可能性があります。結果のデータを活用し、組織全体のストレス要因を分析し、具体的な改善策を講じることが不可欠です。
例えば、特定の部署でストレスレベルが高いことが判明した場合、その原因を探り、業務負担の見直しやコミュニケーションの改善など、具体的な対策を検討する必要があります。また、ストレスの主な要因が長時間労働やハラスメントである場合、労働時間の管理や職場内でのハラスメント防止策を強化することが求められます。
改善策を講じる際には、従業員の意見を取り入れながら、現場の実情に即した対策を考えることが重要です。
継続的な取り組みとして定着させる
ストレスチェックは一度実施すれば終わりではなく、継続的な取り組みとして定着させることが大切です。ストレスの要因は、企業の状況や社会情勢の変化によって変わるため、一度のチェックだけで十分とは言えません。
そのため、定期的に実施することを前提にし、「ストレスチェック → 分析 → 改善 → 再評価」のサイクルを回すことが求められます。こうすることで、職場環境の改善を継続的に進めることができ、従業員の健康管理にもつながります。
また、ストレスチェックだけでなく、日常的にストレス対策を行う文化を醸成すること も重要です。例えば、メンタルヘルスに関する研修を実施したり、産業医やカウンセラーとの相談窓口を設置したりすることで、従業員が気軽に相談できる環境を整えることができます。
ストレスチェックは、単なるアンケートではなく、企業文化の一環として取り組むことで、より効果的なものになります。
ストレスチェックに関する法律・義務・罰則
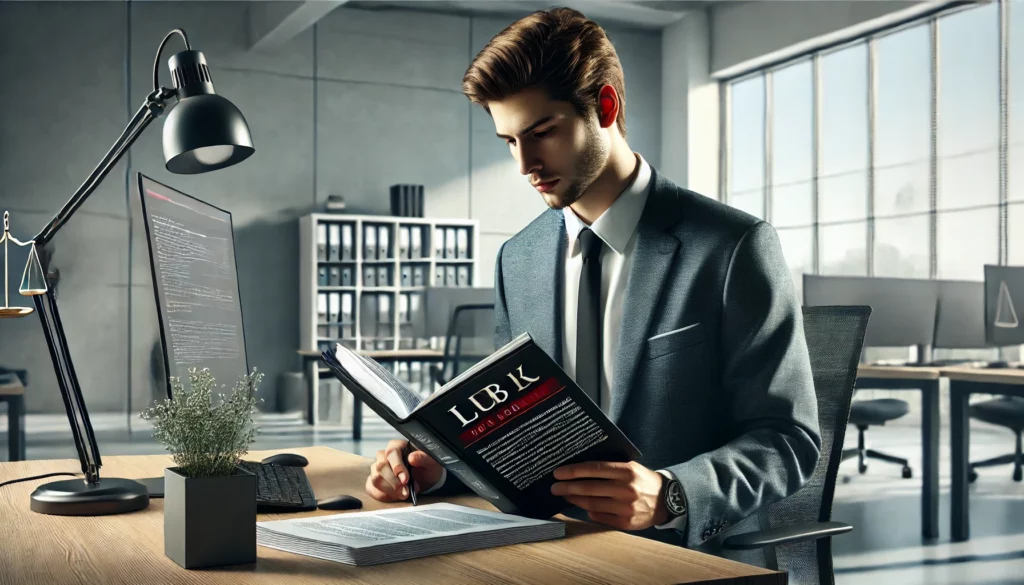
ストレスチェックは、2015年に改正された労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の企業に対して実施が義務付けられています。企業がこの義務を怠ると、罰則が科される可能性があるだけでなく、職場のメンタルヘルス問題が放置されることで、労働災害や訴訟リスクの増加につながることもあります。
また、ストレスチェックの未実施がもたらすリスクは、単に法律違反にとどまりません。メンタルヘルス不調による休職者の増加や、生産性の低下、さらには企業の社会的評価の低下など、多方面に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、企業は法律を遵守するだけでなく、積極的に職場環境の改善に取り組むことが求められます。
労働安全衛生法における義務
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して実施が義務付けられました。これは、労働者のメンタルヘルスを守ることを目的とし、職場におけるストレス要因を特定し、必要な改善措置を講じるためのものです。
企業の義務として、以下のポイントが挙げられます。
- 年に1回以上のストレスチェックを実施すること
- 結果を本人に通知し、ストレスが高いと判定された従業員には医師による面談の機会を設けること
- ストレスチェックの結果をもとに、職場環境の改善を行うこと
- 労働者の同意がない限り、個人のストレスチェック結果を会社が取得しないこと
- 50人未満の事業場は義務ではないが、実施が推奨されている(努力義務)
特に重要なのは、ストレスチェックは「形だけの実施」では不十分 だということです。チェックを行い、結果を従業員に通知するだけではなく、職場のストレス要因を分析し、改善につなげることが企業の責任となります。
また、従業員のストレスレベルが高い場合、希望すれば医師の面談を受けることができますが、企業側はこの面談の申し出を拒否してはなりません。
ストレスチェック未実施のリスク
ストレスチェックを実施しない、または適切に運用しない場合、企業には法律違反のリスクが生じます。労働安全衛生法に違反すると、労働基準監督署による指導が行われ、改善命令が出されることがあります。それでも対応しない場合、企業の責任者が50万円以下の罰金を科される可能性があります。
しかし、罰則以上に深刻なのは、未実施による職場環境の悪化と労働災害の増加 です。ストレスが原因でメンタルヘルス不調を訴える従業員が増えると、以下のようなリスクが高まります。
- 労働災害の認定リスク
ストレスによるうつ病や適応障害が業務に起因すると判断された場合、労働災害として認定され、企業の管理責任が問われる可能性があります。 - 訴訟リスクの増加
従業員が「会社がメンタルヘルス対策を怠った」として訴訟を起こすケースもあります。過去には、ストレスが原因で自殺した従業員の遺族が企業を訴え、高額な損害賠償を命じられた事例もあります。 - 企業の社会的評価の低下
従業員のメンタルヘルスを軽視する企業は、社会的な評価が低下し、求職者や取引先からの信頼を失う可能性があります。健康経営が重視される現代において、労働環境の改善に取り組まない企業は、長期的な競争力を失いかねません。
このように、ストレスチェックを実施しないことは、単なる罰則の問題ではなく、企業全体のリスクマネジメントにも直結するのです。
労働者が知っておくべきポイント
ストレスチェックは企業の義務ですが、労働者自身もこの制度を正しく理解し、活用することが重要です。単にアンケートに回答するだけではなく、自分の健康を守るためにどう活かすかを考えることが求められます。
労働者が知っておくべきポイントとして、以下の点が挙げられます。
- ストレスチェックは「自分のため」のもの
ストレスチェックは、職場の状況を把握し、自分自身の健康を守るための制度です。正直に回答することで、適切なサポートを受けるきっかけになります。 - 結果によって不利益な扱いを受けることはない
ストレスチェックの結果は、本人の同意なしに会社が取得することはできず、これを理由に評価や配置転換に影響を与えることは法律で禁止されています。万が一、結果を理由に不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署や社外の相談窓口に相談することができます。 - 職場の改善に関わる意識を持つ
ストレスチェックは、個人の健康管理だけでなく、職場環境の改善にもつながります。自分自身のストレス要因を把握し、必要な改善策を会社に提案することも、より良い職場づくりにつながります。
ストレスチェックを活用して職場環境を改善しよう
ストレスチェックは、単なる法律上の義務ではなく、職場環境をより良くするための大切なツールです。メンタルヘルスの問題は、個人のパフォーマンスだけでなく、職場全体の生産性や雰囲気にも大きく影響を与えます。ストレスチェックをうまく活用することで、従業員が安心して働ける環境を整え、企業としての成長にもつなげることができるようになるのです。
しかし、ただ実施するだけでは十分ではありません。チェックの結果を分析し、具体的な改善策を講じることで初めて、その効果を発揮します。職場の課題を可視化し、ストレス要因を取り除くことで、より健康的で働きやすい職場へと変えていくことが可能になります。
ストレスチェックは、企業と従業員の両方にとって大きな価値をもたらすものです。適切に活用し、働きやすい職場環境を実現することで、健康で生産性の高い組織を目指しましょう。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る