ストレスチェック義務化で企業に求められること|対象範囲・罰則・制度の全体像を解説
「うちの会社はストレスチェックの義務対象?」「やってないと罰則ってあるの?」そんな疑問や不安を感じている企業担当者は少なくありません。ストレスチェック制度は、2015年に法制化されて以降、企業にとって避けて通れない重要なメンタルヘルス対策の一つとなりました。
しかし、制度の概要や対象範囲、対応方法について正しく理解していないまま運用が後回しになっているケースも散見されます。本記事では、義務化の背景や罰則リスク、実施のステップから外部委託・ツール導入のポイント、そして今後の法改正動向まで、企業が今知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
ストレスチェック義務化の背景と経緯

近年、職場におけるメンタルヘルス対策の必要性は、企業規模や業種を問わず高まっています。特に、うつ病や適応障害といった精神疾患による長期休職や離職が目立つようになり、職場の人員不足や生産性の低下にも直結する深刻な課題となっています。
こうした背景から、企業の自主的な取り組みだけでは従業員の心の健康を守るには限界があると判断され、2015年には、国による予防策として「ストレスチェック制度」が導入されました。
その後も状況は深刻さを増しており、さらに、過重労働やパワーハラスメントなどを背景に、自殺や精神障害に関連する労災の認定件数が年々増加しており、厚生労働省の報告によると、2023年度(令和5年度)の精神障害に関する労災請求件数は3,575件(前年度比+892件)にのぼり、過去最多を更新しています。そのうち自殺(未遂を含む)に関する請求は212件、実際に労災として認定された件数は79件に上ります(出典:厚生労働省「令和5年度 過労死等の労災補償状況」)。
こうした現状を背景に、企業による自主的なメンタルヘルス対策だけでは、従業員の心の健康を守るうえで十分な効果が得られていないと判断されました。 国として予防策を制度として義務化する必要性が高まりました。その流れの中で誕生したのが、「ストレスチェック制度」です。
なぜストレスチェックが義務化されたのか?
先ほども述べたように、ストレスチェック制度の導入に至るまでには、長年にわたり企業のメンタルヘルス対策が自主努力に委ねられてきたという経緯があります。2006年には、厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を発表し、職場でのストレス対策や相談体制の整備を促しました。
しかし、その後も精神疾患に関連する労災や自殺の件数は減少せず、企業による対策の実施状況には大きなばらつきがあることが判明しました。特に中小企業では、体制や知識の不足により、対応が後手に回るケースが多く見られました。
このような背景から、厚生労働省は予防に重点を置いた仕組みとして、ストレスチェック制度を法制化する方針を打ち出し、2014年に労働安全衛生法を改正します。これにより、一定の従業員数を超える事業場に対して、ストレスの状況を客観的に把握するための年1回のチェックを義務付けることが決まりました。
この制度の目的は、単にストレスを測定するだけでなく、職場環境の改善や早期介入によるメンタルヘルス不調の予防にあります。また、面接指導や医師との連携といった具体的な対応にまでつなげる仕組みとなっており、企業の責任がより明確に問われるようになっています。
制度はいつから義務になったのか?
ストレスチェック制度が法的にスタートしたのは2015年12月1日です。この日以降、従業員50人以上の事業場を対象に、年1回のストレスチェックを実施することが義務化されました。
初年度は周知や体制づくりのための準備期間として、制度の運用はやや緩やかでしたが、2016年度からは完全に義務としての運用が開始されました。以後、未実施の企業には是正勧告などの対応が取られるケースもあり、制度は現在に至るまで着実に定着してきています。
ストレスチェックが義務化される対象企業とは?
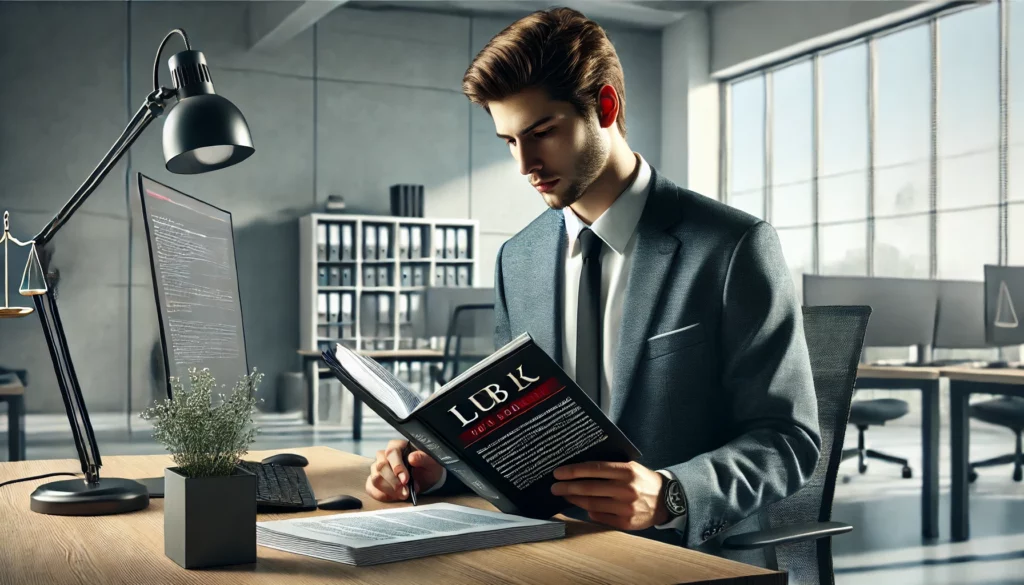
ストレスチェック制度は、すべての企業が対象というわけではありません。法律上、常時50人以上の労働者がいる事業場に対して、その実施が義務づけられています。逆に言えば、50人未満の事業場は義務の対象外となっており、あくまで努力義務として位置づけられています。
しかし、「従業員数50人」のカウントには注意が必要です。対象となるのは、正社員だけでなく契約社員やパートタイム労働者も含まれる場合があるため、制度の趣旨を理解し、正確に労働者数を把握することが重要です。
ここでは、ストレスチェック制度の義務化対象や適用基準、例外について、最新の情報をもとに解説します。
義務の対象は「常時50人以上」の事業場―その背景とは?
ストレスチェック制度が義務づけられているのは、常時50人以上の労働者がいる事業場です。この「50人」という基準は、特別な根拠がある数字というよりも、既存の労働安全衛生法において制度運用の区切りとして用いられてきた基準を踏襲したものです。
たとえば、産業医の選任や衛生委員会の設置といった他の衛生管理義務も、50人以上の事業場を対象にしています。そのため、新たに導入されるストレスチェック制度も、まずはすでに一定の体制が整っている中規模以上の企業を対象にすることで、制度を段階的に定着させていく狙いがあったのです。
加えて注意したいのが、「50人」の数え方です。ここでの「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく契約社員やパートタイム労働者も含まれる場合があります。具体的には、雇用期間の定めがない者や、1年以上継続して雇用されている(またはその見込みがある)短時間労働者もカウント対象となることがあります。
たとえば、週30時間以上勤務する契約社員が多数いる場合、それだけで義務対象になる可能性があるため、単に「正社員数」で判断せず、事業場単位で在籍する全労働者の勤務実態を基に判断することが重要です。
この人数の定義を正しく理解していないと、制度の対象外と誤認して義務を果たさず、結果として行政指導を受けるリスクもあるため、確認とカウントには十分な注意が必要です。
中小企業や50人未満の事業場はどうすべき?今後の義務化に向けた動き
現時点で、50人未満の事業場にはストレスチェックの実施義務はありませんが、厚生労働省では将来的な義務化の方向性も含めて議論が進められています。実際、2024年の厚労省提言では、小規模事業場向けのマニュアル整備や外部委託の推奨など、制度拡大に向けた環境整備が進められています(参照:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」)。
さらに、50人未満の企業であっても、従業員のメンタル不調や離職リスクを未然に防ぐために、自主的にストレスチェックを導入する企業も増加しています。外部の専門機関やツールを活用すれば、コストや運用負担を抑えながら実施することも可能です。
義務かどうかに関わらず、職場のメンタルヘルス対策としてストレスチェックの活用は、企業の持続的な成長に直結するといえるでしょう。
義務を怠るとどうなる?罰則と企業リスク

ストレスチェック制度は、単なる推奨事項ではなく、労働安全衛生法に基づいた法的義務です。対象事業場で実施を怠った場合、企業はさまざまなリスクに直面する可能性があります。法律違反に伴う罰則はもちろん、実務上の支障や従業員との信頼関係の悪化、場合によっては訴訟リスクにまで発展することもあります。
法律違反による罰則と監督署からの是正指導
ストレスチェックの未実施は、労働安全衛生法第66条の10に違反する行為と見なされ、行政からの是正指導や勧告の対象になります。具体的には、労働基準監督署からの報告命令や指導文書の送付、その後の立ち入り調査が行われる可能性もあります。
現時点では、未実施によっていきなり罰金や刑事罰が科されるケースは稀ですが、度重なる指導に従わない場合や虚偽報告を行った場合などには、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金といった制裁措置が適用されることも法律上は定められています。
また、ストレスチェックを実施したにもかかわらず、高ストレス者への医師面接の対応を怠ったり、結果を職場環境の改善に活かさなかったりすることも、行政指導の対象となります。
実務への支障・従業員との信頼低下・訴訟リスクも
法的なペナルティ以上に深刻なのが、企業の信頼やレピュテーションへの影響です。ストレスチェックを怠ることで、社内で「この会社は従業員の健康を軽視している」という印象を与えかねません。とくに、体調不良やメンタル不調によって休職した従業員が発生した場合、適切な対応を怠った証拠として訴訟に発展する可能性もあります。
たとえ制度上の罰則が軽微であっても、こうした訴訟リスクや企業イメージの毀損は、長期的に見て非常に大きな損失をもたらします。
さらに、働き方改革や健康経営に積極的な企業が注目される今の時代において、ストレスチェック制度に取り組んでいないこと自体が、採用活動や取引先からの評価にも影響を与える可能性がある点は見逃せません。
ストレスチェック義務化に向けた企業の対応
ストレスチェック制度は法令で義務づけられている以上、対象企業には実施体制を整え、社内で継続的に運用できる仕組みを構築することが求められます。
導入にあたって何から始めればよいのか迷っている方は、以下の記事も参考にしてみてください。ストレスチェックの導入手順をわかりやすく解説しています。
(参照:ストレスチェック制度の意味と目的|企業が実施すべき方法と注意点
外部委託・ツール導入でストレスチェックをラクに対応する方法

ストレスチェック制度の実施には、専門的な知識や体制が必要です。そのため、社内での運用に不安を感じる企業や人的リソースが限られている中小企業では、外部サービスや専用ツールを活用する方法が現実的かつ効率的な選択肢となります。
コストはかかるものの、制度に則った正確な運用と従業員への信頼性を担保できる点から、多くの企業が外部リソースを活用しています。
外部機関に委託する場合の注意点と選び方
外部委託を検討する際は、まず「厚生労働省が示す要件を満たす実施者かどうか」を確認することが大前提です。たとえば、産業医や保健師、公認心理師などの資格を持つ実施者が在籍しているか、結果の集計や分析、本人通知の手順が法令に準拠しているかをしっかり見極めましょう。
また、データの取扱いやプライバシー保護体制も非常に重要です。匿名性が担保されているか、個人情報の管理が明確かどうかといった点も契約前に必ず確認しておくべきポイントです。
委託業者の中には、制度の導入サポートから実施後の職場改善コンサルティングまでを一括で請け負うところもあり、業務負担を大幅に軽減できます。
ストレスチェックツール導入のメリットと実例紹介
自社運用を前提とする企業にとっては、クラウド型のストレスチェックツールの導入も有力な選択肢です。これらのツールは、オンラインでのチェック実施、集計、分析、結果通知までを一括で行えるため、担当者の負担を最小限に抑えることができます。
たとえば、ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社が提供するクラウド型健康管理サービス「Growbase」は、健康診断結果、ストレスチェック、長時間労働管理など、従業員の健康データを一元的に管理できるシステムです。
さらに、面談管理機能も充実しており、健診事後措置面談や長時間労働による面談対象者への案内メールの一斉配信、面談記録の管理、意見書や紹介状の作成などが可能です。これにより、産業医や保健師との連携がスムーズになり、従業員の健康フォローアップが効率的に行えます。
また、株式会社リロクラブは、福利厚生サービスと連携したストレスチェックを提供しています。同社の「Reloエンゲージメンタルサーベイ」は、従業員の心身のコンディションや組織エンゲージメントを可視化するサービスで、ストレスチェックに加え、エンゲージメントサーベイや従業員のコンディション測定など、多角的な分析が可能です。
これらのサービスを活用することで、企業はストレスチェックの実施と従業員の健康意識向上を同時に推進し、職場環境の改善や生産性向上につなげることが可能です。一方、いずれの場合もツールの機能だけでなく、自社の規模や体制に合った運用が可能かどうかを見極めて導入することが重要です。
今後の法改正・義務範囲の拡大はある?

ストレスチェック制度は、現在「常時50人以上の労働者がいる事業場」に限定して義務化されていますが、今後その対象が広がる可能性が高まっています。とくに、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の遅れが指摘されており、法改正や制度拡張に向けた議論が進行中です。
義務化の対象となっていない企業であっても、制度の今後の動きに目を向け、先手を打った対応が求められる段階に入っています。
小規模事業場への拡大が議論されている背景
厚生労働省や有識者会議の報告では、50人未満の事業場においてもストレスチェックを実施すべきだという提言が繰り返しなされています。特に、2024年以降の検討会では、小規模事業場におけるメンタルヘルス問題の深刻化や、支援体制の格差が課題として挙げられています(参照:厚生労働省「第6回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録」)。
こうした状況を受け、国は段階的な制度拡大を視野に入れ、簡易マニュアルの整備や外部委託の推進など、小規模企業でも実施しやすい環境づくりを進めています。義務化の前段階として、努力義務の強化やインセンティブ制度が導入される可能性も考えられます。
今後の動向と企業が備えるべきこと
制度の義務範囲が広がるかどうかは、今後の政策判断に左右されますが、少なくとも国の姿勢としては「すべての事業場での実施を目指す方向」にあるのは明らかです。そうした流れを踏まえると、まだ義務対象ではない企業でも、今のうちから自主的に制度導入を検討しておくことが賢明です。
特に、中小企業では人的リソースが限られているため、いざ義務化された際に慌てて対応するのではなく、外部委託や簡易ツールの活用で段階的に体制を整えておくことが、リスク管理の面でも重要です。
今後の法改正を“待つ”のではなく、“先回りして備える”姿勢が、企業としての信頼性を高め、従業員との良好な関係づくりにもつながります。
ストレスチェック義務化は「対応力」が問われる
ストレスチェック制度の義務化は、単なる法律上の対応ではなく、企業としてのリスク管理力と組織づくりの姿勢が問われる取り組みです。実施の有無だけでなく、その結果をどのように活かすかが、従業員の健康と企業の信頼を左右します。
特に中小企業にとっては、人員やコスト面での不安もあるかもしれませんが、外部サービスやツールを活用すれば、効率的かつ効果的に制度へ対応する道も十分にあります。今後、制度の対象範囲が拡大される可能性も踏まえると、「義務だから対応する」ではなく、「将来を見据えて主体的に取り組む」姿勢こそが、持続可能な組織運営に欠かせません。
企業の“対応力”が、従業員の安心と生産性を支える大きな鍵になる――それが、ストレスチェック制度が示している本質だと言えるでしょう。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る


