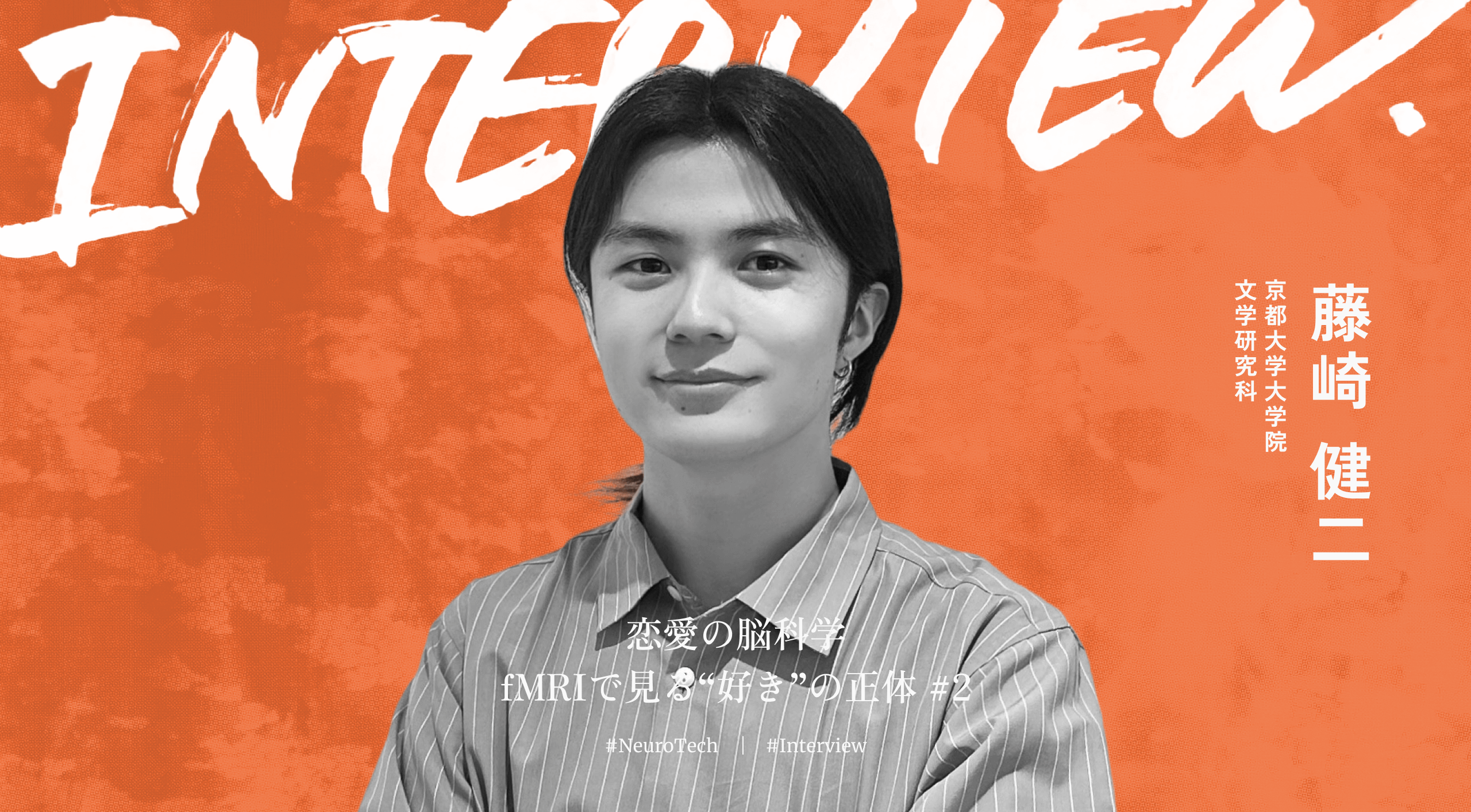「朝、起きられない」は脳のSOS?──現代人の睡眠とメンタルヘルスを見直す
「アラームを何度止めても起きられない」「ベッドから出るのが億劫」──そんな朝のつらさ、誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。けれど、それが毎日続いているなら、単なる「夜型生活」や「気合い不足」では済まないかもしれません。 実は、朝起きられない背景には脳の疲労や睡眠の質の低下、そしてメンタルヘルスの不調が関係していることが近年の研究で明らかになってきました。睡眠不足や慢性的なストレスが、脳内の前頭前皮質(意思決定ややる気を司る領域)の活動を低下させ、朝の起き上がるという行動自体を困難にする可能性があるのです。 なぜ「眠ったはずなのに疲れが取れない」のか 睡眠の質を決めるのは、単なる睡眠時間ではありません。2012年に重要な発見が報告されて以来、その機能が注目されている、脳内の老廃物を排出する「グリンパティック系」と呼ばれる脳の掃除機構は、深いノンレム睡眠の間に活性化することが知られています。 たとえば、2024年に発表された研究では、このグリンパティック系の機能がノルエピネフリンという神経伝達物質によって調整されることが新たに確認されました1。この作用がうまく働かないと、起きた瞬間から脳がどんよりしたままになってしまいます。 また、現代人は就寝直前までスマホを見たり、SNSで刺激を受けたりすることで、交感神経が優位なまま眠りに入ってしまうことも多くあります。その結果、浅い眠りになり、睡眠の回復力が損なわれるのです。 睡眠と脳波について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。 https://mag.viestyle.co.jp/sleep-through-brainwaves/ 脳が「目覚める」ための3つのアクション では、どうすれば「起きられる朝」を取り戻せるのでしょうか? 脳科学と心理学の観点から、すぐに実践できる3つのアクションをご紹介します。 1. 朝日を浴びる 目覚めたらまずカーテンを開け、朝日を浴びましょう。光が目に入ることで、体内時計をつかさどる「視交叉上核」が刺激され、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されるとともに、覚醒に関わる神経系の活動が高まります2。これが自然な目覚めのスイッチになるのです。 2. 起きた直後に軽いストレッチを 寝たまま深呼吸→ゆっくり手足を伸ばす→起き上がって肩回し、といった簡単な動作だけでも、血行を促進し、脳に「活動モードだよ」と伝える効果があります。運動は、気分を高める様々な神経伝達物質(ドーパミンやエンドルフィンなど)の活動に良い影響を与えることが知られており、これが朝の心地よさにもつながります3。 3. やさしい朝習慣を取り入れる たとえば、好きな音楽を流す、温かい飲み物を飲む、アロマを焚くなど、「自分にとって心地よい刺激」を朝に取り入れることで、脳が「今日も頑張ろう」と前向きになれる土台ができます。こうした小さな工夫が、朝の気分を大きく左右します。 「朝起きられない」は、ライフバランスを見直すチャンス 朝起きられない日々が続くのは、生活リズムや働き方そのものが、自分の脳や身体に合っていないサインかもしれません。最近では、「睡眠の質を高めることで心身のバランスを整える」というスリープウェルネスの考え方が広がりつつあります。たとえば、自分の体内時計(クロノタイプ)に合わせた生活リズムの見直しや、働き方の柔軟化がその一例です。 欧州の一部企業では、フレックスタイム制度の活用により、社員が自身の生活リズムに合わせて始業時間を選べるようにしたり、「シエスタ(昼寝)制度」を導入したりするなど、社員の自然なリズムを尊重する動きが出てきています。 日本でも、「睡眠改善を通じて生産性を上げる」ことを目的とした健康経営の取り組みが、徐々に広がりつつあります。自分の脳と身体の声をきちんと聞くこと、それが結果としてパフォーマンス向上にもつながるのです。 おわりに──無理して起きるより、「整えて起きる」を 朝、起きられないとき、「自分はダメだ」と思わずに「もしかしたら脳が休息を必要としているのかも」と一歩立ち止まることも大切です。 脳科学とウェルビーイングの視点から見れば、朝のコンディションは気合いではなく、整える工夫で変えられます。今日の朝がうまくいかなかったとしても、明日の朝を少しだけ気持ちよく迎えるためのヒントは、たくさんあります。 朝の過ごし方を見直すことは、メンタルヘルスとライフバランスを整える第一歩です。少しずつ、自分に合った「整える朝」を探してみてはいかがでしょうか?