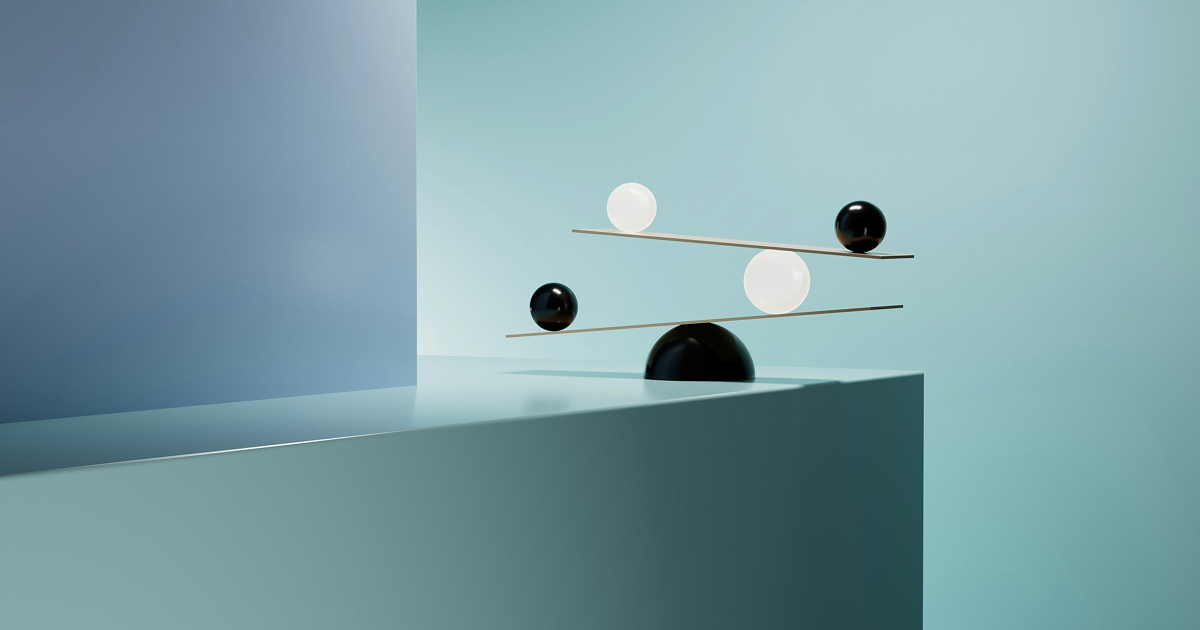ワークライフバランスの成功事例と実現のポイントを徹底解説
働き方改革が進む中、ワークライフバランスの重要性はますます高まっています。しかし、実際にどのように取り組めばよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ワークライフバランスを実現した企業の具体的な事例を厳選してご紹介します。育児支援やリモートワーク制度、副業解禁など、先進的な取り組みから自社に取り入れられるヒントを見つけてみましょう。
ワークライフバランスとは?現代に求められる理由
ワークライフバランスとは、仕事と生活の両方を調和させ、充実させる働き方や生き方です。現代社会では、仕事と私生活の調和=ワークライフバランスの重要性がかつてないほど高まっており、
労働時間だけでなく、働く環境や柔軟性、個人の価値観の多様化に対応した働き方が求められる時代です。
本章では、なぜ今このテーマが注目されているのか、そしてそのバランスが崩れると何が起こるのかをわかりやすく解説します。
なぜ今、ワークライフバランスが重視されているのか
近年、ワークライフバランスへの関心が急速に高まっている背景には、複数の社会的要因が重なっています。
まず、「働き方改革関連法」の施行以降、企業には時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務などが課され、労働環境の見直しが急務となりました。特に近年では男性の育児休業取得促進も重視されており、政府は2030年までに男性の育休取得率を85%に引き上げる目標を掲げています(参照:※厚生労働省「育児・介護休業法について」より)。
参考(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)
また、少子高齢化による人口構造の変化も深刻です。労働人口の減少により、企業は人材の定着・確保が最重要課題となりつつあります。加えて、親の介護や子育てと仕事を両立せざるを得ない“ダブルケア”の世代が増えており、企業にはより柔軟な勤務形態が求められるようになっています。(参照:総務省統計局「人口減少社会、高齢化」)
さらに、テレワークやフレックス制などの柔軟な働き方が浸透したことで、「仕事の成果さえ出せば、場所や時間にとらわれない働き方も可能だ」という認識が広まりました。こうした社会背景の変化によって、企業も従業員も「働き方そのものを見直す」段階に入りつつあるのです。
ワークライフバランスが崩れると起こる問題とは
ワークライフバランスが取れていない状態が続くと、従業員の心身に悪影響を及ぼすリスクが高まります。たとえば、長時間労働による疲弊やメンタルヘルスの悪化、家庭との両立が困難になることで離職につながるケースも少なくありません。また、集中力や生産性の低下にも直結し、企業全体のパフォーマンスにも影響を及ぼすため、組織として早急に対策を講じる必要があります。
ワークライフバランス推進の成功事例まとめ

近年、多くの企業がワークライフバランスの推進に力を入れています。本章では、実際に効果を上げている企業の事例を取り上げ、育児支援、柔軟な働き方、多様性の尊重といった観点から、それぞれの取り組み内容と成果を紹介します。これらの事例から、自社や個人で取り入れられるヒントを探してみましょう。
育児と仕事の両立を支える制度がある企業
育児中の従業員を支援する企業は、柔軟な働き方の実現に積極的に取り組んでいます。
たとえば六花亭製菓では、出産や育児を理由に退職を選ぶ社員が多かったという課題がありました。これを解消するため、社内に保育施設を設置し、園内の保育士と連携しながら、子どもを預けながら働ける環境を整えました。
この取り組みにより、従業員の復職率や定着率は向上し、実際に制度を利用した社員からは「保活のストレスが減った」「働きながら子どもの様子がわかって安心できた」といった声が寄せられています(参照:六花亭製菓「24年間、有給休暇取得率100%の真価」)
ブリヂストンでも、女性社員のキャリア継続を支援するため、0歳児から預けられる保育所を整備し、短時間勤務制度や時差勤務制度を導入しました。こうした制度の活用が広がったことで、女性社員の育児による離職率は大きく下がり、復職率は90%を超えるまでになっています。また、管理職に登用される女性社員も年々増加しており、制度の整備だけでなく、実際に利用しやすい仕組みと職場の理解づくりが進んでいます。(参照:ブリジストン 「福利厚生」)
リモートワークや柔軟な勤務制度を導入した企業
テレワークやフレックスタイム制度など、時間や場所に縛られない働き方を取り入れる企業が増えてきました。パルコでは、新型コロナウイルスの影響を受けてリモート勤務を本格導入し、その後も恒久的な制度として継続しています。通勤時間の削減や生活リズムの安定など、従業員の働きやすさが向上したことで、業務への集中力が高まったという声も多く聞かれています(参照:PALCO「多様な人材を輝かせる」)。
また、日本マイクロソフトでは「週休3日制」のパイロットプログラムを実施しました。この制度では労働時間を減らしながらも、給与は従来通りに設定されており、生産性の向上と従業員満足度の両立が図られています(参照:ZDNET Japan「週休3日制がもたらす影響–短い勤務時間で成果を出す働き方」)。実施後の社内アンケートでは、「私生活の充実が仕事の質にもつながった」「週明けに気持ちの余裕を持てるようになった」といった前向きな声が多数寄せられました。柔軟な働き方を支える制度が、企業と従業員の双方に良い影響をもたらしていることがうかがえます。
多様性や社員の価値観を尊重した企業文化の実現
制度だけでなく、企業文化として多様性を尊重する姿勢を明確にしている企業は、社内外から高く評価されています。
ワコールでは、社員のライフスタイルや価値観に合わせた柔軟な働き方を支えるため、「自己選択型勤務制度」や「短時間正社員制度」を導入しました。これらは、結婚・出産・介護・自己啓発など、ライフステージに応じた多様な働き方を社員自らが選択できる仕組みです。
さらに、社内ではキャリア支援やスキルアップの機会も多く設けられ、社員一人ひとりが「自分らしい働き方」を主体的に築ける土壌が整えられています。利用者からは「会社から理解されていると実感できる」「ライフイベントがあっても働き続けられる安心感がある」といった声が多数寄せられています(参照:ワコール「DE&Iの推進」)。
アイアール株式会社では、社員の声を定期的に集め、制度や運用ルールを改善する「ボトムアップ型マネジメント」を継続的に実施しています。特に注目すべきは、制度導入後の「活用率」に着目している点です。制度の利用率や満足度は導入以前と比べて大幅に向上し、実際に運用されて「使われる制度」へと成長しています(参照:Nihon IR「技術セミナー」)。
同社では制度の内容や使い方について、社内ポータルや説明会などで積極的な情報発信を行っており、新入社員からベテラン社員までが同じ水準で制度を理解・利用できる体制が整っています。こうした文化づくりの結果、エンゲージメントスコアの上昇や離職率の低下といった成果も確認されています。
社員の健康と働きやすさを支える取り組み
ワークライフバランスを整えるうえで、勤務時間や制度の柔軟性だけでなく、社員の健康や心のゆとりにも目を向けることが重要です。
心身ともに健やかであることが、日々のパフォーマンスや長期的な働き続けやすさに直結するため、多くの企業が独自の工夫を取り入れています。
たとえば味の素株式会社では、社員の健康状態を日常的に把握できるアプリを導入し、体調や睡眠、ストレスの状況などをセルフチェックできる仕組みを整えています。加えて、社内には産業医や保健師が常駐し、健康面・精神面での早期フォローが可能な体制を整備。部署ごとに体を動かす機会を設けたり、社食での栄養バランスをサポートしたりするなど、日常的な工夫も行われています(参照:味の素「無理なく続けられるアプリで健康な生活を! 生活改善サポートアプリ「aminoステップ」とは?」)。
また、リクルートホールディングスでは、年に2回、全社員を対象とした「ライフキャリア面談」を実施。日々の業務だけでなく、将来の働き方や生き方について上司と対話する時間を設けることで、自分らしいキャリア形成を考えるきっかけをつくっています。この面談により、「自分の考えや希望を上司と共有しやすくなった」との声も多く、職場の信頼関係づくりにもつながっています。(参照:リクルート「働きやすさ」)
さらに、第一生命ホールディングスでは、社内に専門部署を設けて、心身のケアや生活とのバランスについての社内相談・支援制度を拡充。悩みが起こったときにすぐに頼れる仕組みを整えることで、安心して働き続けられる環境づくりを支えています。社内副業制度など、柔軟な働き方の選択肢を増やす動きもあり、社員の自律的な働き方を後押ししています(参照:第一生命「ワーク・ライフ・マネジメント」)。
こうした取り組みは、社員が心身の負担を抱えにくい環境をつくるだけでなく、組織全体としての安定性や生産性向上にもつながっています。単なる制度整備にとどまらず、「人」を軸に考えた企業の姿勢が、長く働き続けたい職場としての魅力にもつながっています。
ワークライフバランスを実現するための個人的な方法
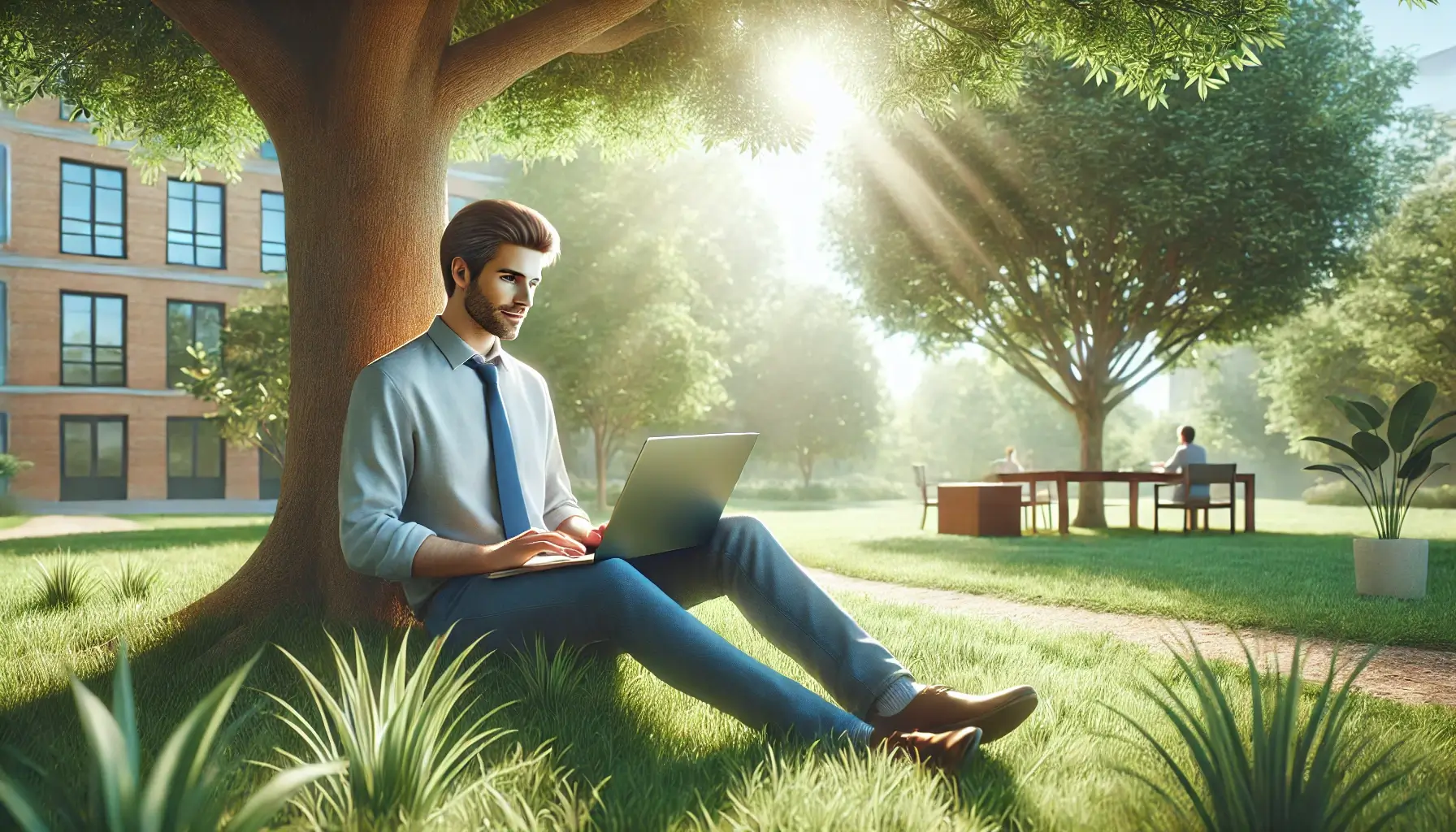
企業の取り組みも大切ですが、個人レベルでもワークライフバランスを整えるための工夫は可能です。本章では、日々の生活や仕事の中で実践できる方法を紹介します。時間の使い方や意識の持ち方を少し変えるだけで、心身の健康や生産性に大きな変化が生まれるかもしれません。今日からできる具体的なアクションに注目してみましょう。
時間管理術を身につける
時間に追われる状態を避け、自分のペースで仕事を進めるには、「可視化」と「優先順位づけ」を意識することが大切です。タスクをToDoリストにまとめたり、ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)を活用したりすることで、集中力を維持しやすくなります。
また、週のはじめに1週間分のスケジュールを見直し、予備時間をあらかじめ確保しておくと、予期せぬトラブルへの対応にも余裕が生まれます。
こうした時間管理の工夫を日常的に取り入れることで、仕事とプライベートの切り替えがしやすくなり、結果として心身の負担軽減やパフォーマンスの向上にもつながります。
オン・オフの切り替えを意識する
ワークライフバランスを乱す原因の一つが、仕事と私生活の境界が曖昧になることです。特にリモートワークでは「常に働いている感覚」になりやすいです。業務終了時には意識的にパソコンを閉じたり、散歩・読書などのリラックスタイムを確保したりすることで、脳と身体を「オフ」に切り替える習慣を持つことが大切です。
こうした切り替えができるようになると、疲労感やストレスが蓄積しにくくなり、私生活もより充実します。オンとオフのメリハリを意識することは、健やかな働き方と生活を両立するための重要なステップです。
自分にとっての「バランス」を明確にする
ワークライフバランスの形は人それぞれ異なります。大切なのは、「自分にとっての理想の生活はどんな状態か?」を明確にすること。仕事・家族・趣味・健康など、優先すべき項目を見直し、今の生活とのギャップを把握することで、無理なく実現に向けた行動が取りやすくなります。定期的なセルフチェックもおすすめです。
まとめ|事例と実践から学ぶ、理想のワークライフバランスとは
ワークライフバランスの実現は、企業の制度だけでなく、個人の意識や行動にも大きく関わっています。今回紹介した企業の事例からは、多様な働き方を支える柔軟な制度と、それを活かす企業文化の重要性が見えてきました。また、個人レベルでも時間管理やオン・オフの切り替えといった工夫により、心身の健康と生産性を両立させることが可能です。
大切なのは「自分に合ったバランス」を知り、それを支える環境を選び、整えていくこと。今後も多様な働き方が広がる中で、自分らしい生き方・働き方を見つけていくために、まずは身近なところから一歩を踏み出してみましょう。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る