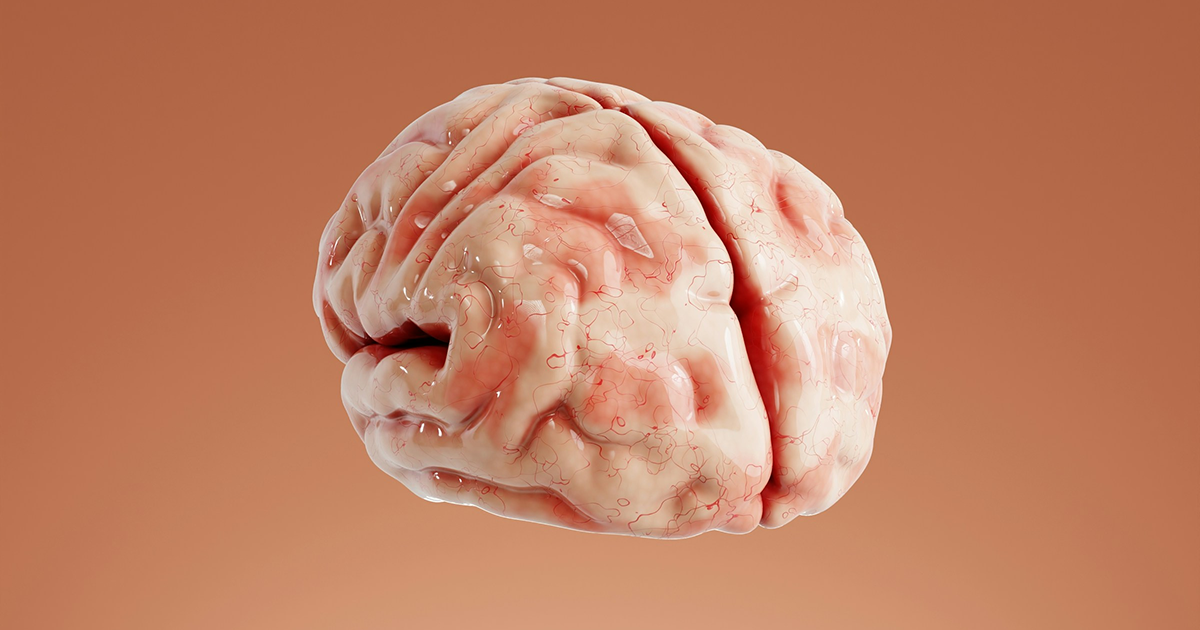大人になってから発達障害に気づくのはどうして?
発達障害は、社会に出てから自分がそうなのではないかと気づき始める人が多いと言われています。子供の頃にはその症状が目立ちにくかったり、周囲に隠されがちだったりするため、早期に自覚することが難しいようです。
では、なぜ子供の頃は、自分が発達障害の症状を持っていることに気づきにくいのでしょうか?
今回も「発達障害」をテーマに、その背景について深掘りしていきます。
前回のコラムはこちらです。
子供の頃は隠されている発達障害
子供の頃に発達障害に気づきにくい大きな理由として、周囲の大人たち、特に母親や担任教師の存在が大きく関係しています。
小学生の頃、忘れ物が多い子供には母親が次の日の準備を手伝ってくれたり、宿題を忘れやすい子供には担任の先生が声をかけてくれたりと、周囲のサポートによって日常生活が成り立つことが少なくありません。そのため、たとえ発達障害の傾向があったとしても、それが表面化しにくくなるのです。
しかし、中学生になると環境は一変します。母親からは「中学生なんだから、自分でしっかりしなさい」と言われ、例えば朝は自力で起きる必要が出てきます。また、小学校のように一日中同じ担任の先生が見守るわけではなく、教科ごとに担当の先生が変わるため、サポートの手が届きにくくなります。
このように、周囲の支援が減り、自立を求められる場面が増えると、生きづらさを感じ始めることが多くなります。そして、その段階で初めて「もしかして自分は発達障害かもしれない」と気づく人が少なくないのです。
発達障害は本当に治療しないといけない病気?
発達障害への対策として、すべてが「治療」を必要とするわけではありません。しかし、本人が困りごとを抱えている場合には対症療法が有効です。治療法は主に薬物療法と非薬物療法に分けられます。
薬物療法では、ASD(自閉スペクトラム症)に精神病薬を使用したり、睡眠リズムを整える薬を処方することがあります。社会性向上が期待されるホルモン「オキシトシン」の投与も新しい選択肢として注目されています※。一方、非薬物療法では音楽療法や認知行動療法、行動療法などが用いられ、特性に合わせた支援を行います。
ただし、治療が必須ではないケースも多く、周囲の支援があるだけで十分に生活できることもあります。ここで重要なのが、発達障害をどう捉えるかです。医学モデルでは「治すべきもの」とされますが、社会モデルでは「社会の仕組みに課題がある」とし、環境整備の必要性を強調します。
発達障害を持つ人が生きやすい社会をつくるには、周囲の柔軟な対応が欠かせません。例えば、忘れ物が多い友人のために充電器を多めに持つなどの小さな工夫で、お互いの関係が円滑になることがあります。このように、多様な特性を受け入れる仕組みを整えることで、誰もが過ごしやすい社会を目指せるのではないでしょうか。
※出典:https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/__icsFiles/afieldfile/2019/07/03/release_20131219.pdf, 2024年12月3日参照
さまざまな人を受け入れる社会作りのために
発達障害の中でも、ASD(自閉スペクトラム症)を持つ人の中には感覚過敏の症状を持つ人がいます。例えば、くすぐりに敏感だったり、少しの音でも反応してしまったりするなど、気が散りやすい特徴が挙げられます。
そのような人たちには、職場で遮音性の高い部屋を用意したり、電気のちらつきやエアコンの音を抑えるなどの環境調整が有効です。このような配慮により、集中力が高まり、パフォーマンスの向上が期待できます。「薬で治してください」と求めるのではなく、特性に合った環境を整えることも重要です。
また、ASDの人は抽象的な言葉を理解しにくい場合があります。例えば、「お風呂見てきて」と言われたとき、湯船の水位を確認するのではなく、お風呂場を見るだけで終わってしまうことがあります。このような特性を持つ人に対しては、職場の上司や同僚が具体的でわかりやすい指示を出すことが大切です。「これをこうしてほしい」と明確に伝えることで、スムーズなコミュニケーションが取れるようになります。
一方、ADHDを持つ人をサポートする方法としては、リマインダーアプリなどの活用が挙げられます。「何時何分にここを出発しよう」といった通知を繰り返し出してくれるアプリは、スケジュール管理が苦手な人にとって大きな助けになります。このような技術を活用し、不得意な部分を補える環境を整えていくことで、より生きやすい社会を築けるのではないでしょうか。
発達障害を持つ人ができる取り組みとして、自分の特性を理解し、「どこまでできるか」「どこからサポートが必要か」を把握することが重要です。例えば、遅刻しがちな人はリマインダーアプリを設定したり、友人に「遅れるかもしれないから連絡してほしい」と頼んだりして工夫を重ねることができます。
一方で、周囲の人も偏見を持たず、当事者の特性を理解しながら協力することが求められます。当事者は自分の症状を理由に開き直らず、周囲の人は一方的な先入観を持たず、お互いに努力し合える関係を築くことが理想です。そのような相互理解と支援が広がれば、誰もが生きやすい社会になるでしょう。
まとめ
今回、大人の発達障害について取り上げました。発達障害は、基本的に小児期にその特性が現れるものです。ただ、子供の頃は母親や担任の先生のサポートによってうまく隠され、生きづらさを感じることが少なかった場合でも、大学生や社会人として自立が求められる段階で困難が表面化し、「大人の発達障害」として認識されるケースが多いと考えられています。
こうした人たちが生きやすくなるための方法として、薬物療法や認知行動療法といった非薬物療法を受ける選択肢があります。しかし、それだけではなく、環境を整える取り組みも重要です。例えば、感覚過敏がある人には音や光の刺激を抑えた環境を用意すること、時間管理や段取りが苦手な人にはスケジュール管理アプリを活用してもらうことなどが効果的です。
発達障害を持つ人が快適に暮らせる社会をつくるためには、当事者に「病気だから治すべき」と一方的に求めるのではなく、周囲もその特性に合わせた環境を整え、支援していくことが大切です。お互いが理解し合い、協力することで、誰もが生きやすい社会を目指していけるのではないでしょうか。
🎙ポッドキャスト番組情報
日常生活の素朴な悩みや疑問を脳科学の視点で解明していく番組です。横丁のようにあらゆるジャンルの疑問を取り上げ、脳科学と組み合わせてゆるっと深掘りしていき、お酒のツマミになるような話を聴くことができます。
- 番組名:ニューロ横丁〜酒のツマミになる脳の話〜
- パーソナリティー:茨木 拓也(VIE 株式会社 最高脳科学責任者)/平野 清花
次回
次回のコラムでは、『発達障害とニューロテクノロジー』に関するお話をご紹介します。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る