働きがい改革とは?組織課題の解決に効く導入メリットと成功の秘訣
「この会社で働き続けたい」と社員に思ってもらえる職場づくりは、今や人事だけの課題ではなく、経営そのもののテーマです。少子高齢化や働き方の多様化が進む中で、従業員の“働きやすさ”だけではなく、“働きがい”が企業の成長を左右する時代になりました。
しかし、働きがいとは何か、どうやって高めるのか──その答えは一つではありません。本記事では、働きがい改革の本質から具体的な施策、企業の成功事例、そして実践ステップまでを網羅的に解説します。あなたの組織にもきっと活かせるヒントが見つかるはずです。
働きがい改革とは?注目される背景と定義
働きがい改革とは、従業員一人ひとりが仕事に価値や意義を感じながら、成長と成果を実感できる環境を整えるための企業改革です。
近年、企業経営において「働きがい」の重要性が高まりを見せています。かつては「働きやすさ」や「生産性」が重視されてきましたが、現在ではそれだけでなく、従業員が自分の仕事に誇りを持ち、内発的なモチベーションを高められる「働きがい」こそが、組織の持続的成長や競争優位の源泉とされています。
この考え方は、従来の評価制度や福利厚生だけでは対応しきれない課題に直面する中で、企業の在り方そのものを見直す動きへとつながっています。つまり、働きがい改革は人事部門にとどまらず、経営戦略の一環として組織全体で取り組むべきテーマといえるのです。
こちらの記事もチェック:
なぜ今「働きがい」が注目されているのか?
この流れの背景には、少子高齢化による人材不足、ミレニアル世代・Z世代を中心とした価値観の多様化、そしてコロナ禍による働き方の急速な変化があります。働く理由や優先順位が「給与」や「安定」だけでなく、「やりがい」や「自己実現」へと変化している中、企業側もその変化に応える形で、人を惹きつけ、つなぎとめるための新たなアプローチが求められているのです。
働きがい改革の定義と基本的な考え方
働きがい改革の根底にあるのは、仕事を通じて人が活き活きと力を発揮し、自律的に成長できる場をいかに提供できるか、という視点です。そのためには、企業のビジョンや理念の浸透、挑戦を後押しするカルチャーの醸成、公平な評価と承認の仕組み、キャリア支援の仕組みなど、多面的な取り組みが必要です。
「人が活きる環境」こそが、企業の未来を左右する時代。働きがい改革は、個の充実と組織の成果を両立させる、新しい働き方の起点となるでしょう。
働き方改革と働きがい改革の違い
「働き方改革」は主に、労働時間の短縮や柔軟な勤務制度の導入など、働く“環境や制度”を整えることにフォーカスした取り組みです。一方で「働きがい改革」は、働く“意義や価値”に焦点を当て、仕事そのものの魅力や内発的なモチベーションを引き出すことを目的としています。
つまり、働き方改革が「外的要因の整備」だとすれば、働きがい改革は「内的要因の充実」ともいえます。両者は対立するものではなく、むしろ相補的な関係にあります。
働きやすい環境の上に、働きがいのある仕事があってこそ、人は本来の力を発揮できるのです。企業が持続的な成長を目指すうえでは、この2つをバランスよく推進していくことが重要です。
働きがい改革が必要な理由と導入メリット

働きがい改革が注目される背景には、社会的・経済的な構造変化と、企業を取り巻く環境の激変があります。これまでの“働きやすさ”や制度的な支援だけでは人が定着せず、パフォーマンスの持続が難しくなっているのが現状です。
だからこそ今、単なる職場環境の整備ではなく、「なぜこの仕事をするのか」「自分の成長と会社の未来がどうつながっているのか」という“意味づけ”を提供できる組織づくりが、企業経営において不可欠になってきています。
少子高齢化・人材不足という背景
国内の労働市場はすでに縮小フェーズに突入しており、生産年齢人口(15~64歳)は1995年のピークを境に減少を続け、2023年時点で約7,400万人まで減少しました。さらに2040年には6,000万人を下回るとの推計もあり、労働力不足は長期的な構造問題となっています。
このような状況では、業種や地域を問わず「人材の取り合い」が激化し、採用難・定着難が深刻化。中途採用市場では1人の人材に対して複数社がオファーを出すケースも珍しくありません。採用単価の上昇、ミスマッチの増加といった課題が表面化する中で、もはや単なる求人広告ではなく、「ここで働きたい」と思われる職場そのものをつくることが、採用戦略以上に重要な“経営課題”となっているのです。
参照:総務省:「生産年齢人口の減少」
モチベーションと定着率を根本から高める
働きがいを感じる職場では、社員が自発的に動き、責任を持って仕事に取り組む姿勢が醸成されます。これにより、単なる業務遂行ではなく、「自分ごと化」された行動が増え、成果にもつながりやすくなります。
また、意欲を持って働ける環境があることで、職場への愛着や信頼感も育まれ、長期的な定着率の向上にも寄与します。とくにエンゲージメントの高い社員は、離職だけでなく“燃え尽き”も防げる点が見逃せません。
企業価値・生産性の向上につながる
働きがい改革は、社員個人の満足度を高めるだけではなく、組織全体の生産性や創造性を押し上げる効果もあります。自律的に動く人材が増えれば、マネジメントの負担も軽減され、スピーディーな意思決定や業務遂行が可能になります。
さらに、「働きがいのある会社」という評価は、採用市場だけでなく、取引先や顧客、投資家などからの信頼にもつながります。これは、無形資産としての企業ブランドを形成するうえで、大きな意味を持ちます。
働きがいを高める5つの要素

働きがいのある職場を実現するには、従業員の内面に働きかける5つの要素――信用、公正、連帯感、尊重、誇り――を職場環境に根付かせることが重要です。ここでは、それぞれの要素が何を意味し、どのような職場の取り組みや状態が対応しているのかを解説します。
1. 信用(Trust)|安心して意見を言える、信頼に満ちた関係性
働きがいを高めるうえで欠かせないのが、「この職場では自分の意見をきちんと受け止めてもらえる」「失敗しても学びとして受け入れられる」と感じられる、信頼に満ちた環境です。
上司や同僚との信頼関係が築かれていることで、従業員は安心して自分らしく働き、本来の力を発揮できます。心理的安全性のある職場風土や、上司からの継続的なサポートとフィードバックは、信頼を生む重要な要素です。
2. 公正(Fairness)|努力が正当に評価され、納得感のある報酬がある
人は、自分の努力や成果が正当に評価されていると感じたときに、大きな満足感とやりがいを得られます。逆に、不透明な評価制度や不公平な扱いがあると、モチベーションは一気に下がってしまいます。
明確な評価基準、オープンな査定プロセス、そして成果に見合った報酬体系は、公正な職場づくりに欠かせません。金銭的な報酬だけでなく、感謝の言葉やキャリア機会の提供も、「認められている」という実感をもたらします。
3. 連帯感(Camaraderie)|仲間と支え合い、つながりを感じられる職場
「一人じゃない」と思えることが、日々の仕事に安心感と力を与えてくれます。職場の仲間と助け合い、互いの努力や存在を認め合える関係性があることで、従業員は自然とポジティブな姿勢で働くことができるのです。
「ありがとう」「助かったよ」といった日常の声かけや、成果を称えるカルチャーが、連帯感を育てます。こうしたつながりが、働きがいの土台となり、離職の防止にもつながります。
4. 尊重(Respect)|多様な働き方や価値観が受け入れられている
働く人々のライフスタイルや価値観が多様化するなか、それぞれの事情や考え方を尊重する姿勢はますます重要になっています。リモートワークやフレックスタイム制度、育児・介護との両立、副業の容認など、柔軟な働き方を選べることは、働きやすさと働きがいの両立に直結します。
さらに、キャリアの希望を伝えられる仕組みや、自律的な成長を支える風土も、個人の尊重を体現する取り組みです。
5. 誇り(Pride)|自分の仕事や会社に価値を感じられる
自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できること、企業の理念に共感し、その一員であることに誇りを持てることは、働きがいの根幹です。企業のビジョンやミッションを現場の仕事と結びつけて伝えることで、従業員は自分の役割の意味を理解しやすくなります。
また、顧客や社会への貢献が見える化されていること、日々の業務に成長や挑戦の機会があることも、「ここで働いていてよかった」と思える原動力となります。
実際に企業が取り組んでいる働きがい改革の事例
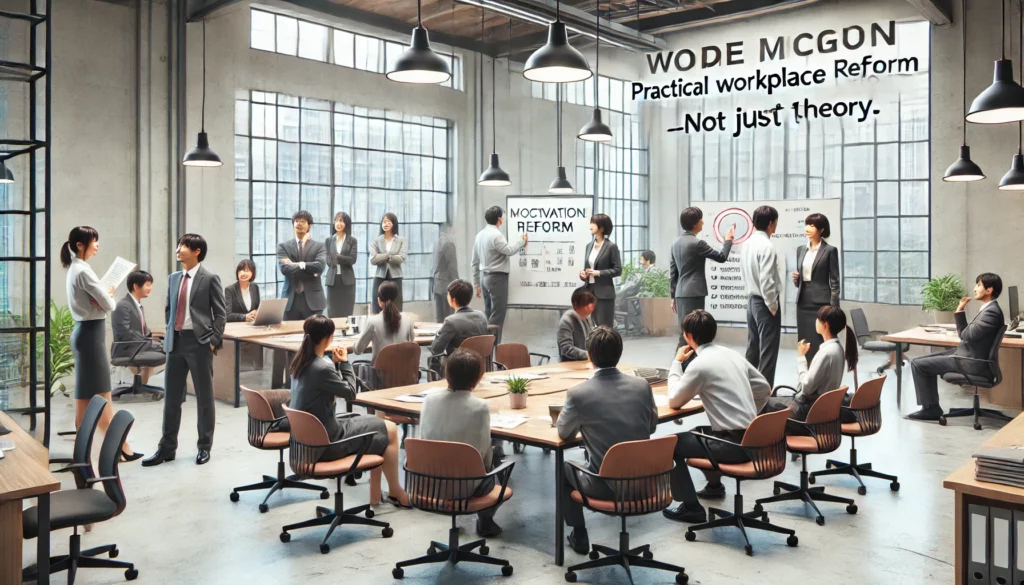
働きがい改革は、抽象的な理想論ではなく、すでに多くの企業が実践している“現場主導の経営戦略”です。規模や業種を問わず、社員のモチベーション向上やエンゲージメント強化を目的に、具体的な制度や文化づくりを推進している企業が増えています。
ここでは、実際に働きがい改革に積極的に取り組む3社の事例を紹介し、それぞれの施策の特徴と成果を紐解いていきます。
【事例1】キリンホールディングス:パーパスを起点にしたキャリア支援と対話文化の推進
キリンホールディングスは、「自然と人を見つめる」パーパスを中核に据え、パーパス経営を推進しています。
社員一人ひとりが自らのキャリアの主体者となる「キャリアオーナーシップ」を掲げ、上司との定期的な1on1など、対話を重視した仕組みを整備。評価や業績と切り離した対話の場を設けることで、心理的安全性を高め、キャリア形成を支援する文化を醸成しています。
こうした取り組みは、社員のエンゲージメント向上や自律的な行動の促進につながっています。
参照:キリンホールディングス「KIRINの「『働きがい』改革」を知る」
【事例2】Unipos:承認の見える化で組織文化を変えるピアボーナス制度
Uniposは、社員同士が「感謝」や「称賛」の気持ちを送り合う「ピアボーナス制度」を開発・導入している企業です。
ポイント付きメッセージを通じて、金銭的報酬よりも“仲間からの承認”を日常的に可視化・共有する仕組みを提供。送受信されたメッセージは全社に公開され、承認の行動が組織全体に広がることで、信頼関係や心理的安全性が高まり、ポジティブな組織文化の醸成につながっています。
参照:Unipos「ピアボーナスとは?失敗事例とデメリット、システムを成功させるコツも紹介」
【事例3】Chatwork:自由な働き方を支えるフルリモートと柔軟な制度
ビジネスチャットを提供するChatworkでは、「時間や場所に縛られない働き方」の実現に向けた取り組みを強化しています。フルリモート勤務の選択や、フレックスタイム制度、副業の解禁など、個人のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を後押ししています。
こうした取り組みにより、従業員が自分らしく働ける環境が整い、生産性の向上と同時に離職率の低下も実現しています。
参照:Chatwork「多様な働き方とは?多様な働き方の種類とメリットを解説」
働きがい改革の進め方と成功の秘訣
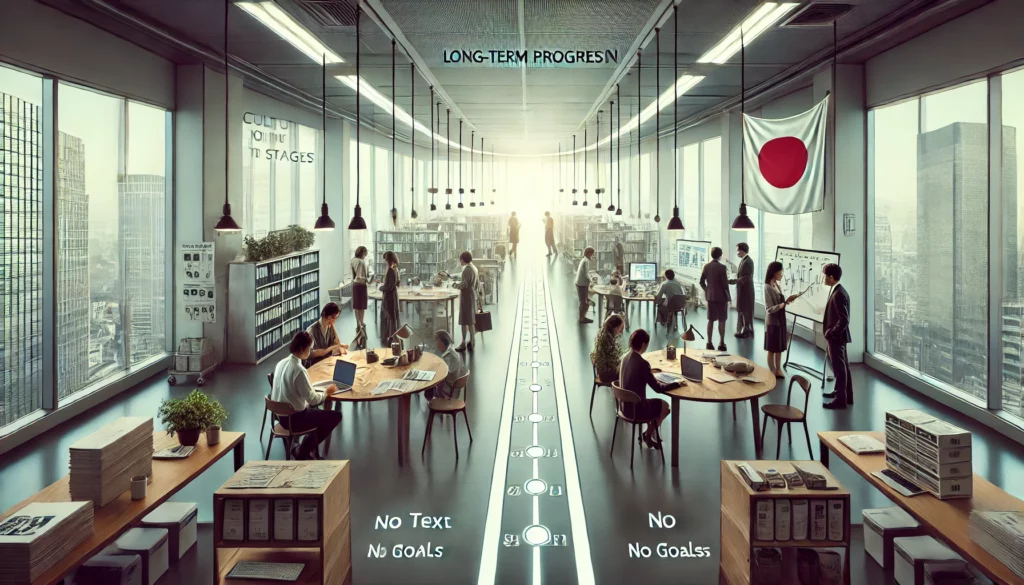
働きがい改革は一朝一夕で成果が出るものではなく、組織の文化や価値観に深く関わる中長期の取り組みです。しかし、正しいステップを踏み、社員と一緒に進めていけば、確実に効果が現れる変革でもあります。
ここでは、実際に多くの企業が採用している「働きがい改革の進め方」を4つのステップに分けて紹介し、よくある失敗を防ぐためのポイントについても触れていきます。
ステップ1:現状把握と課題抽出
まずは、今の自社の「働きがいレベル」がどのような状態にあるのかを把握することが出発点です。サーベイやインタビューを通じて、社員の声を定量・定性の両面から収集し、現場のリアルな声を可視化します。この段階では、“問題を探す”のではなく、“伸びしろを見つける”視点を持つことが重要です。
ステップ2:働きがい要素の見える化
次に、自社にとって重要な「働きがいの構成要素」が何であるかを整理します。たとえば、成長機会、心理的安全性、貢献実感など、前述の7つの要素をベースに、自社独自の価値観と照らし合わせて定義します。これにより、抽象的な「働きがい」を、社員にも伝わる言葉で具体化できます。
ステップ3:施策の設計と小さく始める実践
課題と要素が明確になったら、改善に向けた施策を立案します。いきなり全社展開するのではなく、まずは一部の部署やチームで小さく試す「スモールスタート」が効果的です。たとえば1on1の導入、ピアボーナス制度、フィードバックの強化など、取り組みやすいテーマから始めて成果を積み重ねることで、現場の納得感と再現性が生まれます。
ステップ4:継続のためのフィードバックと改善サイクル
施策は“やって終わり”ではなく、社員からのフィードバックを受け取り、定期的に改善を重ねることが重要です。月次・四半期ごとのアンケートや対話の場を設け、現場でどのような変化が起きているかを確認しましょう。このサイクルを回すことで、働きがい改革が文化として根づいていきます。
失敗しないための注意点と対策
働きがい改革でよく見られる失敗例は以下の通りです。
失敗しないための注意点と対策
働きがい改革でよく見られる失敗例は以下の通りです。
トップダウンすぎる進め方
経営層の意図だけで進められると、現場の当事者意識が生まれず、形だけの改革になってしまいます。社員の声を反映させ、現場との対話を軸にすることが成功のカギです。
施策の形骸化
一度導入した制度が、運用されずに放置されるケースも少なくありません。目的を明確にし、定期的に活用状況を見直すことで、制度の“息切れ”を防ぎましょう。
社員の声が活かされない
意見を集めても反映されなければ、信頼関係を損ねてしまいます。たとえ全ての声に応えられなくても、「聞いている」「改善している」という姿勢を見せることが重要です。
働きがい改革は経営課題の核心

働きがい改革は、単なる人事施策や一時的な取り組みではなく、組織の持続的な成長と競争力を支える「経営の核心」といえるテーマです。少子高齢化、価値観の多様化、働き方の変化――これらの外的変化に対応するためにも、企業は“人を活かす経営”への転換を求められています。
働きがいを高めるということは、社員一人ひとりが自分らしく力を発揮できる土壌をつくること。そして、その結果として得られるのが、高いエンゲージメント、生産性の向上、定着率の改善、さらには企業ブランドの強化です。
改革には時間も対話も必要ですが、小さな一歩からでも確実に前進できます。現場と向き合い、社員の声に耳を傾けながら、組織全体で「働きがいのある職場」を育てていく。その姿勢こそが、これからの時代を生き抜く企業に必要な“経営力”なのです。
今こそ、「働きがい」という視点を経営の中心に据えるとき。目の前の仕事が、組織の未来を変える一歩になるかもしれません。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る


