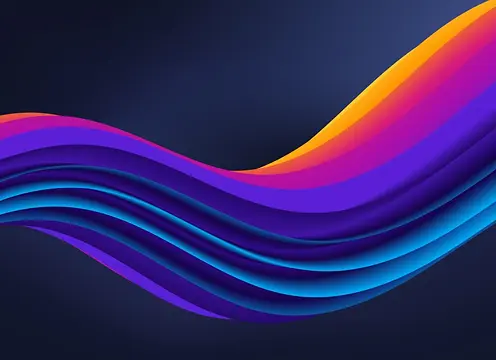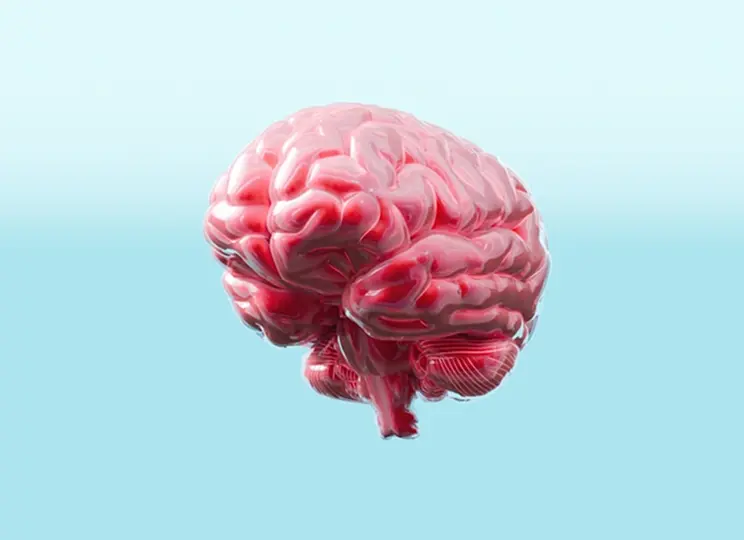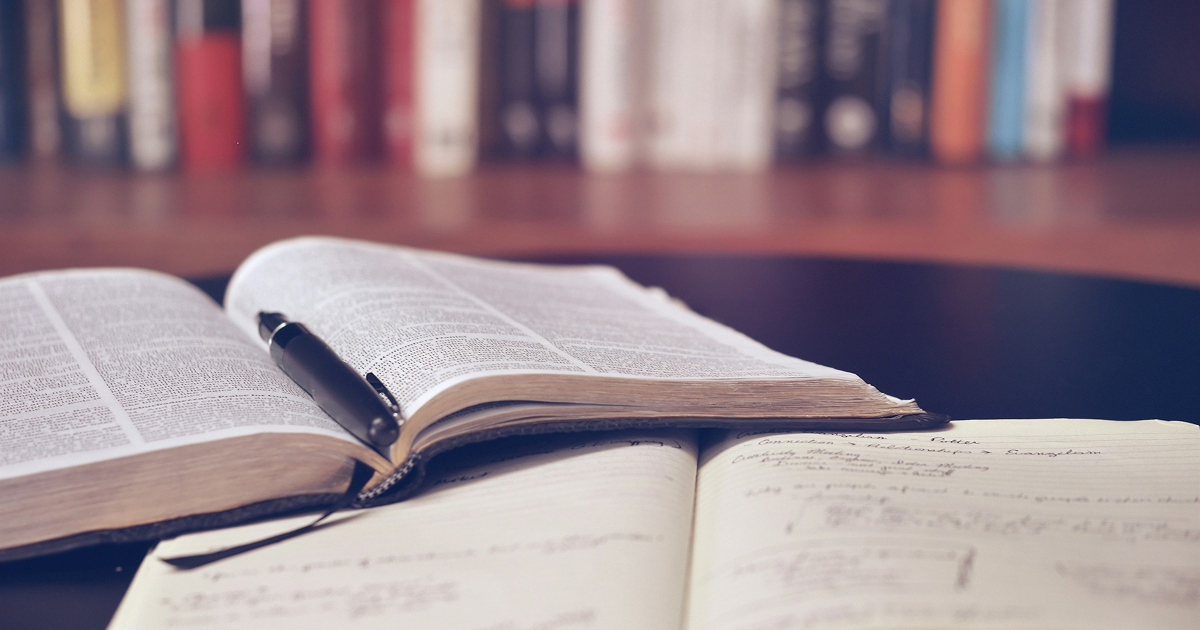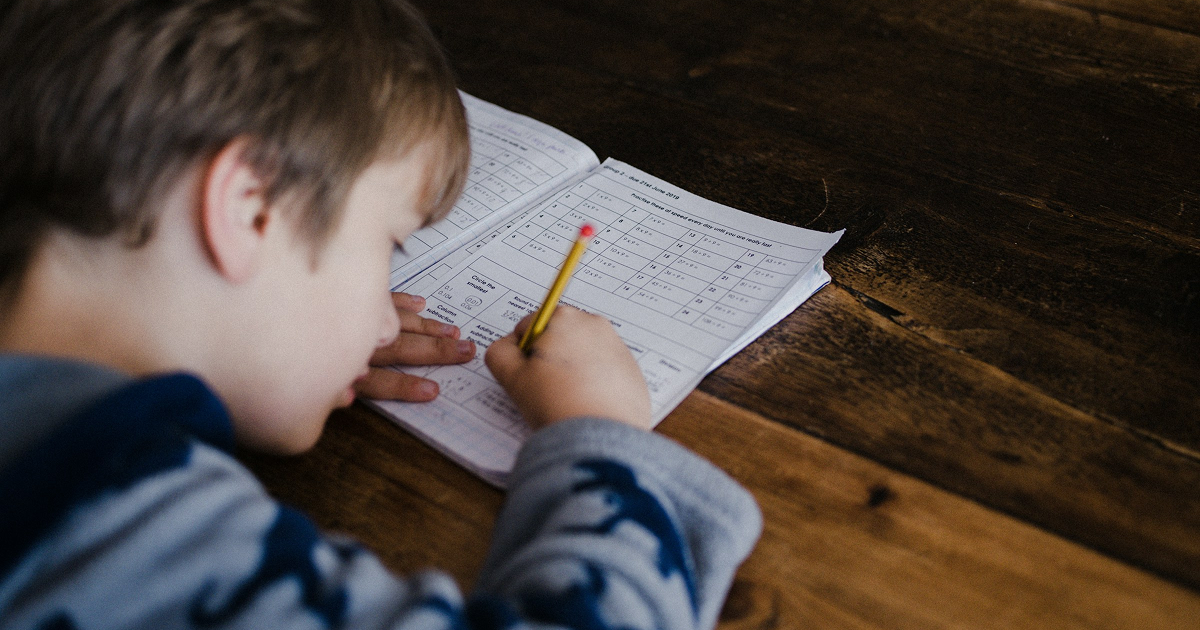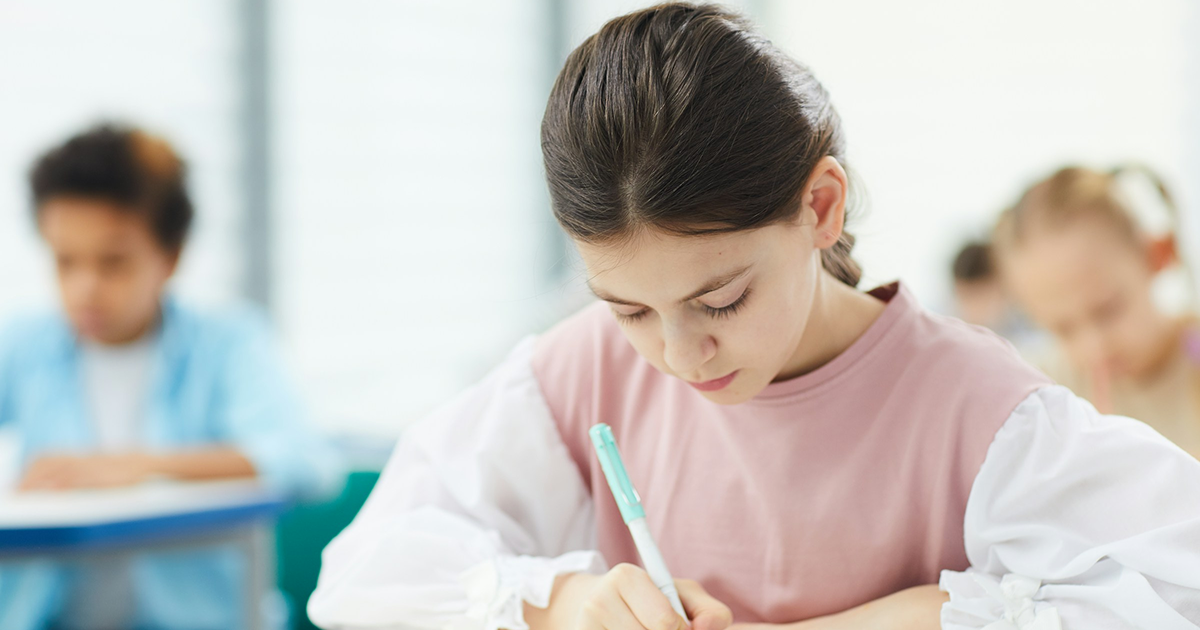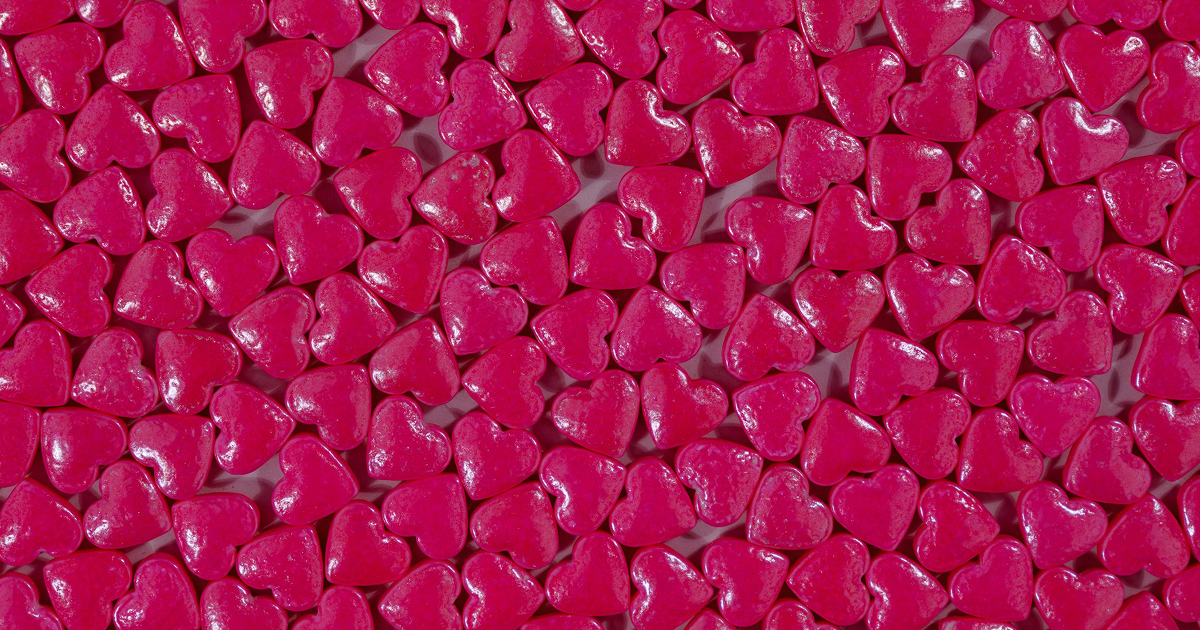ダイエットを長続きさせるための4つのコツ「EAST」/驚くほど痩せる簡単な習慣とは?
ダイエットはすぐに結果が出るものではなく、痩せてなりたい自分になるためには、長い時間がかかります。では、どのようにすれば長期間モチベーションを維持し、ダイエットを継続することができるのでしょうか? 今回は、行動経済学に基づいたダイエットの方法やマインドをご紹介します。 前回のコラムはこちらです。 https://mag.viestyle.co.jp/columm10/ 人間の脳は未来のために頑張ることはできない? 人は将来のために努力をすることが、苦手な生き物だということを証明する実験※があります。「今の自分」という輪と「将来の自分」という輪を紙に描かせてみます。すると「今がよければいい」と考える人は、2つの輪を離して描き、「今の自分は将来の自分と繋がっているんだ」と考える人は、2つの輪を重ねて描く傾向にあるようです。 さらに、前者のように輪を離して描く人ほど、不健康で貯金もしていなくて…という人が多いことがわかっています。 未来のために努力をすることは、人間が本能的に苦手としていることなのです。しかし、これを「脳が得意なことを使って克服していこう」というのが、行動経済学やナッジになります。 行動経済学とは、人間の意思決定や食行動などの日常の営みが、どのようなプロセスで行われているのかを研究し、それに基づいた介入を行うものです。行動経済学において有名なフレームワークのひとつに、ダイエットに役立つ「EAST」と呼ばれるものがあります。 ※出典:Frontiers | Looking Back From the Future: Perspective Taking in Virtual Reality Increases Future Self-Continuity (frontiersin.org), 2024年7月11日参照 脳が得意なことを使ってダイエットを継続させる4つのコツ 「EAST」の1つ目は「Easy=簡単」です。脳はめんどくさがり屋なので、少しでも大変なことがあると、やる気をなくしてしまいます。「Easy」はその解決策として、あらゆることを「デフォルト化」してしまえばいい、という考えです。 例えば、臓器提供の話が例に挙げられます。臓器提供は、チェックリストに印をつけていくのが、とても煩雑な作業であるため、多くの人は同意をしないそうです。しかし、デフォルトで印がついている状態のものを渡し、同意しない場合はチェックを外す仕組みにすると、多くの人はその行為を面倒に思い、臓器提供に同意をするということがわかっています。これを「デフォルトオプション化」と言います。 自分にやらせたいことをデフォルトオプション化してしまえば、頭を使って考える必要がなくなるため、自然に行動に移すことができるのです。 ダイエットの話で言えば、毎日のご飯で何を食べるかを決めていないから、月見バーガーやケンタッキーを食べてしまうけれど、「夜ご飯は絶対にサラダにする」と言うように、食べるものをデフォルト化してしまえば、脳に負担をかけずに健康な食生活を継続できるのではないか、ということです。 「EAST」の2つ目は「Attractive=魅力的」です。脳は、注意を引くようなものでないと、行動を変えることができません。そのため、サラダを例に挙げると、盛り付けを綺麗にすることや、お気に入りのお皿に盛り付けるなどして、サラダを魅力的に見せ、美味しく食べられるようにする、というものです。 「EAST」の3つ目は「Social=社会的」です。人間は、周りの人がどうしているかが気になってしまい、周りの人の行動にとても影響を受けやすい生き物です。それを利用して、ダイエットでは「今日何を食べたか」「どのくらい歩いたか」などを、友達や周りの人と報告し合うことにより、人の力を借りて痩せられるのではないか、というものになります。 「EAST」の4つ目は「Timely=時間」です。人間はいつでも習慣を変えられるわけではなく、変えやすいタイミングがあることがわかっています。 例えば、中東では糖尿病や肥満が多いことが問題になっています。そこで「ダイエットをしなさい」と言われても、すぐに食生活を改善することは難しいのですが、ラマダン(断食)の時期に食事の介入をすると、食生活を変え易くなるそうです。 ダイエットに金銭的な報酬は効果なし!?驚くほど痩せる簡単な習慣とは? ダイエットを長続きさせるためには、悪い習慣を良い習慣に変えていくことが大切です。「痩せたら1万円あげる」と言うような金銭的な報酬は、ダイエットにはあまり効果がないとされています。反対に「短期的に変わる指標」「KPI的な指標」は、ダイエットの報酬として、効果的であると考えられています。 例えば、「食品を選ぶときにカロリーチェックをしたか」「糖分の含まれている飲み物は飲まなかったか」「夕食を18時までに食べ終えたか」と言うように、複数の簡単な指標を作り、もし失敗したら「どうしたら改善できるか」というセルフチェックを習慣にすることで、驚くほど痩せていく、という研究事例があります。 まとめ ダイエットは体重などの数値に囚われてしまいがちです。しかし、体重はあくまで、ダイエットを行なった結果であり、「間食をしなかった」「一駅分歩いた」というような痩せるまでの過程に目を向けていくことが、ダイエットの長続きのコツでもあります。 そもそも私たちの脳は、ダイエットのような長期的な行動を苦手とします。反対に、脳が得意なことを使って、食生活や運動生活を変えていくことができれば、ダイエットを成功させることができるかもしれません。 🎙ポッドキャスト番組情報 日常生活の素朴な悩みや疑問を脳科学の視点で解明していく番組です。横丁のようにあらゆるジャンルの疑問を取り上げ、脳科学と組み合わせてゆるっと深掘りしていき、お酒のツマミになるような話を聴くことができます。 番組名:ニューロ横丁〜酒のツマミになる脳の話〜 パーソナリティー:茨木 拓也(VIE 株式会社 最高脳科学責任者)/平野 清花 https://open.spotify.com/episode/3EwVd7FIlgssCQc2p5Nwiz?si=VMPMbTW3RcCGKdpeTSmggA 次回 次回のコラムでは、ニューロテクノロジーを利用した『ダイエットに効果がある最新技術』をご紹介します。 https://mag.viestyle.co.jp/columm12/