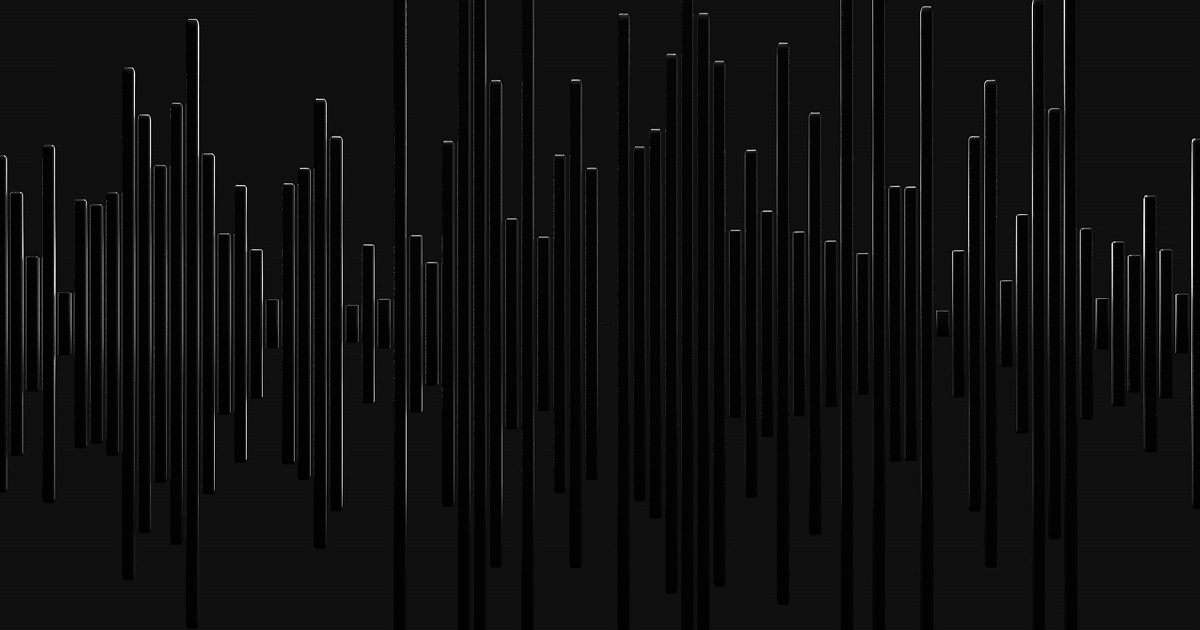心理的安全性を高める職場づくり|企業の取り組み事例10選を紹介
「安心して話せる」「間違いや反対意見を言っても否定されない」――そんな職場の空気が、チームの力を最大限に引き出す鍵になると言われています。注目を集める「心理的安全性」は、単なる理念ではなく、日々の行動や制度設計によって育まれる文化です。 本記事では、実際に心理的安全性の向上に取り組み、成果をあげている企業の具体的な事例を10社分紹介します。上司の関わり方、評価制度、対話の場づくりなど、今すぐ実践できるヒントを豊富にまとめました。 自社の組織づくりに取り入れられる工夫が、きっと見つかるはずです。 心理的安全性とは?職場に求められる「安心して話せる環境」 職場のチームワークや生産性を高めるうえで、近年多くの企業が注目しているのが「心理的安全性」です。マネジメントや組織開発の分野でも取り上げられる機会が増えており、持続可能で健全な職場づくりには欠かせない概念となりつつあります。 この章では、「心理的安全性とは何か?」という基本から、その重要性、組織にもたらす効果までをわかりやすく紹介します。 心理的安全性の定義と注目されている背景 「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、自分の意見や気持ちを安心して表現できる職場の状態を意味します。1999年にハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱し、近年ではGoogleの大規模な社内調査「プロジェクト・アリストテレス」によって、その重要性が広く知られるようになりました。 プロジェクト・アリストテレスでは、「成果を出すチームに共通する要素は何か?」を分析し、その結果、最も重要なのが「心理的安全性」であると結論づけられました。どれだけ優秀なメンバーが揃っていても、発言しにくい雰囲気の中では、創造性やチームワークが十分に発揮されないことが分かったのです。 心理的安全性が高いチームでは、メンバーが失敗を恐れずに意見を出し合い、互いを尊重する文化が根付いています。そうした関係性があるからこそ、情報共有やアイデアの発信が活発になり、チームの成長にもつながっていきます。 心理的安全性がもたらす3つのメリット 心理的安全性が高い職場には、次のようなメリットがあります。 離職率の低下:安心して働ける職場では、人が辞めにくくなります 創造性・イノベーションの向上:自由な発言が、新しいアイデアのきっかけになります エンゲージメントの向上:信頼関係が深まり、仕事への意欲や自発性が高まります これらのメリットだけでなく、「心理的安全性」そのものについてさらに深く理解したい方は、こちらの記事も参考にしてみてください:👉 心理的安全性を高める4つの因子とその実践方法 心理的安全性を高める企業の取り組み事例10選 心理的安全性を高める取り組みは、業種や企業規模を問わず注目されています。ここでは、実際に社内文化の改善やチームの活性化に成功した企業の事例を紹介します。どの事例も、大小さまざまな組織で再現可能なヒントに満ちています。 1. カヤック|評価の「見える化」とフィードバック文化の定着 カヤックでは、全社員の360度評価を社内で完全公開するというユニークな制度を導入しています。360度評価とは、上司だけでなく同僚や部下など、さまざまな立場の人から意見をもらう多面的な評価手法で、個人の強みや課題をより客観的に把握することができます。 同社では、半期ごとの自己評価に対して、同職種の社員がコメントをつける仕組みで、過去の記録も全社員が閲覧可能です。これにより、誰がどのように評価されているかをオープンに共有し、透明性と信頼感を育んでいます。 また、社員同士が毎月ランダムにマッチングされ、良い点(スマイル)と改善点(コブシ)をコメントし合う取り組みも実施しており、直接の業務を知らない相手とのやりとりでも、公開されている評価を参考にフィードバックを行います。 「書かないこと」が最もネガティブに捉えられる文化の中で、社員は率直な意見を歓迎し、対話を通じて互いの成長を支える風土が根づいています。 参考:リクルートマネジメントソリューションズ 特集「組織の成果や学びにつながる心理的安全性のあり方」 2. メルカリ|ピアボーナス「mertip」で感謝が飛び交う職場に メルカリでは、社員同士がリアルタイムで感謝や賞賛を贈り合えるピアボーナス制度「mertip(メルチップ)」を導入しています。この制度はSlackや専用Webフォームを通じて簡単に贈ることができ、感謝の気持ちとともに少額のインセンティブも付与される仕組みです。 もともと社内には、Thanksカードを贈る「All for One賞」という文化がありましたが、mertipにより拠点や部署を超えた日常的・即時的なコミュニケーションがさらに活性化し、導入後の社内アンケートでは満足度87%と高い評価を得ています。 社員からは「感謝が見える形になったことで、他部署との連携がしやすくなった」「お互いに見てもらえていると実感できる」という声もあり、心理的安全性の土台となる信頼と相互理解の強化に大きく貢献しています。 参考:mercan 公式HP「贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。」 3. ねぎしフードサービス|店舗同士のつながりと1on1で信頼関係を構築 飲食店「牛たん とろろ 麦めし ねぎし」を展開するねぎしフードサービスでは、過去に起きた“店舗に従業員が誰も出社しない”という出来事を機に、企業ビジョンを売上重視から「人中心の永続性」へと転換しました。 この方針転換以降、同社は従業員との信頼関係を深めるためのさまざまな取り組みを実施しています。たとえば、同地域内に似た形態の店舗を複数出店することで、店舗間の交流を活発化させました。また、アルバイトを含めた定期的なミーティングでは、立場に関係なく発言しやすい場づくりが徹底されています。 さらに、独自の人材育成プログラム「100ステッププログラム」や、店長とスタッフの月1回の1on1ミーティングを通して、個人の成長や課題を丁寧にサポートし、多様な人材が安心して働けるよう、外国人アルバイト向けの研修制度も整備されています。 こうした施策の積み重ねにより、従業員満足度は65%から85%に大きく向上しました。 参考:ねぎしフードサービス 公式Youtube「100年企業への人財共育と風土づくり|牛たん とろろ 麦めし ねぎし」 4. 三菱電機モビリティ|自分たちから始める対話型の風土改革 三菱電機モビリティ株式会社では、設立当初から心理的安全性の向上を重視し、全社員が主体となって取り組む風土改革を推進しています。 同社が掲げるテーマは「自分たちから始める風土改革」。その実現に向けて、役職や部門を越えて対話を行う全社参加型ワークショップ「変革フェスティバル」を開催しています。この場では、社員一人ひとりが自身の「ありたい姿」を言語化し、本音で意見を交わすことで、現場ごとの心理的安全性に関する課題も自然と浮き彫りになっています。 こうした取り組みにより、「対話する文化」が少しずつ根づき始めており、社員が変革を“自分ごと”としてとらえる意識が社内に広がっています。 この活動は、心理的安全性AWARD2024にも選出されるなど、社外からも高く評価されています。 参考:三菱電機モビリティ株式会社 プレスリリース「「心理的安全性AWARD2024」において最高評価の「PLATINUM RINGを受賞」 5. ZOZOテクノロジーズ|情報の“見える化”でデジタル心理的安全性 ZOZOグループの技術部門を担うZOZOテクノロジーズでは、心理的安全性を“イノベーションの前提条件”と位置づけ、デジタル環境下での信頼構築に本格的に取り組んでいます。 以前は、Slack上にプライベートチャンネルやDMが乱立し、情報の流れが不透明になっていたことから、社員同士の助け合いや本音の発信がしづらい状況が続いていました。そこで、まず着手したのが情報のオープン化と構造化です。 SlackのプライベートチャンネルとDMの原則禁止、チャンネルの命名ルール制定、月1回の「棚卸しデー」の導入により、誰がどこで何を話しているかが見える状態を整備しました。また、経営会議の議事録も原則公開とし、トップ自らオープンな姿勢を示すことで、全社的な信頼醸成につなげています。 参考:BUSINESS INSIDER「DM禁止、原則オープン、ZOZOテクノロジーズが「デジタル心理的安全性」のためにやったこと」 6. 電通総研|全社と現場の両軸で築く心理的安全性の土台 電通総研では、心理的安全性を育むために、全社と部署の両面から取り組みを進めています。同性・事実婚パートナーを配偶者として認める制度や、多様な働き方を支援する仕組み、心身の健康を支える施策などを通じて、エンゲージメント向上の土台づくりを強化しています。 現場レベルでは、人と組織に関するサービスを担うHCM(Human Capital Management)事業部が中心となり、部署横断チーム「WST」を結成しました。WSTでは、社員アンケートをもとに、「縦割りの関係」や「相互理解の不足」などの課題を洗い出し、趣味をテーマにした投稿「タグトーーク!」、懇親会、新入社員紹介動画などの取り組みを実施しました。 こうした活動が社内外で評価され、OpenWork「若手社員がおすすめする企業ランキング」1位(2024年)にも選出されました。 参考:電通総研 人事ソリューションサイト「事例から学ぶ「風通しのいい職場」の条件と心理的安全性」 7. 三井住友海上火災保険|柔軟で対話の多い働き方 三井住友海上火災保険のCXマーケティング戦略部では、従来のように順を追って計画通りに進める仕事の進め方から、チームで話し合いながら柔軟に進行できる新しいスタイルへと切り替えました。社外の研修を通じてその考え方を学んだことで、企画・データ分析・実行・改善の流れが大幅にスピードアップし、従来3か月以上かかっていた施策が、1か月以内で実現できるようになりました。 日々の業務では、朝の短いミーティングで全員が進捗や悩みを共有し合っています。これにより、職種や立場を超えて声をかけ合う機会が増え、誰でも自由に意見を言いやすい空気が生まれました。以前は会話が少なく孤独を感じることもありましたが、今では自然と助け合う場面が増え、チームの一体感が高まっています。 こうした変化を通じて、心理的安全性が高まったと多くのメンバーが実感しています。 参考:scrumic.japan HP「三井住友海上火災様 セミナー受講インタビュー」 8. LIFULL|対話を促す仕組みで心理的安全性を向上 株式会社LIFULLでは、社員が安心して意見や感情を表現できる心理的安全性の確保を重視しています。全社ガイドラインで「敬意をもって意志を伝え、決定には全力を尽くす」と明文化し、率直な対話を前提とした組織文化の浸透を図っています。 現場レベルでは、1on1ミーティングの定期実施や「コミュニケーションデイ」の設定により、チーム内での対話機会を確保しています。また、チームビルディングやオンボーディング施策も工夫されており、新入社員が早期に安心して働ける環境づくりがおこなわれています。さらに、社員一人あたりに設定されたコミュニケーション予算を活用し、会食やイベントによる交流も活性化しています。 部門を越えた関係性を築くために、サークル活動支援やピザパーティ、バースデーパーティの開催といった施策も実施し、こうした制度と風土の両輪により、社員同士の相互理解が深まり、自然と心理的安全性が高まる職場が実現されています。 参考:LIFULL HP「チームへの投資」 9. NTTコミュニケーションズ|全社横断の対話型アプローチ NTTコミュニケーションズでは、NTTドコモ、NTTコムウェアとのグループ再編に伴う組織変化を背景に、社員のエンゲージメントスコアが低下傾向にあることに危機感を抱き、2023年秋から「Go Together Next Stage」を掲げた組織開発プロジェクトを始動しました。150名以上の社員で構成された「組織開発ワーキンググループ(WG)」が中心となり、透明性、つながり、対話、挑戦、価値観の共有といった5つの目標を掲げ、心理的安全性を軸とした職場づくりに取り組んでいます。 初期段階では、役員によるセミナーや組織長向けのワークショップを通じて、心理的安全性の理解促進とアクション宣言を実施し、その後、部門単位でワークショップを展開し、現場レベルでの具体的な行動計画に落とし込んでいます。 また、有志社員が中心となって進める「ワクワクプロジェクト」や、マネジャー層向けの研修「Manager Meetup」など、上下の垣根を越えた対話の機会も増加し、今後は、社員一人ひとりの行動に結びつくハンドブックの作成や、ツール活用による職場づくりを通じて、心理的安全性をより深く組織に根づかせていく方針です。 参考:docomo business HP「NTT Com流組織開発~全社横断の組織づくりの本質に迫る!第2回「心理的安全性で変わる職場 NTT Com流組織開発の歩みとは?」」 10. トリプルバリュー|全員が挑戦しやすい職場づくり 株式会社トリプルバリューでは、社員一人ひとりが安心して意見を伝え、互いに尊重し合いながら挑戦できる職場環境づくりに取り組んでいます。その姿勢が高く評価され、2024年の「心理的安全性AWARD」において、最上位のゴールドリング賞を受賞しました。 同社では、自社開発のエンゲージメントカードや社内イベントを通じて、自由に話し合える空気づくりを推進しています。また、育児中のパート社員が働きやすいよう、出勤日数や時間を自由に選べる柔軟な勤務制度を整備し、互いに助け合える働き方を実現しています。 さらに、役割に応じて「Chief Flower Officer(オフィスの花を管理・演出する責任者)」などユニークな肩書きを設定し、個人の強みを活かして活躍できる機会を提供しており、こうした数々の取り組みにより、社内では自発的に新しいプロジェクトが次々と立ち上がり、心理的安全性の高い風土が企業の成長エンジンとして機能しています。 参考:トリプルバリュー HP「心理的安全性の高い場づくりに取り組むチームを讃える「心理的安全性AWARD2024」にて、トリプルバリューがゴールドリングを受賞」 事例から見える心理的安全性を高める共通の工夫とは ここでは、これまでに紹介した事例をもとに、特に多くの組織に共通していた実践ポイントを4つに整理して紹介します。 共通ポイント1:上司の関わり方が空気をつくる 多くの企業が、上司の「聴く力」や「対話の姿勢」の重要性を認識し、マネジメント層への研修や働きかけを行っています。たとえば、三井住友海上火災保険では傾聴スキルの強化を通じて、相談しやすい関係性を築きました。NTTコミュニケーションズでは、幹部や組織長による心理的安全性に関するアクション宣言が、現場の対話文化を後押ししています。 このように、上司が対話の姿勢を示すことは、職場全体の心理的安全性の土台づくりにつながります。 共通ポイント2:定期的な1on1・チーム対話の「場」を設ける LIFULLやねぎしフードサービスのように、定期的な1on1やチームでのコミュニケーションデイを設けている事例も多数見られました。短時間でも顔を合わせて話す時間を持つことで、日常の悩みや違和感を共有しやすくなり、安心して働ける空気感が醸成されています。 このように、日常的な対話の機会を仕組みとして取り入れることが、関係性の強化に直結しています。 共通ポイント3:評価制度に「安心して話す」行動を組み込む カヤックのように、360度評価を全社員に公開する制度を導入している企業では、「本音で話すこと」そのものが組織にとっての価値として明確に位置づけられています。また、三菱電機モビリティのように、対話の質そのものを風土改善のKPIと捉える動きも見られました。 このように、評価制度に対話の視点を組み込むことで、安心して発言できる文化が根づきやすくなります。 共通ポイント4:「可視化」や「感謝」を通じて心理的障壁を取り除く Slackチャンネルの見える化(ZOZOテクノロジーズ)やピアボーナス制度(メルカリ、Chatwork)のように、行動や感謝の気持ちを「見える化」する仕組みも心理的安全性の向上に寄与しています。Uniposのような仕組みを通じて「ありがとう」が飛び交う職場では、信頼とつながりが自然と育まれます。 このように、目に見えるかたちで感謝や貢献を共有することが、心理的な壁を和らげる鍵になります。 心理的安全性の取り組みを自社で始めるには? 心理的安全性の取り組みを始めるには、いきなり全社的な改革に着手するのではなく、小さな一歩から始めることが成功のカギです。ここでは、取り組みを自社でスタートするための基本ステップを3つご紹介します。 まずは小さなチームから始めてみる 最初から全社での導入を目指すよりも、3〜5人ほどの少人数チームや一部門単位での導入が現実的です。たとえば、週1回「10分間の1on1ミーティング」を設けて、上司が部下に「最近どう?」と気軽に声をかけるだけでも、安心して話せる雰囲気づくりが始まります。 また、「週に1回、30分の雑談ランチを設定」「朝礼でありがとうを一言伝える時間を作る」など、業務の中で無理なくできる工夫から試してみましょう。小さな成功体験が積み重なれば、他のチームへの波及も自然と起こります。 導入目的を明確にし、施策をカスタマイズ 施策を考える前に、「なぜ取り組むのか」を明確にすることが重要です。たとえば「メンバーの発言量が少ない」「離職が続いている」「部署間の壁が厚い」といった課題があるなら、それに合った施策を設計する必要があります。 具体的には、発言しやすい雰囲気を作りたい場合は「ファシリテーション研修」や「発言しやすい会議ルールの整備」、信頼関係を深めたいなら「月1のチームビルディング」「シャッフルランチ」などが有効です。会社に合ったちょうどよい方法を見つけて、小さく試しながら柔軟に見直していくのがポイントです。 効果測定の仕組みもセットで考える 施策をやりっぱなしにせず、「現場で実感されているか?」を確認する仕組みも大切です。たとえば、施策の前後に3問程度の簡易アンケート(例:「自分の意見を言いやすくなったと思う」「上司に相談しやすいと感じる」など)を実施したり、1on1のあとに「今日の話しやすさはどうだった?」と3段階でフィードバックをもらう方法があります。 無料で使えるGoogleフォームや社内チャット(Slack、Teams)で手軽に実施できるため、初期コストはほとんどかかりません。アンケート結果をもとに、必要があれば微調整しながら続けていくことで、現場の信頼感と取り組みへの納得感も高まります。 誰でも実践できる、心理的安全な職場づくり 心理的安全性のある職場は、特別なリーダーシップや大規模な制度改革がなければ実現できない、というものではありません。多くの成功事例が示すように、誰もが実践できる工夫の積み重ねが、安心して話せる空気を育てていきます。 上司の聴く姿勢、日常的な1on1、フィードバックの可視化、小さな「ありがとう」の言葉――これらは、どんな組織でも今日から取り入れられる行動ばかりです。 大切なのは、小さく始めて、継続しながら改善していくこと。心理的安全性は、「文化」として育てることで、チームにも事業にも確かな変化をもたらします。