ウェルビーイング経営が企業成長を後押しする理由|導入メリット・戦略・成功事例を解説
「従業員の幸せが、企業の成長を本当に後押しするのだろうか?」多くの経営者や人事担当者が抱えるこの問いに、現代の経営学は明確な「イエス」を提示し始めています。心身ともに健康で、働きがいを感じられる従業員は、生産性や創造性が向上し、結果として企業全体の競争力強化に不可欠な存在です。特に、コロナ禍を経て働き方が大きく変化した今、ウェルビーイングの実現は、企業にとって避けて通れない重要な経営テーマとなっています。
この記事では、ウェルビーイング経営がなぜ企業成長に不可欠なのか、その本質的な理由と具体的なビジネスメリット、そして導入・推進のための戦略的アプローチを、先進企業の事例を交えながら解説します。
ウェルビーイングとは?ビジネスにおける本質的な意味と重要性
ウェルビーイング(Well-being)とは、単に病気でない、あるいは弱っていないという状態を指すのではなく、身体的・精神的・社会的にすべてが満たされた、良好で幸福な状態にあることを意味します。これは世界保健機関(WHO)による健康の定義にも通じる考え方です。
ビジネスの文脈におけるウェルビーイングは、従業員一人ひとりが仕事や私生活において充実感を持ち、心身ともに健康で、自らの能力や個性を最大限に発揮できる状態を目指すものです。企業が従業員のウェルビーイング向上を支援することは、もはや単なる福利厚生の範疇を超え、企業の持続的な成長と競争力を支える重要な経営戦略として捉えられています。
ウェルビーイングの構成要素についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
企業が今、ウェルビーイングに取り組むべき社会的背景
企業がウェルビーイング経営に注目し、積極的に投資するようになった背景には、以下のような複合的な社会的・経済的変化があります。
- 働き方の多様化とコロナ禍の影響: リモートワークの普及などにより、従業員の働き方は大きく変化しました。一方で、コミュニケーションの希薄化や仕事と私生活の境界の曖昧化が進み、メンタルヘルスへの配慮や自律的な働き方の支援が一層求められるようになりました。
- 従業員エンゲージメントの重視: 従業員が仕事に対して持つ「熱意」「没頭」「活力」といったエンゲージメントの度合いが、企業の生産性や業績に大きく影響することが明らかになっています(ギャラップ社調査など)。ウェルビーイングの向上は、このエンゲージメントを高めるための重要な鍵となります。
- 人材獲得競争の激化と定着の重要性: 少子高齢化に伴う労働力人口の減少が進む中、優秀な人材の獲得とリテンション(定着)は企業にとって死活問題です。特に若い世代は、報酬だけでなく「働きがい」や「自己成長」、「心理的安全性」といったウェルビーイングに関連する要素を企業選択の重要な基準とする傾向があります(日本労働政策研究・研修機構調査など)。
参照:厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析」:https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3.pdf
ウェルビーイング経営が企業にもたらす具体的なビジネスメリット
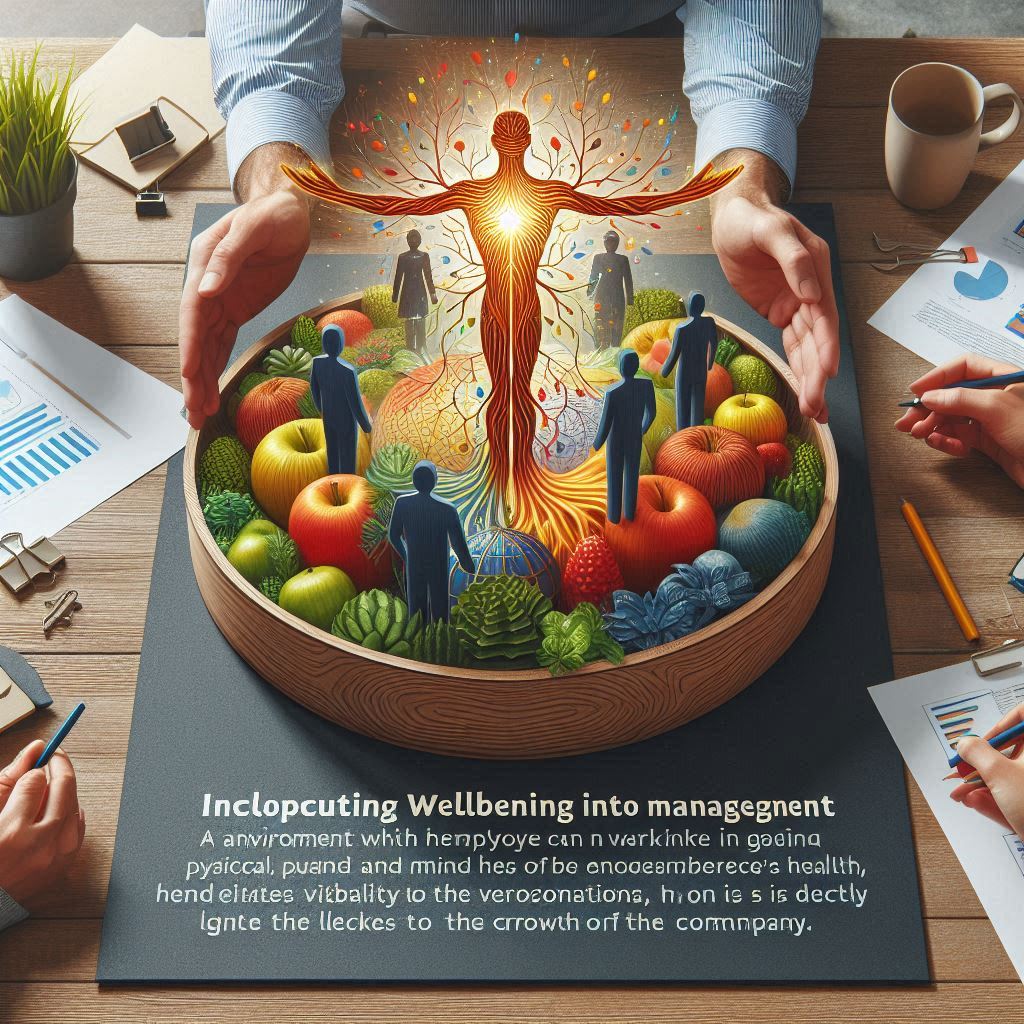
ウェルビーイングへの投資は、単に従業員のためだけでなく、企業経営に具体的なリターンをもたらす戦略的な取り組みです。ここでは、従業員の幸福が企業の成長にどう結びつくのか、主要なビジネスメリットを解説します。
メリット1:生産性向上とイノベーション創出の促進
従業員が心身ともに健康で、仕事に前向きに取り組める状態は、個々の集中力や業務効率を高め、組織全体の生産性向上に直結します。厚生労働省の調査(※)でも、メンタルヘルス不調によるパフォーマンス低下が企業の生産性に大きな影響を与えることが示されています。
逆に、ウェルビーイングが高い職場では、従業員のストレスが軽減され、創造性や問題解決能力が刺激されるため、イノベーションが生まれやすい環境が育まれます。
参照:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo01.pdf
H3: メリット2:企業ブランドイメージと社会的評価の向上(ESG投資との関連)
ウェルビーイング経営に積極的に取り組む企業は、「従業員を大切にするホワイトな企業」というポジティブなブランドイメージを社会に発信できます。これは、顧客からの信頼獲得や製品・サービスの選択において有利に働くだけでなく、投資家からの評価にも繋がります。
近年注目されるESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)において、従業員のウェルビーイング(人的資本への配慮)は「S(社会)」の重要な評価項目の一つです。「健康経営銘柄」や「ホワイト500」といった認定制度も、企業の社会的評価を高める上で有効です。
健康経営について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
メリット3:従業員エンゲージメントの向上と人材確保・定着
ウェルビーイングを重視する職場環境は、従業員が会社や仕事に対して持つ愛着や誇り、貢献意欲(エンゲージメント)を高めます。自分の健康や幸福が組織によって尊重されていると感じる従業員は、より主体的に業務に取り組み、組織目標の達成に向けて力を発揮する傾向があります。
また、心理的安全性が高く、良好な人間関係が築かれている職場は、従業員の定着率を向上させ、採用コストの削減や組織知の蓄積にも繋がります(リクルートワークス研究所調査など)。
参照:https://www.works-i.com/research/report/item/hatarakigai-survey.pdf
ウェルビーイングを経営戦略として導入・推進するための5つのポイント

ウェルビーイング経営を単なるスローガンに終わらせず、企業文化として定着させ、具体的な成果に結びつけるためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、そのための5つの重要なポイントを解説します。
経営層の理解と全社的な推進体制の構築
ウェルビーイング経営の成功は、経営トップの強いコミットメントとリーダーシップから始まります。経営層がウェルビーイングの重要性を深く理解し、明確なビジョンと方針を全社に発信することが不可欠です。
その上で、人事部門、健康管理部門、各事業部門などが連携する推進体制を構築し、専任の担当者やチーム(例:チーフ・ウェルビーイング・オフィサー(CWO))を設置することも有効です。
従業員の現状とニーズの的確な把握
効果的なウェルビーイング施策を展開するためには、まず自社の従業員がどのような健康課題を抱え、どのようなサポートを求めているのかを正確に把握する必要があります。
定期的な健康診断結果の分析、ストレスチェックの実施、従業員サーベイ(満足度調査、エンゲージメント調査など)、個別インタビューなどを通じて、定量的・定性的なデータを収集し、課題を特定します。
具体的な施策の計画と多角的な実行(働き方、メンタルヘルス、環境など)
把握された課題とニーズに基づき、具体的なウェルビーイング施策を計画し、実行します。これには、以下のような多角的なアプローチが含まれます。
- 働きがいのある仕事の設計: 裁量権の付与、キャリア成長の機会提供、公正な評価制度など。
- 柔軟な働き方の推進: フレックスタイム、リモートワーク、時短勤務、休暇取得促進など。
- メンタルヘルスケアの充実: カウンセリング窓口設置、ストレスマネジメント研修、ラインケア教育など。
- 健康増進プログラムの提供: フィットネス支援、健康的な食事の提供、禁煙支援など。
- 快適で安全な職場環境の整備: 人間工学に基づいたオフィス家具、適切な照明・空調、リフレッシュスペースなど。
定期的な効果測定と改善サイクルの確立
ウェルビーイング施策は、実施して終わりではありません。導入した施策が実際にどのような効果をもたらしているのかを定期的に測定・評価し、その結果に基づいて改善を重ねていくPDCAサイクルを確立することが重要です。KPI(重要業績評価指標)としては、従業員の健康指標、エンゲージメントスコア、生産性指標、離職率などが考えられます。
テクノロジーの適切な活用
近年では、AIやIoT、ウェアラブルデバイスといったテクノロジーを活用し、ウェルビーイング施策をより効果的かつ効率的に展開する動きも広がっています。例えば、従業員の健康状態をリアルタイムでモニタリングしたり、個別最適化された健康アドバイスを提供したりするシステムなどがあります。
ただし、テクノロジー導入ありきではなく、あくまで目的達成のための手段の一つとして、プライバシーへの配慮を十分に行った上で慎重に検討することが肝要です。
テクノロジー活用の詳細は以下記事をご参照ください
企業の成功事例から学ぶウェルビーイング経営の実践

ウェルビーイング経営は、理想論ではなく、すでに多くの企業が実践し成果をあげている現実的な戦略です。特に先進的な取り組みを行っている企業の事例からは、制度や施策だけでなく、現場に根づかせる工夫や課題との向き合い方まで、多くのヒントを得ることができます。
NECソリューションイノベータの事例
NECソリューションイノベータは、「Well-being経営」を経営戦略の一環と位置づけ、社員の心身の健康、成長、働きがいを支える取り組みを進めています。2024年度からは「健康」「成長」「働きがい」の3つのテーマで個人の価値向上を目指す全社プロジェクトを立ち上げ、部門横断型のワーキンググループを組成。社員の声を反映しながら、産業医や安全衛生委員会とも連携し、実効性のある施策を展開しています。
注目されるのは、同社が自社で開発・運用している「健康ミッションアプリ」の導入です。このアプリは、運動や食事など日々の健康行動を“ミッション”として提示し、社員が楽しみながら生活習慣を改善できる仕組みです。ポイント獲得や仲間とのコミュニケーションを通じて、健康への意識向上と行動変容を促進しています。
さらに、デジタルツールを活用して健康課題を可視化し、対策へとつなげている点も特筆すべきポイントです。例えば、社内調査で明らかになった「運動不足」や「メタボ予備軍の多さ」といった課題に対し、生活習慣改善に向けた施策を重点的に行っています。こうした継続的な取り組みが、社員のウェルビーイング向上と企業の活力につながっています。
参照:https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/csr/society/healthcare.
Works Human Intelligenceの取り組み
人事システム開発大手のWorks Human Intelligenceは、自社のHRテクノロジーを活用した先進的なウェルビーイング戦略を展開しています。同社は、従業員の自律的な学習と企業の戦略的な研修を両立させる学習プラットフォーム「COMPANY Learning Platform」を提供しています。
このプラットフォームは、従業員が自らのキャリア目標や個人のニーズに合わせて学習できる環境を提供し、AIによるコンテンツのリコメンド機能や、他の従業員との学習共有機能を備えています。これにより、従業員のモチベーション維持やスキル向上を支援し、組織全体の生産性向上に寄与しています。
さらに、同社は統合人事システム「COMPANY®」を通じて、健康管理システムCarelyとの連携を実現し、人事データと健康データの統合管理を可能にしています。これにより、従業員の健康状態を把握し、適切なサポートを提供することで、ウェルビーイングの向上を図っています。
これらの取り組みを通じて、WHIは従業員のウェルビーイングを重視し、働きやすい環境の整備と個々の成長支援を実現しています。
参照:https://www.works-hi.co.jp/news/20240423
ミイダスのデータ活用事例
タレントマネジメントシステムを提供するミイダスは、「適材適所」をキーワードにしたユニークなウェルビーイング戦略を展開しています。同社は、自社開発のアセスメントツールを全社員に適用し、個々の特性や強みを科学的に分析。その結果を基に、各人の適性に合った業務配置を行うことで、仕事の満足度と生産性の向上を実現しています。
さらに、同社は「組織サーベイ」を導入し、従業員のコンディションを定期的に把握しています。これにより、ストレスやモチベーションの状態を可視化し、適切なフォローアップを行うことで、働きがいのある職場環境の構築に努めています。
これらの取り組みにより、ミイダスは従業員の満足度と生産性の向上を実現し、離職率の低下にも寄与しています。また、これらの実践から得られた知見をもとに、クライアント企業にも適性検査や組織診断のサービスを提供し、適材適所の人材配置を支援しています。
参照:https://corp.miidas.jp/landing/survey
ウェルビーイング経営の今後の動向と日本企業が直面する課題

ウェルビーイング経営は、今後ますますその重要性を増し、進化していくと考えられます。ここでは、最新のトレンドと、特に日本企業がその推進において直面しやすい課題、そして今後の展望について考察します。
AIやデータ活用によるパーソナライズ化の進展
AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータ解析といった技術の進化は、ウェルビーイング支援のあり方を大きく変えつつあります。従業員一人ひとりの健康データ、勤務データ、コミュニケーションデータなどを統合的に分析し、個々のニーズや特性に合わせた、よりきめ細やかで効果的なサポート(パーソナライズド・ウェルビーイング)を提供することが可能になっています。
例えば、個人のストレスレベルや睡眠パターンに基づいて最適な休息タイミングを提案したり、特定の健康リスクを予測して予防的介入を促したりするような活用が期待されます。
人的資本経営とESG投資におけるウェルビーイングの位置づけ
ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の世界的な拡大に伴い、企業の「人的資本」への取り組みが投資家からの評価を左右する重要な要素となっています。
従業員のウェルビーイングは、この人的資本の中核的要素であり、その開示情報(例:従業員エンゲージメントスコア、健康関連指標、ダイバーシティ&インクルージョンへの取り組み状況など)は、企業の持続可能性や将来的な成長性を判断する上で重視されています。
SASB基準(サステナビリティ会計基準審議会が策定)のような国際的な開示フレームワークにおいても、人的資本に関する項目の重要性が高まっています。
日本企業がウェルビーイングを推進する上での課題と展望
日本企業がウェルビーイング経営を本格的に導入・推進していく上では、いくつかの特有の課題も存在します。
- 短期的な成果主義との両立: ウェルビーイングへの投資は、効果が表れるまでに時間を要することが多く、短期的な業績目標とのバランスをどう取るかが経営判断の難しい点です。
- 組織文化の変革: 年功序列や長時間労働を是とするような旧来型の組織文化や、過度な同調圧力などが、個人のウェルビーイングを尊重する文化の醸成を阻害する場合があります。特に管理職層の意識改革とリーダーシップが鍵となります。
- 効果測定とROIの可視化: ウェルビーイング施策の投資対効果(ROI)を客観的に測定し、経営層に説明することが難しいという課題も挙げられます。
これらの課題を克服するためには、経営トップの強いリーダーシップのもと、長期的な視点に立った戦略策定、データに基づいた効果検証、そして何よりも従業員の声に真摯に耳を傾け、共に企業文化を創り上げていく姿勢が求められます。
ウェルビーイングを経営戦略の中核に据え、持続的な企業価値向上を目指す

ウェルビーイングとビジネスの関係は、もはや「あれば良い」という付加的なものではなく、持続的な企業成長のための必須要素となっています。本記事で見てきたように、従業員の心身の健康と幸福感は、生産性向上、イノベーション創出、人材確保・定着など、直接的なビジネス成果に結びついています。
企業の事例からも明らかなように、データに基づいた科学的アプローチと経営戦略としての一貫した取り組みが成功の鍵となります。また、AIやデジタルツールの活用、ESG投資との連動など、ウェルビーイング経営の手法は今後さらに進化していくでしょう。
これからの企業には、単なる制度や施策の導入にとどまらず、組織文化そのものをウェルビーイング志向に転換していくことが求められます。「人」を中心に据えた経営が、結果として企業の持続的な競争力と社会的価値の向上につながるのです。
ウェルビーイング経営は特別なものではなく、これからのビジネスの標準となっていきます。今こそ、自社のウェルビーイング戦略を見直し、従業員と企業がともに成長できる好循環を生み出す時です。未来の働き方に向けて、一人ひとりの幸福と組織の成功を同時に実現する経営へと舵を切りましょう。
WRITER
NeuroTech Magazine編集部
BrainTech Magazine編集部のアカウントです。
運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。
一覧ページへ戻る


