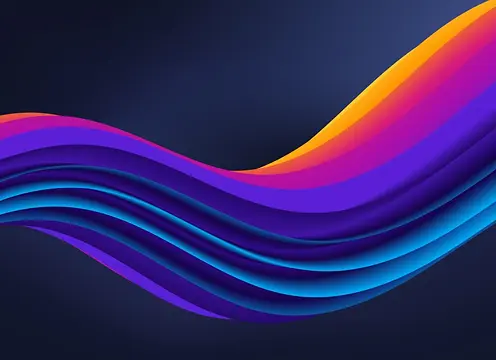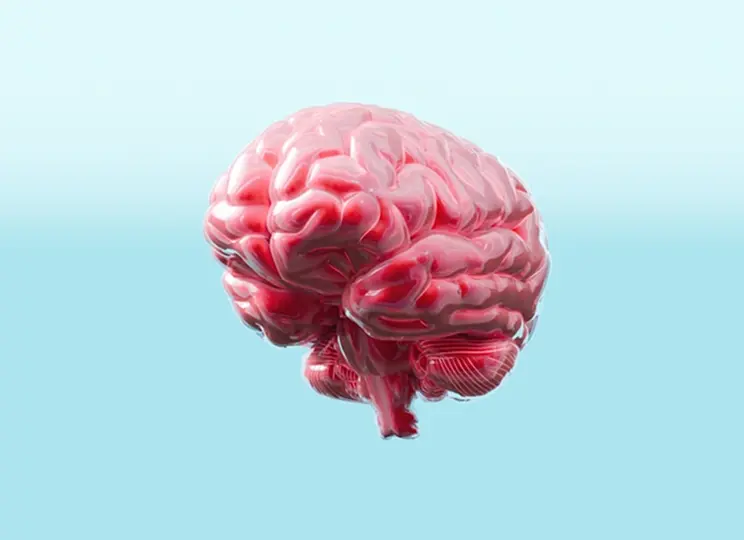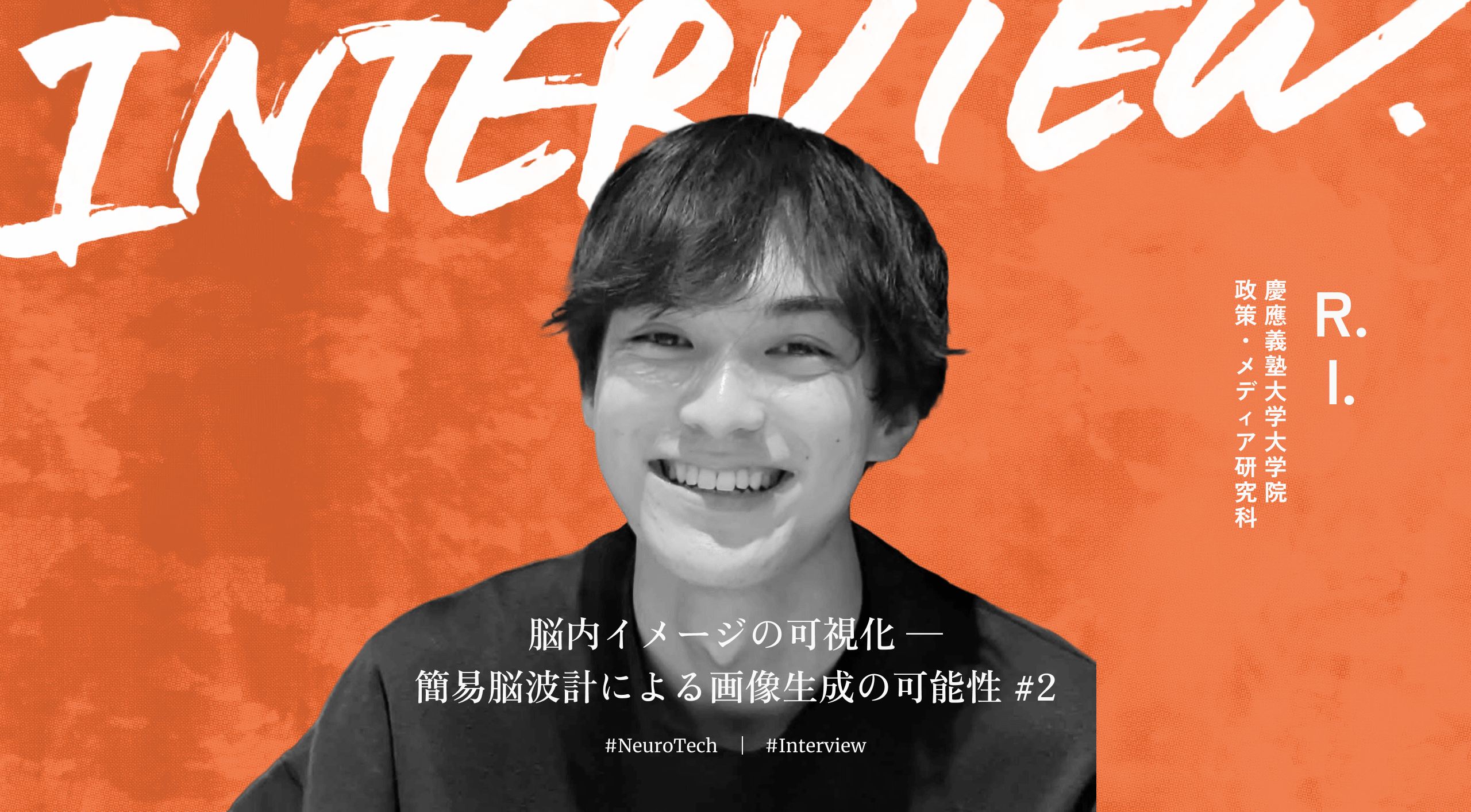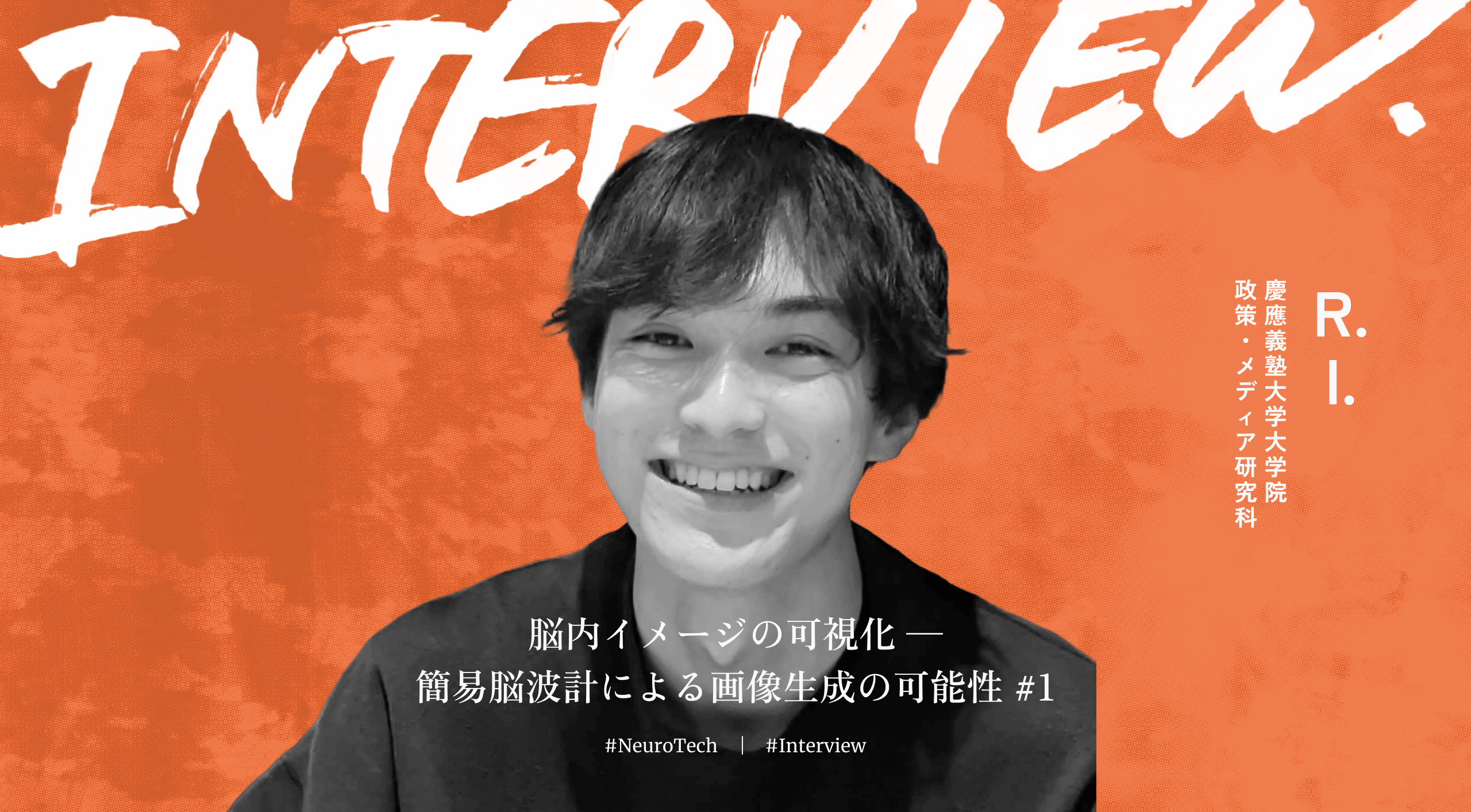脳波に出会って見えた未来:研究者・R.I.さんの研究に活かされたインターンでの日々
今回は、慶応義塾大学で「簡易型脳波測定器を用いた意図画像探索」について研究されているR.I.さんにお話を伺いました。インタビューの前半では、R.I.さんの研究に至るまでの背景やこれまでの研究成果などについて詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。 前半記事 ▶脳波による画像生成:慶應義塾大学・R.I.さんが語る「想起イメージの再現」 今回のインタビューの後半では、R.I.さんのパーソナルストーリーに焦点を当て、大学での生活や現在の趣味、研究活動に関するエピソードなどについて伺いました。 研究者プロフィール 氏名:R.I.所属:慶應義塾大学大学院 政策メディア研究科研究室:中澤・大越研究室研究分野:EEG、ニューロアダプティブ、画像生成 インターンでの経験が研究方針を決めた 前半の記事で「インターンがきっかけで脳に興味をもった」と述べられていましたが、インターンではどのようなことをしていたのでしょうか? 当初は主に脳科学の研究論文をまとめる業務を担当していました。4年目の現在は、脳波実験環境のプログラミングを始めとした技術的な仕事を任せてもらっています。 普段からプログラミングはされているのですか? はい。普段は、主に研究に利用するモデルの構築と、競技プログラミングへの参加を通してプログラミングには触れています。 業務以外で何かアプリケーションを開発した経験はありますか? 過去にシステム開発の手順を学ぶために、フリーライドシェアの予約を行うアプリケーションを開発しました。他にもエアホッケーゲームなどのちょっとしたアプリケーションの開発は何度か経験しています。 R.I.さんが制作したエアホッケーゲーム 脳波に興味をもつようになった具体的なエピソードはありますか? インターンでは脳科学の知見を用いたコンサルティングも行っています。そこでの活動を通じて脳科学、および脳波計測による実験を通してクライアントの要望を解決する様子を目の当たりにして、その応用可能性と社会貢献性の高さに強く惹かれました。 趣味は読書、科学に留まらない幅広い知的好奇心 研究以外で現在ハマっている趣味はありますか? 読書にハマっています。小学校から高校までオランダで過ごしていたため、文学を多く読む教育を受けていたこともあり、小さい頃から日常的に本を読んでいました。もともとは科学系の本を中心に読んでいたのですが、現在は文学や哲学といった幅広いジャンルの本を読んでいます。 長い間海外で過ごされていたのですね。最近読んだおもしろい本はありますか? 最近読んだおすすめの本は、ミラン・クンデラさんが書かれた「存在の耐えられない軽さ」です。この本では、プラハの春というチェコスロヴァキアで起きた民主化運動の中での人間関係の話が綴られています。 一般的な文学では愛や責任といった人間関係の重さに着目しているものが多いのですが、この本はその逆で、政治体制が変わってしまったことで、自分がそれまでに積み上げてきたものが一瞬で崩れ去ってしまう虚しさや、誠実に生きてこなかったために、人生の中盤でミッドライフ・クライシスを感じて人間関係が崩れてしまうといった、人間という存在の軽さが描かれていて、とても興味深い内容でした。 オランダに住み始めた当初はどのような気持ちで過ごしていたのですか? 初めは言語がわからない中で面識のない外国人に囲まれて過ごしていたため、非常に心細かったです。人間関係を構築することも困難であったため、住み始めてからしばらくはひたすら耐え忍ぶ日々が続き、その間すがる思いで本を読んでいました。 現地での生活に慣れ始めたのは、引っ越してからおよそ2年後でした。拙いながらも自分からコミュニケーションを取れるようになった瞬間から、当初あった不安な思いはなくなりました。それからは、毎日が学びの連続でした。日本と異なる言語や文化に触れた経験は自分の価値観の形成に大きく影響しており、現在の活動や意思決定の根底に深く根付いていると感じています。 海外生活で得た学びが、現在のご自身を形作っているのですね。 データサイエンスで国を代表する人間を目指して 将来の夢や目標はありますか? 大学で学んだことを活かして、データサイエンスの分野で日本を代表するような人間になりたいと考えています。長い間海外で生活してきたことで、世界で活躍することに強い関心をもっているので、自身の専門性を活かしてこの国の技術を底上げするような存在になりたいです。 その夢を達成するために、これからどのようなことに取り組んでいきたいと考えていますか? データに関する技術、運用、ガバナンス戦略など、あらゆる側面において深い知識を身につけていきたいと考えています。そのためには、キャリアの中で様々な立場を経験しながら、データに対して幅広く向き合っていくことが重要だと思っています。 また、最先端技術の動向を常に把握する必要があるため、将来的には海外での経験を積む機会を持ちたいと考えています。 それでは最後に、これから同じ領域に挑戦してみたい学生や若い研究者に向けて、メッセージをお願いします。 脳波を扱う研究は常にノイズとの闘いであり、非常にチャレンジングな分野だと考えています。それゆえに、まだまだ発展途上の領域でもあります。そんな可能性に満ちた脳科学に興味を抱き、日々研究に取り組んでいます。もしそういった思いをお持ちでしたら、ぜひ挑戦してみてほしいと思います。 NeuroTech Magazineでは、ブレインテック関連の記事を中心にウェルビーイングや若手研究者へのインタビュー記事を投稿しています。 また、インタビューに協力していただける研究者を随時募集しています。応募はこちらから→info@vie.style