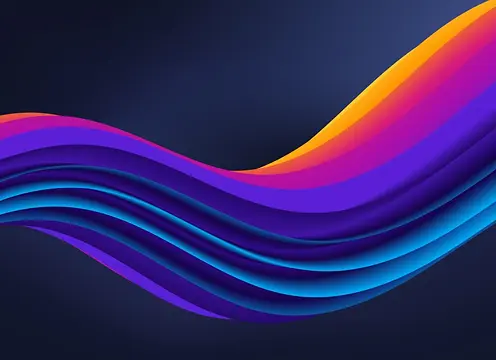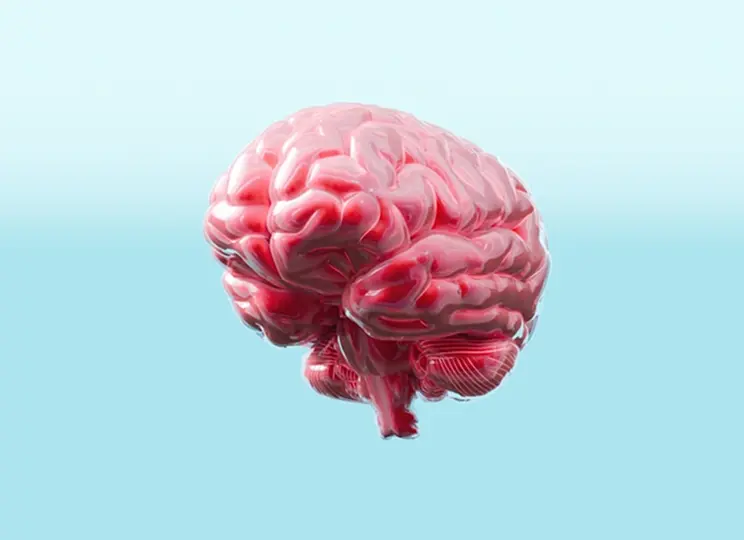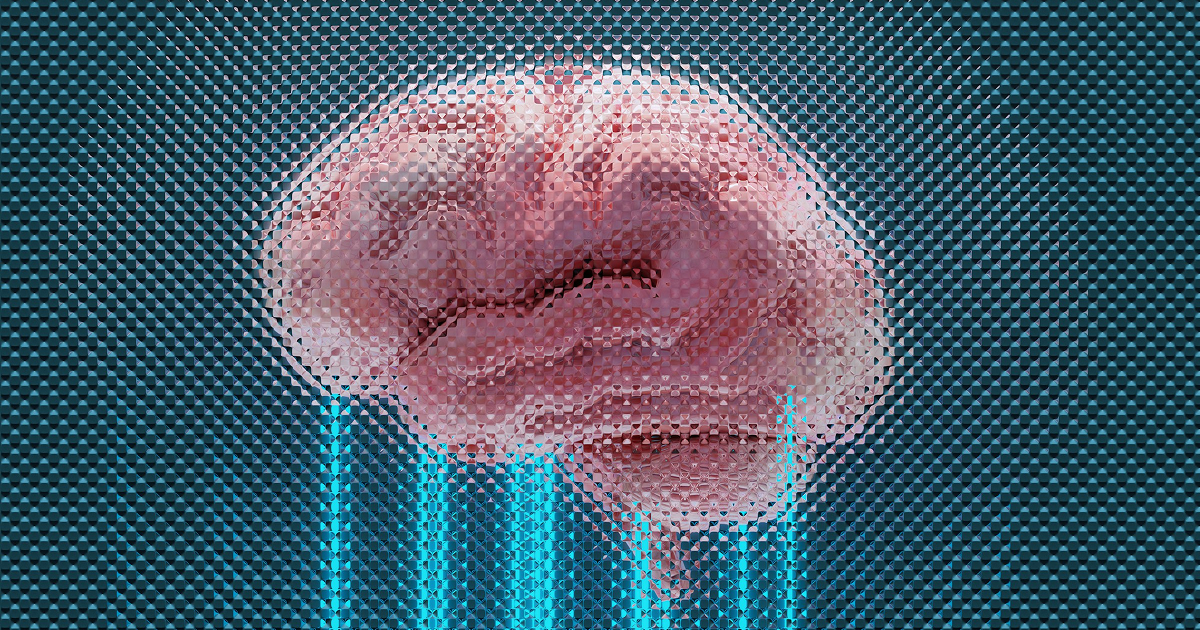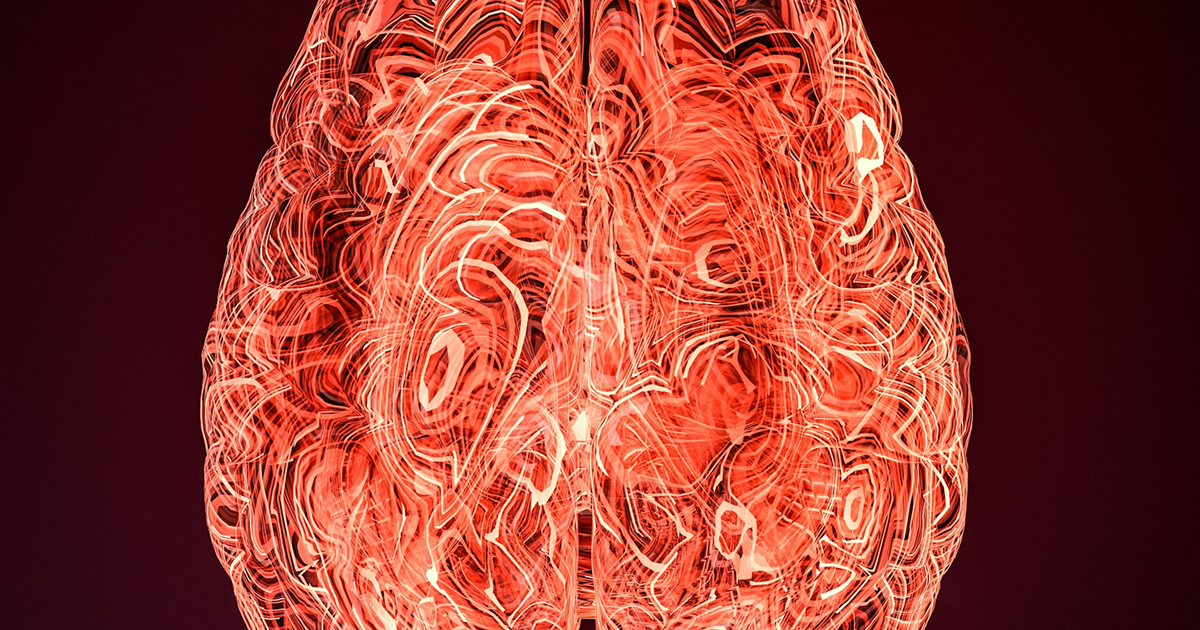もやもや病とは?診断されたら知っておきたい基礎知識と支援制度まとめ
もやもや病は、まだ多くの人にとってなじみのない病気かもしれませんが、子どもから大人まで幅広い年代で発症する可能性があり、日常生活にも大きな影響を及ぼします。発作的に現れる手足の麻痺や言葉の障害、突然の頭痛や意識障害──その背景には、脳の血管に起こる特徴的な変化があります。 この記事では、もやもや病の基本的な特徴から診断方法、日常生活で気をつけたいこと、支援制度の活用までをやさしく解説します。 もやもや病の基礎知識 もやもや病は、脳の血管が徐々に狭くなり、最終的に閉塞することで、その先に異常な新生血管(もやもや血管)が出現する指定難病です。この病態は、脳への血流が不足することで様々な神経症状を引き起こします。 もやもや病とは? もやもや病とは、脳の主要な血管である内頸動脈の末端や、そこから分かれる血管が徐々に狭くなり、最終的に詰まってしまう進行性の疾患です。 この血管の閉塞にともない、脳の底部では血流を補うために、細くてもろい異常な血管が網の目のように発達します。これらの血管は、特に重要な脳血管造影検査において、まるで煙のようにもやもやと映し出されることから、「もやもや病」という特徴的な名前がつけられました。 発症のピーク もやもや病は、発症が特定の年齢層に集中する傾向があり、発症年齢にはふたつのピークがあるとされています。 小児期(5〜10歳頃)この時期には、脳虚血発作(手足のしびれや麻痺、感覚障害、言語障害など)がよく見られます。特に、熱い食べ物をフーフーと吹く、ハーモニカを吹く、激しく泣くといった過呼吸を伴う行動がきっかけとなり、一時的な麻痺や言葉の障害などの症状が誘発されやすいとされています。まれに、意識障害に至ることもあります。 成人期(30〜40歳頃)成人では、脳出血で発症するケースが多く、小児とは異なる症状が目立ちます。脆弱なもやもや血管が破れて出血を起こし、突然の頭痛、意識障害、麻痺など重篤な症状につながることがあります。 日本におけるもやもや病の現状と背景 もやもや病は、世界的に見ても日本を含む東アジア地域に患者が多いことが知られています。その背景には遺伝的要因が関与している可能性が指摘されていますが、具体的なメカニズムはまだ完全には解明されていません。 日本では、もやもや病はその希少性と治療の困難性から、厚生労働大臣が定める「指定難病」に認定されています。これにより医療費助成の対象となり、患者の経済的負担が軽減されます。また、指定難病に認定されていることは、もやもや病の研究促進や治療法の開発、そして患者のQOL(生活の質)向上に向けた支援が引き続き必要であることを示しています。 もやもや病の主な症状とその特徴 もやもや病の症状は、脳の血流が不足する「虚血」によるものと、血管が破れて出血する「出血」によるものの大きく二つに分けられます。また、発症年齢によっても症状の現れ方が異なる特徴があります。 虚血型・出血型 もやもや病の臨床症状は、病態に応じて大きく「虚血型」と「出血型」の二つに分類されます。 虚血型:脳への血流が一時的、あるいは慢性的に不足することで起こる症状です。主に内頸動脈など既存血管の狭窄や閉塞により脳血流が低下し、神経機能に障害が生じます。脆弱なもやもや血管が十分に血流を補えない場合や、その血流の供給が不安定な場合にも、虚血症状が生じることがあります。 出血型:もろく脆弱なもやもや血管が破綻し、脳内に出血が生じることで起こる症状です。脳内で出血が起こると、周囲の組織が押しつぶされてしまい、突然の意識障害や麻痺といった重い症状が現れることがあります。 小児と成人で異なる症状 もやもや病は、発症する年齢によって症状の傾向が大きく異なります。 ▶ 小児期(5〜10歳ごろ) 小児では虚血型の症状が中心です。脳の血流が一時的に不足することで、以下のような症状が繰り返し現れます: 手足の麻痺・しびれ 感覚障害 言語障害(言葉が出にくい、うまく話せない) 特に、熱い食べ物をフーフーと吹く、ハーモニカを吹く、激しく泣くというような、過呼吸を伴う行動がきっかけとなり、症状が誘発されやすいとされています。 これらは、呼気による二酸化炭素の低下 → 脳血管の収縮 → 血流悪化 というメカニズムを通じて発作を引き起こします。また、頭痛や知能発達の遅れが見られることもあります。 ▶ 成人期(30〜40歳代) 成人では、出血型の症状が中心で、もやもや血管の破綻による脳出血が主な原因です。典型的な症状には: 突然の激しい頭痛 意識障害 片側の手足の麻痺 感覚障害 出血の範囲や場所によっては、命に関わる重篤な状態に陥ることもあります。 なお、成人でもまれに虚血型(脳梗塞)で発症することがありますが、小児に比べて頻度は低いとされています。 一過性脳虚血発作(TIA)の具体例 一過性脳虚血発作(TIA)は、もやもや病の虚血症状の典型的な現れ方の一つです。脳への血流が一時的に途絶えることで、脳機能が一時的に麻痺する状態を指します。症状は数分から数時間で完全に消失するのが特徴ですが、本格的な脳梗塞の前触れである可能性があります。 具体的な例としては、以下のような症状が挙げられます。 食事中に箸を持った手が急に動かせなくなる 文字を書いている途中で手がしびれて字が書けなくなる 急に言葉が出なくなり、話せなくなる 片方の目が見えにくくなる、または視野の一部が欠ける 歩いている最中に片足がもつれる、力が抜ける これらの症状は、脳のどの領域の血流が障害されたかによって異なり、繰り返し起こることで患者さんや周囲の人に病気の存在を気づかせるきっかけとなります。 無症候性もやもや病 もやもや病の中には、脳血管造影検査で特徴的な異常血管(もやもや血管)が確認されるにもかかわらず、患者さん自身が自覚できる神経症状が全く現れない「無症候性もやもや病」と呼ばれるタイプも存在します。 これらの患者さんは、他の病気の検査中に偶然発見されたり、家族に症状のあるもやもや病患者がいるために検査を受けて判明したりすることがあります。 無症状であっても、将来的に脳虚血発作や脳出血を発症するリスクは存在するため、定期的な経過観察が重要となります。特に小児の場合は、自覚症状がなくても認知機能の発達に影響が出る可能性もあるため、専門医による慎重な経過観察が必要です。 もやもや病の原因とリスク要因 もやもや病の発症メカニズムはまだ完全に解明されていませんが、遺伝的素因が病気のなりやすさに深く関与していることが明らかになっています。特に、特定の遺伝子の変異が、病気の発症リスクを高める重要な要因と考えられています。 もやもや病と特定遺伝子の関連性 もやもや病には、生まれつきの体質(遺伝)が関係していることが分かっています。その中でも特に重要とされているのが「RNF213」という遺伝子の変化です。 2011年に日本の研究チームが、このRNF213という遺伝子が、もやもや病を発症しやすくなる原因のひとつであることを発見しました。中でも「p.R4810K」という名前の変化は、日本を含む東アジアの患者に多く見つかっています。 RNF213は、血管の発達や維持に関わる遺伝子と考えられています。ただし、この変化がどのようにして脳の血管を狭くしたり、もやもやとした異常な血管をつくるのか、その仕組みはまだ完全には解明されていません。 また、この変化を持っている人が全員もやもや病を発症するわけではなく、他の遺伝的要因や環境要因も関係していると考えられています。 参考:Liu W, Morito D, Takashima S, et al. "Identification of RNF213 as a Susceptibility Gene for Moyamoya Disease and Its Possible Role in Vascular Development." PLoS One. 2011 Jul 20;6(7):e22542. doi: 10.1371/journal.pone.0022542. Epub 2011 Jul 20. 家族性発症 もやもや病は、家族内で発症する「家族性発症」のケースが存在します。全体のもやもや病患者のうち、約10~20%が家族性発症であると報告されています。これは、遺伝的要因が病気の発症に深く関わっていることを強く示唆しています。 家族性発症の多くは、先に述べたRNF213遺伝子の変異が関与していると考えられています。しかし、この遺伝子変異がなくても家族内で発症するケースや、逆に遺伝子変異があっても発症しないケースも存在するため、遺伝子変異の有無だけで発症を断定することはできません。 環境要因や他の疾患との関係 もやもや病の発症には、遺伝的要因だけでなく、複数の環境要因や他の疾患が関与している可能性も指摘されています。しかし、現時点では特定の環境要因が直接もやもや病を引き起こすという明確な証拠は確立されていません。 一方で、もやもや病には合併しやすい疾患や、病状が悪化しやすくなる要因がいくつか知られています。代表的なものは以下の通りです。 甲状腺疾患(バセドウ病や橋本病): もやもや病患者において、甲状腺疾患の合併が高頻度に見られることが報告されています。両者の関連性についてはまだ不明な点が多いですが、免疫学的メカニズムの関与が示唆されています。 ダウン症候群: ダウン症候群の患者にも、もやもや病の合併が見られることがあります。 放射線治療の既往: まれに、過去に頭部の放射線治療を受けた方が、長い年月を経て脳の血管に変化が生じ、もやもや病に似た状態になることがあります。これは放射線の影響による可能性があると考えられていますが、定期的なフォローアップによって、早期に変化に気づくことが大切です。 これらの要因が直接もやもや病を引き起こすわけではありませんが、病態の進行や症状の発現に影響を与える可能性が考えられています。 参考:Almeida, P., Rocha, A. L., Alves, G., Parreira, T., Silva, M. L., Cerejo, A., Abreu, P., & Monteiro, A. (2019). Moyamoya syndrome after radiation therapy: A clinical report. European Journal of Case Reports in Internal Medicine, 6(12), Article 1337. もやもや病の診断方法 もやもや病の診断は、特徴的な脳の血管の変化や、それにともなって起こる血流の異常を確認することで行われます。病気の状態を正確に把握するために、複数の画像検査を組み合わせて総合的に評価します。 画像検査による血管と血流の評価 もやもや病の診断において、画像検査は不可欠です。主に以下の検査が行われます。 MRI(磁気共鳴画像) 脳そのものの状態を詳しく調べることで、脳梗塞や脳出血が起きていないか、脳の萎縮(縮み)がどの程度進んでいるかなどを確認できます。 MRA(磁気共鳴血管撮影) 脳の血管の様子を、体に負担をかけずに調べる検査です。太い血管が細くなったり詰まったりしていないか、また、もやもや病に特徴的な異常な血管ができていないかを確認できます。造影剤を使わずに血管を映し出せるため、体への負担が少ないのが特徴です。 脳血管撮影(カテーテル検査) もやもや病の診断において、脳血管撮影は血管の閉塞や異常血管(もやもや血管)の詳しい状態を把握するために重要な検査の一つです。 細い管(カテーテル)を血管に入れて造影剤を注入し、脳の血管をリアルタイムで詳しく調べます。この検査では、血管がどれくらい細くなっているか、もやもやとした異常な血管がどこにできているか、また、それを補う別の血流の道(側副血行路)がどう発達しているかを、立体的に確認できます。 ただし、体に負担のかかる検査であるため、MRAなどの非侵襲的な検査で強くもやもや病が疑われた場合や、治療方針を決める際に必要なときに行われます。 脳血流検査で機能を確認 血管の形態だけでなく、実際に脳のどの領域で血流が不足しているかを評価するために、脳血流検査も行われます。 ASL(動脈スピンラベリング) MRI装置を用いて、非侵襲的に脳の血流量を測定できる手法です。造影剤を使用しないため、繰り返し検査を行うことが可能です。特定の脳領域の血流低下の有無や程度を評価するのに役立ちます。 PET(陽電子放出断層撮影) 脳の血流の量や、酸素やブドウ糖をどのくらい使っているかを詳しく調べる検査です。放射性の薬を使うため放射線被ばくを伴いますが、脳の働きの状態を調べるのにとても役立ちます。 この検査では、安静にしているときだけでなく、わざと負担をかけた状態でも血流がどう変化するかを見ることができます。これにより、脳が血流不足にどのくらい対応できるか(血流予備能)を確認することができ、治療が必要かどうかを判断する大切な手がかりになります。 もやもや病と診断されたら知っておきたい情報 もやもや病と診断された方が、安心して日々の生活を続けていくためには、症状を悪化させないための生活上の工夫や注意点を知っておくことが大切です。あわせて、利用できる医療費助成や福祉制度についても理解を深めておくと安心です。 日常生活での留意事項 もやもや病患者は、ふだんの生活の中で脳に負担をかけすぎないように気をつけることが大切です。血流の変化をできるだけ安定させるための工夫が必要になります。 過呼吸を避ける 過呼吸は脳血管を収縮させ、脳血流を低下させるため、虚血発作を誘発する可能性があります。熱い麺をフーフーと吹く、ハーモニカを吹く、激しく泣く、笛を吹く、激しい運動をする、大声で歌うといった行為は控えるか、様子を見ながら慎重に行う必要があります。 水分補給の徹底 脱水になると血液がドロドロになり、脳への血流が悪くなるおそれがあります。特に夏の暑い日や、熱が出ているときなどは脱水になりやすいため、こまめに水分をとることがとても大切です。 喫煙・飲酒の影響 タバコは血管を縮めたり、動脈硬化を進めたりするため、もやもや病のある人にとっては原則として禁煙が強く推奨されます。また、お酒も飲みすぎると血圧が大きく変動しやすくなるため、飲む量には注意が必要です。飲酒については、主治医と相談しながら、自分の体の状態に合ったアドバイスを受けることが大切です。 食事 特定の食事制限は基本的にありませんが、動脈硬化の予防という観点からは、バランスの取れた食生活を心がけることが望ましいです。塩分の過剰摂取や、飽和脂肪酸・コレステロールの摂りすぎには注意しましょう。 運動 激しすぎる運動は過呼吸を誘発したり、血圧を大きく変動させたりする可能性があるため、避けるべきです。しかし、全身の健康維持のため、主治医と相談の上、無理のない範囲でのウォーキングなどを行いましょう。 医療費助成制度と支援 もやもや病は国の指定難病であるため、医療費助成の対象となります。 指定難病医療費助成制度 もやもや病は、所定の条件を満たすことで「難病医療費助成制度」の対象になります。この制度を利用すると、医療費の自己負担が軽くなります。 制度を利用するには、お住まいの都道府県に申請して、認定を受ける必要があります。詳しい手続きや条件は、地域の保健所や「難病情報センター」のホームページで確認できます。 参考:難病情報センターHP 患者会・支援団体 もやもや病患者やその家族を対象とした患者会や支援団体が存在します。これらの団体は、病気に関する情報提供、交流会の開催、悩み相談などを通じて、患者さんと家族の精神的なサポートを行っています。同じ病気を抱える人々との情報交換は、病気と向き合う上で大きな支えとなるでしょう。 もやもや病と向き合うために もやもや病は、脳の血管に徐々に変化が起こる指定難病ですが、早めに見つけて、きちんと治療を受けることで、症状の進行を防ぎながら、落ち着いた生活を送ることができます。 症状が出たときはもちろん、検診などで疑われた場合でも、できるだけ早く専門の医師に相談して、詳しい検査を受けることがとても大切です。 この病気とうまく付き合っていくには、正しい知識を持ち、利用できる支援制度を活用することが安心につながります。ふだんの生活で気をつけることを守りながら、定期的に通院し検査を受けることで、脳の状態をしっかり見守ることができます。 患者さんご本人だけでなく、ご家族も一緒に病気について理解を深め、支え合っていくことが大切です。医療機関や患者会、自治体などの支援も活用しながら、安心して日々の暮らしを続けていきましょう。